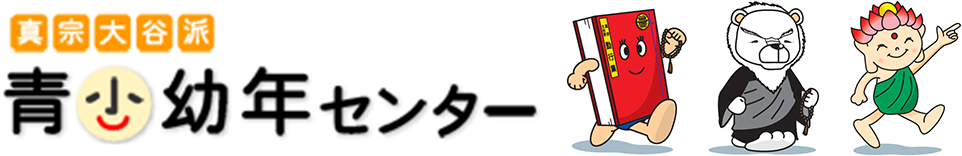8.救済の名のもとに
平野 喜之(金沢教区)
■救いを求めて
「こんなことになるとは思っていなかった」
2018年7月6日に死刑が執行された、オウム真理教元幹部井上嘉浩さんの最後の言葉です。行年48歳でした。その井上さんが中学3年生の時に書いた「願望」という詩の一部を紹介しましょう。
朝夕のラッシュアワー/時につながれた中年達/夢を失い/ちっぽけな金にしがみつき/ぶらさがっているだけの大人達
工場の排水が/川を汚していくように/金が人の心をよごし/大衆どもをクレージーにさす…/時間においかけられて/歩き回る一日がおわると/すぐ、つぎの朝/日の出とともに/逃げ出せない、人の渦がやってくる
救われないぜ/これがおれたちの明日ならば/逃げ出したいぜ/金と欲だけがある/このきたない人波の群れから/夜行列車にのって…
青年期にこのような感情に襲われることは特別なことではありません。そのような感情に襲われたとき、みなさんならどうされるでしょうか?
■教祖と信者
私は井上さんと同じ京都の私立高校に通っていました。高校時代に私もまた彼と似たようなことを感じていて、クラスメートと一緒にある宗教団体に足を運んだことがありました。井上さんもまた高校2年のとき、オウム真理教(当時は、「オウム神仙の会」)の夏季セミナーに参加しました。そのことがきっかけで後に彼は出家し、救済の名のもとに多くの凶悪事件を犯し、死刑判決を言い渡されました。死刑が確定してから約1年後、彼は「蛙の念仏」という詩をよみました。その詩の中で彼は、オウムに入信することになった時の気持ちを「希望の見えない社会に失望し、生きる意味を受験勉強の解答のようにオウム真理教という宗教に求めてしまい」と述べています。では、彼がそこに救いを求めたオウムとはどのような宗教だったのでしょうか?
彼はその「蛙の念仏」という詩の中で、次のように述べています。
考えるな/それはエゴで煩悩で救いはない/空っぽになって言われたことをやりつづけろ
出家した私はこの教えの生活にはまり込み/闇路を走りつづけては自分の足音すら恐くなり/偽善と大義の陶酔の中で目前のワークに没入しました
オウムでは、麻原彰晃(本名:松本智津夫)教祖の存在は絶対的でした。麻原教祖だけがこの汚れ切った社会を救うことのできる最終解脱者(さとりの究極にまで至った人)だと信じられていました。そしてまた意図的に、疑問をもたれないように仕組まれてもいました。それが、「考えるな/それはエゴで煩悩で救いはない/空っぽになって言われたことをやりつづけろ」という教えでした。教祖の指示は絶対で、それがいくら理不尽でもそこには教祖の深いお考えがあるに違いないから信者は黙って言われたことをしていればいい、というものでした。
■誰もが持つ「服従欲」と「救済の陶酔感」
古来、宗祖と呼ばれる人たちのなかで、
「弟子一人ももたずそうろう」 【『歎異抄』/『真宗聖典』(東本願寺出版)・628頁】
と言われたのは、私の知る限り親鸞聖人だけです。教祖という存在は信者にとってどのような存在であるべきなのかを考えるとき、なぜそのように言われたのか、その意図を尋ねずにはおれません。
「わが教祖こそ世界を救う真実の救済者だ。この教祖の教え以外の宗教は全部虚偽だ」。もしみなさんがこのようなことを唱える宗教団体の信者たちと出会ったら、きっと違和感を持たれるに違いありません。しかし教団の内部にいると、それがおかしいということに案外気づきにくいものです。そういう教団は、「教祖から離れると地獄に落ちるぞ」、などと言って脅すこともあります。すでに教団の中にたくさんの知り合いができているということもあります。ですから、仮に教団のおかしさに気づいたとしても抜け出すのには相当勇気がいります。しかし、教団をやめられない理由はそれだけでしょうか?
人間には、自由でありたいという根源的な欲求があります。しかし、自由であるということは、自分自身で物事の是非を判断して行動するということでもあります。そこには、責任も伴います。もし失敗したら、責任は判断した自分に課せられてしまいます。しかし、自分が絶対的に正しいと信じている人に従ってさえいればいい、ということになれば、責任を取らなくてもいいから楽だということがあります。人間にはそういう服従欲とでも呼ぶべき欲望があるからこそ、信者であることをやめるのが難しいのです。
さらには、「自分の信じている教祖は絶対的に正しいのだから、その教祖の教えを実践している自分は正義の味方」と思うことができる陶酔感から覚めたくない、自分は愚かな人たちを教え導く救済者であるという使命感に燃えたいという欲望もあります。だから、教えが少々おかしくても自由がなくても、その気持ちよさがある限り、自由を奪われても自ら信者であり続けようとするのです。
親鸞聖人は
「是非しらず邪正もわかぬ、このみなり、小慈小悲もなけれども、名利に人師をこのむなり」
【「正像末和讃」/『真宗聖典』(東本願寺出版)・511頁】
と、是非も邪正もしらない自分なのに、人を教え導く先生としてみなから慕われたいことを願うそういう愚かな自分であることを深く懴悔されています。この懴悔の言葉は、いつでも「救う側」や「正義の側」に立ちたい私たちの性分を照らす言葉でもあります。親鸞聖人の見方では、法(教え)の前ではみな平等に愚かな凡夫であり、御同朋御同行なのです。もし師と弟子ということがあるなら、互いに師となり弟子となるのです。人間どうしの間には、教祖とか信者というような固定された絶対的な区別はないのです。