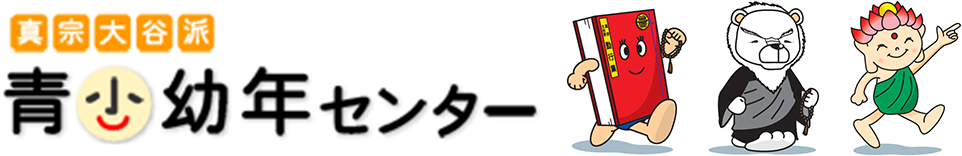24.決断と他者
相馬 晃(九州教区)
<自由な選択ができるはずなのに苦しい>
人は日々決断をして生きています。毎日の洋服の選びや献立決めといった日常の事から、進学・就職・結婚などの大きな進路の選択まで、私達の日々は決断の連続といって良いでしょう。また現代では、進路選択の動機において、家の事情よりも個人の自由が尊重されるように思います。その一方で、進路の選択をどうしたら良いか戸惑ったり、すぐに進路変更することも多くなったように思います。
人生の大きな決断や進路で悩んだり、苦しんだりするのは一体なぜでしょうか。
<進路に迷う私の経験>
 私自身の経験ですが、私は寺の次男として生まれました。寺の直接の跡継ぎではなかったのですが、寺院に関わっていかなければならないという責任感を感じつつ、一方では、社会人として、実家に頼らずに独立しなければならないという義務感を感じていました。高校進学以降は、親や地域の人からよく見られたいという感情から、真面目な尊敬される僧侶にならなくてはならないという思いが強くなっていきました。
私自身の経験ですが、私は寺の次男として生まれました。寺の直接の跡継ぎではなかったのですが、寺院に関わっていかなければならないという責任感を感じつつ、一方では、社会人として、実家に頼らずに独立しなければならないという義務感を感じていました。高校進学以降は、親や地域の人からよく見られたいという感情から、真面目な尊敬される僧侶にならなくてはならないという思いが強くなっていきました。
私がその道に躓いたのは、大学生の頃、地元でお参りをしている時に、ある門徒の方から言われた一言です。「あんたら坊さんは人が死んでそれを喜んでいるんやな」。まったく不意に言われたことで何も返答のしようがなく、ただ自分の進んでいこうとする道はそういう道なのかと呆然としました。そこから、僧侶として生きる道とそれ以外の進路の間で悩み、葛藤し続けていました。
その後、私は進路を悩みながらも、真宗の教えを学ぶ中で「老・病・死」が仏教の課題であることを知り、僧侶という仕事の大切さを少しずつ感じていくようになりました。そうして、私が躓きを感じた時から10年ほど歳月が経ったころだと思います。自分が勤めた葬儀の場でその方にたまたまお会いしました。親族として参列していたその方は、にこっとして私に「今日はありがとうございました」と仰って下さったのです。私はその様子に不思議だなと思いつつも、かつてその方の一言に右往左往していた自分自身を振り返るようになりました。
<他者から評価されたいという心が苦悩を生み出す>
「坊さんは人の死を喜んでいる」との言葉を受けた時、自分は僧侶として一生懸命やっているのに、なぜこの人は認めてくれないのかという思いでした。しかし、考えてみると、他者に認められたいから僧侶をやっているのでしょうか。かつての自分を振り返ると、周囲の期待から立派な僧侶になりたいとただ漠然と思っているだけで、心の底から僧侶だ、と胸を張れるような気持ちではなかったと思います。
仏教では、他者との関わりで生じる人間の自尊心を「勝他・利養・名聞」という言葉で表しています。「勝他」は他人より勝れたいという心、「利養」は自分の利益だけを中心にする心、「名聞」は他人によく見られたいという心です。そういう心がある私たちは、他人に負けたり、自分だけが損をしたり、他人に評価されなくなったら、大変な苦悩を味わうことになります。したがって、この三つの心は私たちに苦しみを生じさせる原因でもあります。
振り返ると、かつての私は周囲から認められたいという「名聞」の思いが強かったのだと思います。そして今現在、この心が無くなったかといえばそうではありません。やはり他人から認められたいという思いはあります。けれども、現在は、周囲に認めてもらえるかどうかは別として、人の生死に関わる僧侶という役割を大切だと思うようになりました。
<他者に振り回されない決断の心構え>
人生における決断や進路選択において、他人の意見を聞くことは大切だと思います。しかし、他人の期待に応えなければならないとか、他人に認められなければ意味がないと思い込み、かえって他人の意見に左右されることはないでしょうか。
ここで釈尊が亡くなる前に語った言葉を紹介します。
この世で自らを島とし、自らをたよりとして、他人をたよりとせず、法を島とし、法をよりどころとして、他のものをよりどころとせずにあれ。【『ブッダ最後の旅』(岩波文庫)P63】
この言葉は、弟子の阿難が釈尊亡き後、誰を指導者と仰げばよいかと問うたのに対して、釈尊が、他者を依りどころとするのではなく、自らが頷いてきた教え(法)を依りどころにしなさいと語られたものです。釈尊が弟子に語られた状況とは異なるかもしれませんが、人生における決断においても、他人に意見や教えを乞うことはあっても、最終的には、人がそう言ったから決めるのではなく、自分の力で考えて決断に責任を持つことが大事なのではないかと思います。
最後に、私自身は今でも決断は苦手です。他者の一言やアドバイスに流されやすいという性格もあります。だからこそ、決断の際には「勝他・利養・名聞」の心を基準としていないか、本当に自分が選んだ道に責任が持てるのか、問い続けるしかないと思っています。