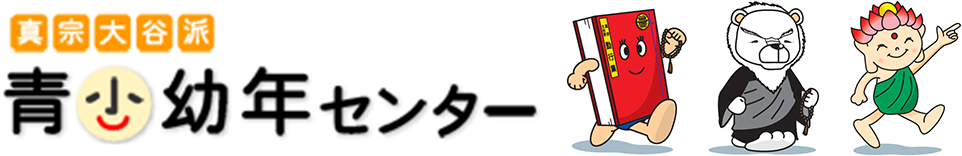25.赤鬼がくる
橘 佑輝(山形教区)
〇聞法を始めた頃
仏教の話はどうもややこしい。聞法を始めた頃、お寺に参って法話を聞いてもさっぱり分からない、そんな日々が続きました。分からないとなると、本堂の畳に座っておるのも何となく気まずいものです。かと言ってせっかくお寺に足を運んだのに、途中で帰るのも勿体ない気がして帰るに帰れず、雨が少し風をつけて斜めに降ったのも手伝って、本堂の縁側に座って過ごしたことがあります。それで庭先にある梅の木の葉っぱやら、平たい虫の這うのやらを眺めたりしていました。ちょうど本尊に背を向けるように座っておりましたから、ぽたぽたという雨音に混じって、後ろから法話がいくらか聞こえてくるのです。
その日は浄土と穢土の話でした。僕たちの暮らしているこの世は穢土といって、煩悩に動かされ互いに傷つけあう場所なんだと。そこでは誰しもが現実にぶつかり、耐え忍んで生きていかざるをえない。対して浄土というのは美しい場所だ。生きていることと願いとがつながる。生きとし生けるものの故郷だと。大体このような話でした。それならばそんな酷い穢土など早うに捨てて、皆して浄土に行ってゆうゆうと暮らしたらええやないか。そんな乱暴なことを思ったものです。
ところが「穢土を荘厳せよ」という言葉で、浄土は行って終いになる場所ではない。我が身は穢土にある。現実に腰を据えるんだと。びしりびしりといった調子で法話が続くものですから、狐につままれたような、謎かけをされたような、釈然としない気持ちで家路に着いたのを覚えています。
〇赤鬼がくる
それから一年ほどして京都のご本山で勤めていた時に、一人のおばあさんからどうしても聞きたいことがあると声を掛けられました。なにが聞きたいのですかと尋ねたら、自分の亡くなった夫が本当にお浄土に往けたのか教えて欲しいという返事が返ってきました。そのおばあさんは遠く熊本から上山されたのでした。
夕方、幾人かで車座を囲みました。聞くと、おばあさんの夫は癌になって、闘病の末に命終わっていかれるのです。治療の甲斐もなく、いよいよモルヒネの量も増えて、せん妄状態に陥っていく時に「赤鬼がくる、赤鬼がくる」と声を絞り出した。で遂にはそれが夫の最期の言葉になったと。
それ以来おばあさんは仏法を聞きに、村々のお寺を参るようになります。でも腑に落ちないのです。どんな人でもお浄土に往くと教えられるたびに、じゃあ夫のあの最期はなんだったのだろうかと思うわけです。極楽浄土にはたして鬼がいるだろうか。やっぱり赤鬼がいるのは地獄ではないだろうか。夫は何ぞ悪いことをして地獄に堕ちたんじゃないか。そう考えると何ともやりきれない。こういう話でありました。
皆しんとして動かず、聞き入っていました。しばらくの沈黙のあとに、同座していた老僧がおばあさんの顔をまっすぐ見て、こんなことを言うのでした。
「これは推測です。察しをつけるしかありませんが、赤鬼というのはアメリカ兵のことではないですか(※注)。年齢から考えても、お連れ合いさんは戦争を体験しておられるはずです。私の父も出征兵でして、物静かな父でしたが、酒をあおった時など戦争の辛い記憶をぽつりぽつりと話すことがありました。その際きまってアメリカ兵のことを赤鬼と呼んでおりました。どうしても忘れることができない恐ろしさが、あの真夏の戦場にあったのでしょう。それが死ぬまで父の心に深く刻まれていたように思えます。きっとお連れ合いさんも若い時分に戦争に行ったことを胸の内にしまって、ずうっと悩んでこられたんでしょう。それで命の終わりに、あらためて自分の戦争体験と向き合った。そういうことではないですか。…自分の人生に問題を感じることは、人間が人間になる第一歩です。ですから間違いなく、お連れ合いさんが歩み始めたその道は、お浄土に続いておりますよ。」
〇人生の終わりに
 どんな人も命の終わりに尋ねることはたったひとつ。自分の人生は果たして意味があったのかどうか、これでしょう。その時に自分の人生は良かった意味があったと言えたら良いのですけど、中々そう言い切るのは難しいことです。預かったこの命をきちんと全うできたとは素直に言えないのです。何といいましょうか、人間には胸の奥に正直さがあって誤魔化せない。自分の人生にふと問題を感じてしまう。最期そこに苦しむのが人間じゃあないか。
どんな人も命の終わりに尋ねることはたったひとつ。自分の人生は果たして意味があったのかどうか、これでしょう。その時に自分の人生は良かった意味があったと言えたら良いのですけど、中々そう言い切るのは難しいことです。預かったこの命をきちんと全うできたとは素直に言えないのです。何といいましょうか、人間には胸の奥に正直さがあって誤魔化せない。自分の人生にふと問題を感じてしまう。最期そこに苦しむのが人間じゃあないか。
でも命の終わりに立って、自らの人生を嘆く背姿は誰かに届いていくのです。なぜならきちんと生きることが出来なかったと嘆く姿は、きちんと生きようとする者の姿だから。必ず誰かに届いていく。届いて、その人を活かすような形で、この世界に響きが残っていく。だから精一杯、生きたらいい。自分ひとりで自分の人生を完結させる必要なんてない。真宗ってそういうことでしょう。
(※注)戦時下においてアメリカ兵を蔑視する表現でありますが、当時僕がその場で聞いた戦争を語る言葉として、そのままの表現で書かせてもらいました。