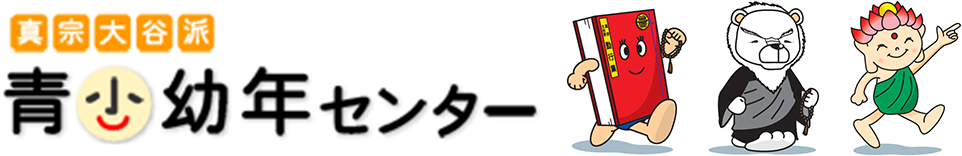28.生老病死を生きていくヒント
太田 宣承(仙台教区)
生老病死に向き合う場を預かる身として
釈尊の教えの根本命題である「生老病死」。生きとし生ける者の至上命題でありながら、現代の私たちは、どこかこの命題をぼかしながら過ごしているように思えてならない。
私の父は、温泉街の中に特別養護老人ホーム「光寿苑」を建てた。
『年老いても、病気になっても、呆け(※)や障がいがあっても、生きる意味や価値が色あせることはない。それを発見できる道場としたい。』
という高らかな理念のもとに築かれてきた場所である。
父の急逝から四半世紀。その灯火を絶やしたくない一心で、私もこの場所でお年寄りや職員と共に生きてみたいと臨んできた。
お年寄りと共に暮らす中で、親鸞聖人の「正像末和讃」の一節がいつも私の心に問いかけてくる。
よしあしの文字をもしらぬひとはみな まことのこころなりけるを
善悪の字しりがおは おおそらごとのかたちなり(『真宗聖典』511頁)
認知症になられた方も、記憶力や判断力が落ちてきた方も、それぞれが喜怒哀楽豊かに過ごしながら、その時その時を豊かな心で生きている。善とか悪とか知っているかのように語ってしまう私の顔を鏡で観てみると眉間に縦皺があるのに気づく。一方、お年寄りたちのお顔には笑い皺などの感情豊かな線が沢山みえる。
老いと病の真っ只中を生きるその方々には、仏様の「まことのこころ」がありのままに届いているように思えて止まないのである。
入居者Aさんから知らされたこと
「光寿苑」にこんなエピソードがある。
入居者Aさん80代女性。入居11年目の春、長男が癌で亡くなる。あまりにも早過ぎた別れ。火葬には参列したものの、母親として何もしてあげられなかった悔しさがあった様子で、わが子との死別から2か月後のお盆が近づいた頃、私にAさんは話した。
『息子が毎晩、私の枕元に立つの。きっとちゃんと見送ってなかったからよ。だから、家に線香あげにいきたいんだけど…。』
すぐにでも自宅にお連れしたかったが、丁度その時期、自宅の改修工事のため、出向く事が叶わなかった。その代わりというのも何だが、僧侶である私は、離れた場所でも仏様と心は行きあえる旨の話をしながら、光寿苑内の仏間で一緒に勤行をした。お勤めも終わり、スッキリした表情のAさん。あくる朝、尋ねてみると、『枕元に立たなくなった。』と言う。その次の日も、またその次の日も見なくなった…と。勤行の日以来、Aさんの枕元に立たなくなった理由。きちんと拝めたことで、母として見送れなかった後悔の念が見せていた幻想とも言える心理状態から解放されたのだと感じた。
そこから半年以上が経った頃、今度はAさんが末期の胃癌となり、看取り期の告知を受けることになる。ただし、家族の意向やAさんの心情も勘案し、本人には明確な告知はしないという方針となった。Aさんは体調自体思わしくなかったが、元気にならなければと、あっさりした物ではあったが食べる努力をしていた。しかし、食べては吐き、食べては吐きを繰り返す苦しい日々が続いた。
Aさんに対して、何か他にやってあげられる事はないか?皆で考えた末、『線香をあげに自宅に帰る』という場面を実現できていない事を思い出す。Aさんに気持ちを聴くと、
『12年、家に戻ってないし、行ってみたいけど、迷惑掛けるしねぇ…』
遠慮しながらも、どこか心残りのある口ぶりと表情。そこで長男妻に相談し、12年ぶりに自宅に一時帰宅する事が決まった。長男妻の提案で、Aさんの誕生日に誕生ケーキを振る舞おうという企画があがった。何を口にしても吐いてしまう状態だっただけに、ケーキは懸念材料ではあったが、嫁が作ってくれた誕生ケーキとあればきっと喜ぶだろうと、お願いをした。
当日は体調も良く、自宅へ。ご仏壇の前で手を合わせ、亡き方々に話し掛けていたというAさん。その後、ささやかな誕生パーティーへ。
ケーキが出て来る。付き添いの職員は洗面器を持ち横で待機していたが、ケーキを5口ほど食べたAさんは不思議と吐く事はなかった。至極の喜びは、人の体や生命力にまで影響するものなのか。
その後、20日間生きたAさん。再び吐く事はあったが、吐きながらも『ありがたい、ありがたい』とわが身のありのままに感謝して生きて、職員の心まで動かした。最後は、長男妻と私の前で安らかに息をひきとった。
人生の最期、一人十色の自分に出遇う
病気と共に生き、やがて生涯を全うするお年寄りたちが出遇いゆく世界にご一緒させて頂いていくにつれ、親鸞聖人の『教行信証』の一節が深く問われてくる。
臨終一念の夕、大般涅槃を超証す。(『真宗聖典』250頁)
〔息を引きとるその時、仏に懐かれ苦悩から解放される(私訳)〕
生きゆく様、死にゆく様、人それぞれの色がある。その色々を良し悪しで感じ受けとめてしまう私に対して、良し悪しを超えた感性をプレゼントしてくださるのが仏の教えである。
最期の時、どんな自分の色で全うしていくのだろう。
生老病死に真に向き合う時、人は「一人十色(いちにんといろ)」の自分らしさに出遇い直すのだと感じる。自分らしさと思っていた以前の色から真逆の色になっても、さらには心の奥底にしまってある色も全部ひっくるめて、色とりどりの私として大事にできたら…。寧ろ浄土の世界から丸ごと大事にされていた私であったと頭が下がる時、苦悩を超越する世界が真に深まっていくのではないだろうか。
※(筆者)現在では「認知症」と表記すべきところではありますが、当時の父の発言のまま「呆け」と使っております。