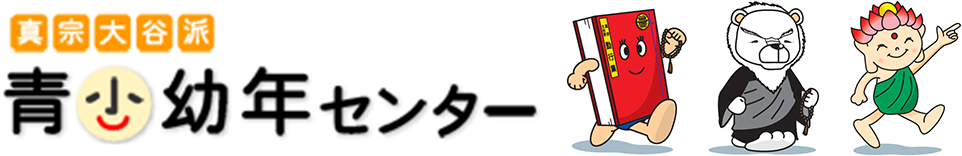32.死者から問われること 死者にたずねること
虎石 薫(高田教区)
誰にも避けられない死
あなたはお葬式に参列したことがありますか。亡くなった方は、家族、親戚、友人、先生、先輩後輩、上司部下、自分より年上であったり年下であったり、同い年であったりしたことでしょう。また、病気、事故、自死、老衰など、死に至る経緯も様々だったことと思います。
お葬式に参列したことがない方もいるはずです。お葬式のことは、どちらかと言えば考えたくない方もいるかもしれませんね。
私は、僧侶になった同年から10年ほど葬儀社に勤めていました。主に納棺の儀式を担当し、その現場で貴重な体験をしました。
私の経験を1つの題材にして、誰もが避けて通ることのできない死について、考えるきっかけになればと思います。
死者から問われること
私が納棺の儀式の担当に就いたのは、映画『おくりびと』が公開された2008年のことでした。
この映画をご覧になられた方ならお分かりのことかと思いますが、納棺の儀式とは、単に棺桶に故人を納めるだけではなく、身なりを整え、故人が愛用していたものを一緒に納めるなどして、旅立ちの準備を整えるという意味があります。
また、お通夜や葬儀の準備、行政や私生活上の手続きなどが慌ただしくなる前に、家族がゆっくりと故人と向き合うことができる最後の時間でもあります。
納棺の儀式は、かつて自宅で行われることが一般的で、家族や親族、地域で役目を担う人たちによって執り行われていました。近年は、施設や病院などで亡くなった後は自宅に戻らない方も増えました。このような場合は施設やお通夜を行うセレモニーホールで行うことが多いのです。
体を洗い清める湯灌、顔色や表情を整える死化粧、死装束の着付け、故人と副葬品を納棺、という順番で行われます。顔や手足の清拭、化粧や整髪、衣服の着せ替えを、家族が自然な流れで心を込めて施せるように、スタッフは亡くなった方の生前の姿を尋ねながら案内進行して手伝います。
息を引き取ってから距離感のあった家族は、故人に自然に触れることができると、心のシャッターが開くかのように、故人との思い出や感情を話し始め、悲しみの時間の中にも笑いがおきることがあります。「眠っているみたい」「いろいろ作ってくれた働き者の手だ」「この洋服がお気に入りだったよね」。
心を込めて尽くしたひと時が、死別の現実を思い出した時に、生きる勇気を与える重要でかつ貴重な時間となる。
私は、納棺の儀式での故人と家族のやりとりから、光と温かさを感じ、力をもらっていました。
ただ同時に、生ききった死者から問われました、「あなたは生きていますか?」と。
それは職務に集中する一方で、家庭・職場・恋人、様々な人付き合いに疲れ、虚しさを感じながら、それに気づかないふりをしている私へ呼びかける声なき声でした。
「お腹も空くし、あくびも出る。生きてはいるけれど、いま人生の何処にいて、これから何処へいくのか。何処へいったらいいのだろうか?」と、私の心の中の叫びがこだまする日々が続いている頃のことでした。
死者にたずねること
かつて私は「消えてしまいたい。死にたい」とのぞんだことがありました。葬儀社に就職する前の、20代後半。うつ病と診断されました。
思い返すと、小学生の頃には家族の仲や学校での友人関係が悪くならないように、おどけて笑わせて間を取り持っているような子どもでした。祖父のしつけが時に叱責だったり、父の飲酒に息をひそめて過ごしたり、辛いことや傷ついたことがあっても、自分をごまかして生きていました。思春期の頃には、自分の意思に反していたとしても妄信的に「○○するべき」「○○しなければならない」ということを言動の根拠にしていて、よく良い子だと評されてきました。それと同じ分だけ嫌われたくないと緊張していました。「私は嫌だ」と言えないで面倒な事を背負い込んで疲れ、感情や意思を言葉に当てはめることが上手くいかなくなって、いわゆる心の闇を抱え込んでいき、自分に自信がなく周囲を羨み、「こんな生活から逃げ出したい」と現実から目を背けていました。
大学を卒業して最初に就職した頃には、誰がどう見ても私のミスだと分かるようなことでも「私ではありません」と言ってしまい、罪悪感と自己嫌悪に苛まれ、そんな自分の内面をひた隠すように取り繕い、次第に仕事も家事も能率が上がらず、日常生活に様々な支障をきたしていきました。
うつ病治療のために今も精神科へ通院していますが、私が向き合ったのは診察室の主治医とだけではありませんでした。亡くなった父や祖父、そして父や祖父が大切にしてきた御本尊に自ずと向き合うことになりました。
父と祖父との死別は「真正面から向き合う御本尊とは何なのか」「本当に尊いこととはどういうことなのか」という問いをもたらしました。父や祖父の言動が私の言動を抑圧したことや私の心を傷つけたことを、私は今でも許せずにいます。ただ併せて、父や祖父もまた悩み苦しんで「かなしみ」を抱いていたのだと思うようになりました。
すると、お通夜や葬儀、月参りや法話会で、御本尊と真向かいになって勤行し法話を聴聞し、抱えた想いを吐露し座談する隣の人のひとりひとりに通底する「かなしみ」の声を聴いていきたいと思えるようになりました。「かなしみ」の声からもたらされる問いかけが私の歩む道を照らしてくれているからです。
「あなたは生きていますか?」と死者から問われることは、自分の本音を偽る心の動き、思いのままにならない身体、物事に偏った捉え方をしてしまう思考の働き、これらを抱えた自分とその生活を問い直す機会になりました。また、「私はどこで生きているのか?」と死者にたずねることは、変わりゆく環境・社会・価値の中で生じている不平等・分断・貧困に目を向ける機会になりました。この営みは、葬儀社を退社した今でも続いています。