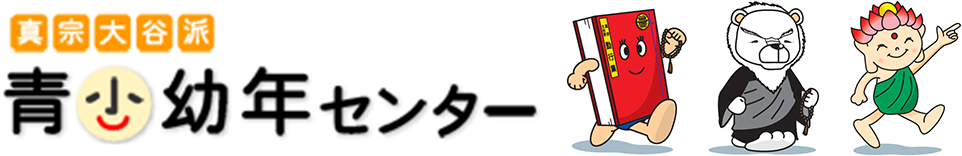43.ウスバキトンボ
赤松 範秀(北海道教区)
秋のお彼岸も過ぎ、日も短くなってきたある日の夕方、一本の電話がかかってきた。
「俺もいよいよ死んでいくみたいだ。話を聞いてくれるか」
電話の主は地元のご門徒。末期のがんを患い、長期にわたり抗がん剤治療を続けてきた70代の男性である。4~5日前、入院先の病院の先生から「外泊許可を出すから、息子さん、娘さんに伝えておきたいことを話してきなさい」と言われ、いよいよなんだなと覚悟をしたこと。久しぶりに自宅に戻り、子どもさん方に自分が死んだ後について、仕事について、家の周りの片付けについて伝えてきたこと。せっかく家に帰ったものの、ちょっとした段差を越えるのにも難儀したので、すぐに病院へ戻ってきたことなどを話された。そして、「今、病院のベッドの上なんだが、あと一人伝えておきたい人がいることを思い出したんだ。俺、辞世の句を作ってみたから、住職聞いてくれるか」と言葉を継がれた。
実は、私はこの男性のことが長らく苦手だった。顔を合わせれば、私が言われて嫌なことをチクッと言ってくる。「アンタは読経の時は声が大きいのに、法話になった途端に声が小さくなる。自信のないのがよく分かる」といった具合だ。なぜ言われて嫌な気分になるのか。指摘通りの自分がここにいるからと頭では分かっていても、他人から言われるのは嫌なものである。その男性を避けるような時期が続いた。
ある年の大晦日の午後、除夜の鐘の準備をしていた。来てくださる方を柔らかな灯りでお迎えしたいと境内にアイスキャンドルを並べていた。下を向いて作業を続けていると、不意に声をかけられた。「アンタは友だちがいないのか。こういうことは一人でやっちゃ駄目だろう」。その男性だった。そして、黙々と準備を手伝ってくださった。勝手なもので、苦手で嫌なことを言う人から、気にかけてくれるからこそ言ってくださる人へと出会い直しが始まった。
「余すなく伝え ウスバキトンボ 身を軽るを」
「余すなく伝え終え ウスバキトンボ 彼の岸へ」
訥々とした口調で辞世の句を詠み上げられた。そして、これまで多くの人を傷つけ、そのことで悩んできたこと。そんな自分は泳げないから三塗の川で溺れてしまうだろうな、とも。最後に、「心残りがあるとすれば、俺の通夜法話でアンタが何を話すのか聞けないことだな」と言って、電話は切れた。
1週間後、その男性は亡くなられた。
息子さんに、娘さんに、そして私を含め有縁の人に伝えたいことは余すことなく話ができたから、肩の荷を下ろせて身が軽くなった。これで仏さまの国へ帰らせてもらえる。辞世の句に触れ、ここまでは理解できた。しかし、「ウスバキトンボ」がどんなトンボなのか知らなかった。電話の後、早速ウスバキトンボについて調べてみて驚いた。この辞世の句はウスバキトンボが分からなければ十全に味わうことができない。
ウスバキトンボとは、もともと熱帯のトンボである。春の終わりに熱帯地域から日本に渡ってきて、お盆の頃に個体数を増やすことから、盆とんぼとも呼ばれる。寒さが苦手なウスバキトンボは、彼岸を過ぎ、肌寒くなる頃には飛ぶ力を失い、枯れゆく草につかまりながら動けなくなっていく。最後は寒さに凍えて命が尽きていく。つまり、寒のある日本では冬を越すことができない。故郷の熱帯地域で一生を終えることもできたであろうに、どういうわけか海を越えて日本を目指してくる。まさに「死への片道切符」であり、悠久の昔からこうした旅路を繰り返してきたという。
この男性はウスバキトンボに自分自身を重ねられたのだ。身体を動かす力を失い、ベッドの上で動けなくなっていく自分。冬を越すことはできない、もう雪を見ることはないのだと。
また、この句は私たちを次のように教えてくれる。ずっと母親のお腹の中に居られれば、他人を傷つけることも、自分が傷つくことも、そのことで思い悩むこともない。つらい出来事に遭うこともなかったかもしれない。しかし、人として生まれてきた、その瞬間から誰もが死への片道切符を握りしめている。老病死しつつある今を生きている。さらには、自他を傷つけ合い、そのことに思い悩むことを通して、他人に、そして自分に出遇っていく旅路がすでに始まっている。それが悠久の昔から繰り返してきた人間の営みであると。
親鸞聖人は善導大師の言葉に依りながら、自他に出遇いたい、自分の身一杯を生きていきたいと願う時、四つの激しい濁流に生きている自身を教えられるという。一つには欲暴流、「怒り、腹立ち、嫉み妬む心多く、暇なき」私。二つには有暴流、「鼻高々に威張ってみたい。他人には馬鹿にされたくない」私。三つには見暴流、「私は正しい、間違っているのはあなただと主張してやまない」私。そして四つには無明暴流、「本当のことが分からないのに、分かった顔をして生きている」私、と。
さらに、親鸞聖人はこれら四つに続いて、「また生・老・病・死なり」(『真宗聖典』244頁)と言われる。私はこの言葉に親鸞聖人その人を、親鸞聖人の声を感じるのである。「生老病死」という始末のつかない身を生きながら、自らの思いに右往左往する私たち。人として生まれたからには、この身の事実を教えられることがなければ、いかに真剣に生きようとも、かけがえのない人生が流転の一生で終わっていく私たちではないか、と。
男性が亡くなられた翌日、お通夜を勤めた。お通夜が終わった後、喪主である息子さんが話しかけてきた。「住職、話が長い。長いだけじゃなく、何が言いたいのかも分からん」。
言われて嫌なことを言う人だ。また遇いましょう。