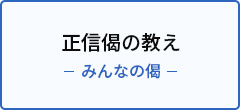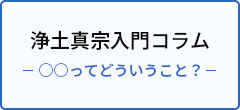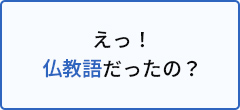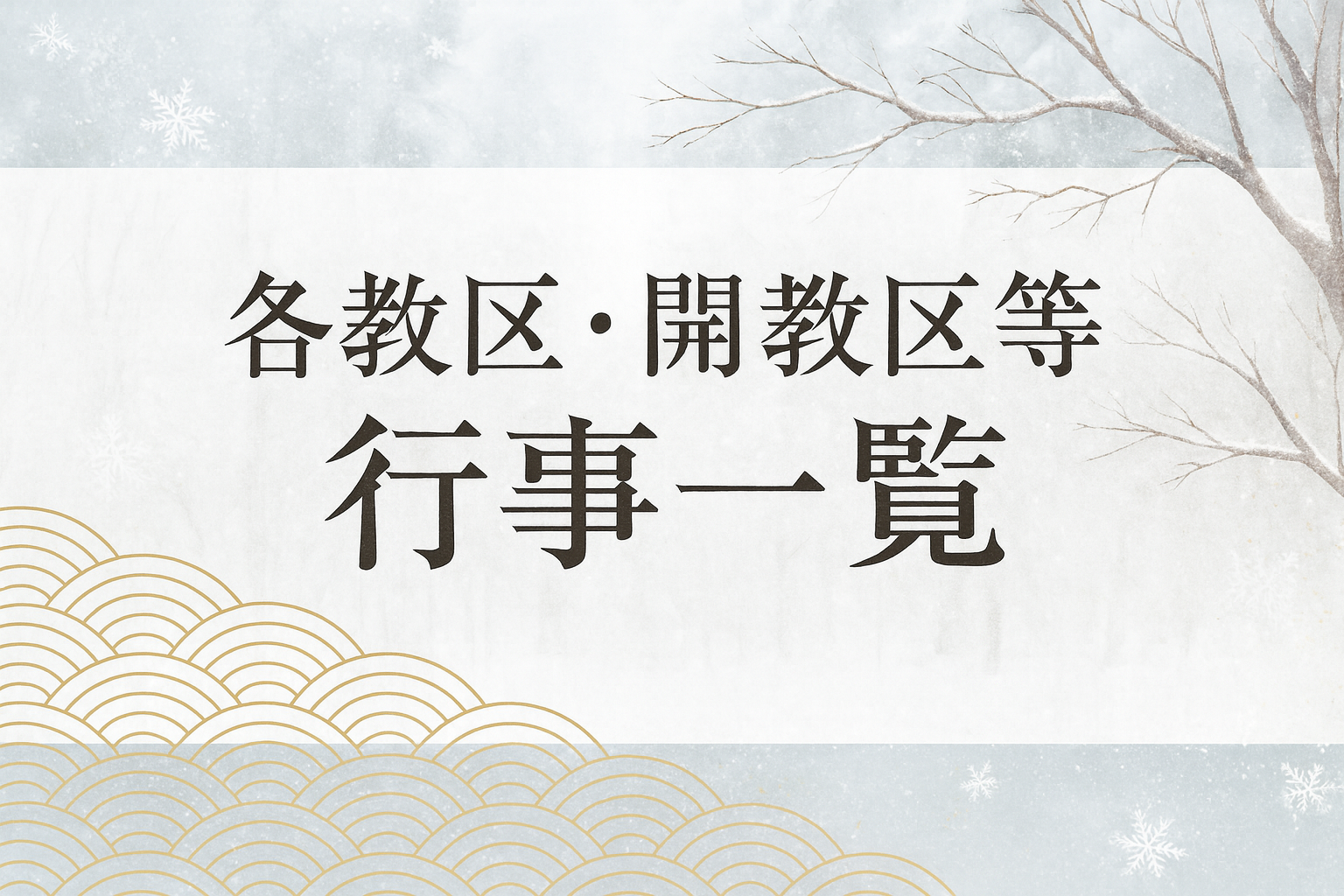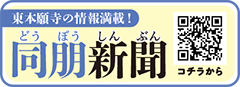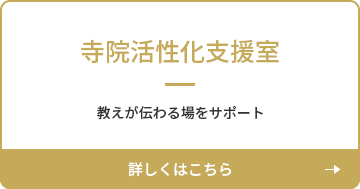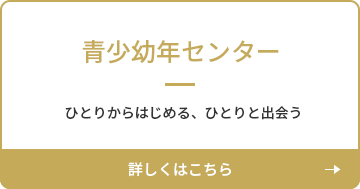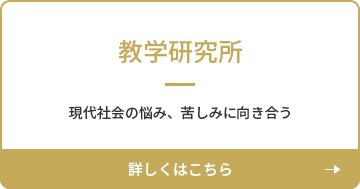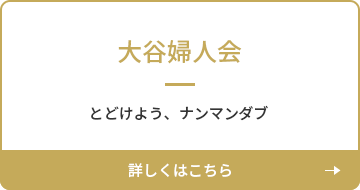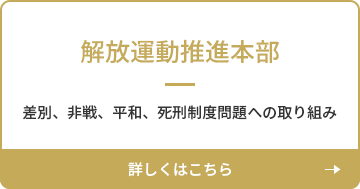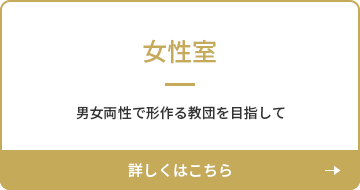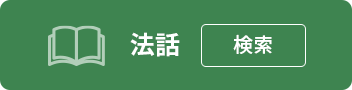2024年4月17日から23日(京都・東本願寺から吉崎別院への御下向)、5月2日から9日(吉崎別院から京都・東本願寺への御上洛)にかけて行われた第351回蓮如上人御影道中。御下向、御上洛、それぞれ全行程に同行した真宗大谷派(東本願寺)職員によるレポートをお届けします。
御影道中では、法話を担当する「随行教導」、責任者の「宰領」をはじめ8人の「供奉人」と呼ばれるお供の方々が、御輿車(リヤカー)のかじ取りや「蓮如上人様のお通り」の先触れの声、交通安全の誘導、浄財のお引き受けなどを担当します。そこに自主参加と呼ばれる一般参加の方が加わります。また、御影道中の運行を円滑かつ安全にすすめるため、蓮如上人御影道中協力会の方々がさまざまな形でサポート。そして、毎年道中一行をお出迎えするお立ち寄り会所宅のご家族やご近所の方々の丁寧な準備によって、蓮如上人の御影はお迎えされます。
★本年の御影道中ではGPS端末を利用したリアルタイム位置情報を共有しました。位置情報の履歴はこちらからご覧いただけます。道中がどのようなルートを通るか、ぜひご覧ください。
※レポートの内容は東本願寺公式Facebookに投稿された記事を再編集したものです。
目次
- 1 御下向(4月17日~23日)
- 1.1 御下向1日目(4月17日)《東本願寺(京都府京都市)~等正寺(滋賀県大津市)》
- 1.2 御下向2日目(4月18日)《等正寺(滋賀県大津市)~最勝寺(滋賀県高島市勝野)》
- 1.3 御下向3日目(4月19日)《最勝寺(滋賀県高島市勝野)~新旭町~今津町~榮敬寺(滋賀県高島市マキノ町)》
- 1.4 御下向4日目(4月20日)《榮敬寺(滋賀県高島市マキノ町)~意力寺(福井県敦賀市)》
- 1.5 御下向5日目(4月21日)《意力寺(福井県敦賀市)~木ノ芽峠~南越前町~今庄~武生~超恩寺(福井県越前市)》
- 1.6 御下向6日目(4月22日)《超恩寺(福井県越前市)~鯖江市~福井別院(福井県福井市)》
- 1.7 御下向7日目(4月23日)《福井別院(福井県福井市)~坂井市~吉崎別院(福井県あわら市)》
- 1.8 《御影道中「御下向」を終えての感想》
- 2 蓮如上人御忌法要(4月23日~5月2日)
- 3 御上洛(5月2日~9日)
- 3.1 御上洛1日目(5月2日)《吉崎別院(福井県あわら市)~坂井市~福井別院(福井県福井市)》
- 3.2 【御上洛2日目(5月3日)】《福井別院(福井県福井市)~鯖江市~武生~圓宮寺(福井県越前市)》
- 3.3 御上洛3日目(5月4日)《圓宮寺(福井県越前市)~南越前町~湯尾峠~今庄~浄念寺(福井県南条郡南越前町)》
- 3.4 御上洛4日目(5月5日)《浄念寺(福井県南条郡南越前町)~余呉~木之本~明樂寺(滋賀県長浜市)》
- 3.5 御上洛5日目(5月6日)《明樂寺(滋賀県長浜市木之本)~高月~湖北~虎姫~びわ~長浜別院(滋賀県長浜市)》
- 3.6 御上洛6日目(5月7日)《長浜別院(滋賀県長浜市)~米原市~彦根市~豊郷町~愛荘町~寶満寺(滋賀県愛知郡)》
- 3.7 御上洛7日目(5月8日)《寶満寺(滋賀県愛知郡)~東近江市~近江八幡市~野洲市~守山市~傳久寺(滋賀県草津市)》
- 3.8 御上洛8日目(5月9日)・御帰山式《傳久寺(滋賀県草津市)~大津市~東本願寺(京都府京都市)》
- 3.9 《御影道中「御上洛」を終えての感想》
御下向(4月17日~23日)
御下向1日目(4月17日)
《東本願寺(京都府京都市)~等正寺(滋賀県大津市)》
真宗本廟(東本願寺)から御影道中が出発する日。
2024年4月17日13時から真宗本廟(東本願寺)阿弥陀堂において、「御下向式」が執り行われました。
「御下向式」では、大谷暢裕門首の挨拶、正信偈のお勤め、木越宗務総長と、随行教導の平等良香氏からの挨拶などがあり、参拝に訪れた約250人が、吉崎別院まで旅をされる蓮如上人の御影と一行の出発をお見送りしました。
14時過ぎに東本願寺を出発した御影道中一行は、烏丸通を北上して御池通から蹴上坂へ。
初日は京都の街中を通ります。
「蓮如上人さまのおとーりー」の大きな触れ声と共に通り過ぎる一行を見て、カメラを向ける観光客や気にせず通り過ぎる人…、と反応はさまざまですが、中には「蓮如上人行ってらっしゃい!」と声をかける人もおられました。
そして、「よいしょ、よいしょ」のかけ声とともに坂道を超え、19時頃、滋賀県大津市にある宿泊会所の等正寺様に到着しました。
御下向2日目(4月18日)
《等正寺(滋賀県大津市)~最勝寺(滋賀県高島市勝野)》
この日は、御影道中の御下向・御上洛の中で1日の移動距離としては最長の約42kmを歩きます。長い道のりではありますが、沿道からの「気をつけて!」「いってらっしゃい!」「ご苦労さま!」などの声に励まされます。
部活帰りの高校生たちからは「何してはるんですか?」と聞かれ、「京都から福井まで蓮如上人の御軸と7日かけて歩いてるんだよ」と答えると「エグいことしてますね!頑張ってください!」というやりとりもあったりしました。
道中では、御輿車(リヤカー)の綱をひきながら、参加者同士でいろいろな話をします。
時には真宗の教えで大切にしていることを話し合うなど、歩きながら座談のようになる場面もあります。
この日の天気は曇り気味で、前日より涼しく歩きやすい天候でしたが、ひたすら長距離を歩いた一行の足は2日目にしてガタガタ…。しかし、安全に気をつけ、皆で蓮如上人のお供を続けます。
御下向3日目(4月19日)
《最勝寺(滋賀県高島市勝野)~新旭町~今津町~榮敬寺(滋賀県高島市マキノ町)》
朝から快晴。終日強い日差しの中、また午前中は突風の吹く中の道中でした。
そのような中、畑仕事の手をとめてひざまずいて手を合わせる人、車をとめて車窓から手を合わせる人、「こんにちは〜!」と手をふる小学生、病院の前では椅子を並べて一行が通るのを待ち受けている人たちの姿もありました。
一行の疲れが既にピークを迎える中、途中参加、部分参加(※御影道中では、1日のみの参加や区間参加も受け付けています)の方の存在は大変力になります。
そして、綱をひきながらの会話も日によって新たなであいがあります。
御影道中は「動く聞法道場」と言われますが、歩く中での会話をはじめ、そこに身を置いて体験する一つ一つが道場になっていることを感じました。
御下向4日目(4月20日)
《榮敬寺(滋賀県高島市マキノ町)~意力寺(福井県敦賀市)》
名残桜と里山の風景の中、長い上り坂と下り坂を歩き、福井県に入りました。本日の歩行距離は約40km。御下向2日目に次ぐ長距離です。この日から最終日まで小学生の息子さんと親子で自主参加する方が合流しました。
会所のお寺の一つでは、ご住職が「御影道中がこんなに長く続けられることの不思議を実感しています。皆さんがここに来てくれるかぎり続けていきたいし、これまで続いているということは、蓮如上人が私たちにお念仏を届けたいと、今も願い続けていてくださる証拠だと思います」と、参拝に来た方に御影道中に対する思いを述べておられました。
長い坂に入る前は御輿車の綱を普段より延長し、供奉人も総出で「よいしょ、よいしょ」のかけ声とともにのぼります。暑い中でしたので、汗がとまりません。
福井県に入ると、今度は長い下り坂。御輿車が暴走しないように、後ろにつけた綱をブレーキとして引っ張りながら進みます。
宿泊会所の意力寺さんの直前は急な上り坂。意力寺さんの門徒さんも加わり、30人以上で坂を登りきりました。
中には小学生の頃以来参加したという高齢の門徒さんの姿もありました。昔は「蓮如上人さま、おとーりー」のふれ声が聞こえてきたら、友だちとみんなで走っていき綱を引っ張っていた、と思い出を語ってくださいました。
御下向5日目(4月21日)
《意力寺(福井県敦賀市)~木ノ芽峠~南越前町~今庄~武生~超恩寺(福井県越前市)》
この日は、御下向の難所・木ノ芽峠を越えて、福井県越前市まで進みました。
雨が心配される中、昨日から今朝にかけて宿泊した意力寺さんで、御輿車から蓮如上人の御影の入った御櫃を降ろして背負子に固定して出発。
峠道は細く、崖すれすれのところもある中、一行は、背負子を代わる代わる背負って進みました。
木ノ芽峠越えでは、御輿車の移動に吉崎別院の職員も加わり、御櫃を降ろした御輿車をトラックに載せ、峠の麓から峠の先の南越前町まで先回り。徒歩で峠を越える一行を迎えます。
そして、雨にあうことなく木ノ芽峠を無事に越えました。しかし、福井県の越前市に入った頃にはこの旅で初めての土砂降りに…。
越前市の武生には、この地域専用の御輿車「武生の御輿」があります。この日の宿泊会所・超恩寺様の手前のご門徒宅にて御影を「武生の御輿」にお移しし、武生の街を歩みます。
終盤は厳しい天候の中でしたが、なんとかこの日の全行程が終了しました。
「蓮如上人御影道中」は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で、2020年以降、一部区間を車両で移動する年が続き、例年通りの徒歩行程ができていませんでした。
ようやく昨年(2023年)は、通常どおりの徒歩移動で執り行うことができました。しかし、2022年の豪雨災害の影響で「木ノ芽峠」の区間は、昨年は車両での迂回となっていました。
今年は、この「木ノ芽峠」も例年どおりの徒歩での移動ができ、御影道中が5年ぶりの完全復活となりました。
御下向6日目(4月22日)
《超恩寺(福井県越前市)~鯖江市~福井別院(福井県福井市)》
朝、宿泊会所の超恩寺様を出発、途中の光澤寺様で昨日から使用した「武生の御輿」から、蓮如上人の御影は再び東本願寺からひいてきた御輿にお移ししました。(「武生の御輿」は御上洛の際には、光澤寺様から樫尾様宅まで使用します。)
この日は福井県の越前市、鯖江市、福井市の主に旧街道を歩き、沿道には蓮如上人がお通りになるのを待つ人たちの姿がありました。
福井市内の浄得寺様から福井別院までは、この春東本願寺に入所した新入職員が参加。疲れた一行にとっては大変心強い助っ人となりました。
浄得寺様での随行教導の法話では、「ここまでいろんな人との出会いを喜びながら歩かせてもらっている。昔はお念仏申しながら歩いていたと聞くが、ふと気づくと自分は暑い、風が強いなど不平を言いながら歩いていることにはっとして恥ずかしくなった。歩くことを通して自分の腹の中にあるどうしようもないものに向き合うことが、御影道中の大事な一面ではないかと感じさせてもらった」と、これまで歩んできた実感が述べられました。
また、供奉人の皆さんからは、道中を歩く上でのさまざまなアドバイスをいただきます。
例えば、綱は先頭から背の高い人の順で並んでひくと、効率よく力が発揮されること。また、お念珠には輪ゴムをつけて腕に通しておくと歩いている最中に落とさないなどなど、これまでの経験から、いろいろなアドバイスをいただいています。
参加者は皆疲労困憊ですが、いい顔をしています。
いよいよ明日は御下向最終日!雨の予報ではありますが、御忌法要が勤まる吉崎別院へ向けて歩みを進めていきます。
御下向7日目(4月23日)
《福井別院(福井県福井市)~坂井市~吉崎別院(福井県あわら市)》
御下向最終日。
小雨が降る中、朝7時30分に福井市の福井別院(東別院)を出発。福井市、坂井市春江町、坂井市坂井町の旧北国街道を通りました。
途中雨は上がり、午後4時30分過ぎにあわら市入り。昨日に引き続き、東本願寺の新入職員も加勢し、細呂木地区の「切り通し」がある吉崎古道を通って、吉崎に向かいます。
吉崎では、ご門徒さんや地元の皆さんが、提灯をもって道中の一行をお出迎えされます。
吉崎の集落に入ったところで、蓮如上人の御影は御輿車から地元の消防団が担ぐ御輿にバトンタッチ。すでに暗くなっている中、提灯の明かりとともに吉崎の町をゆっくりと練り歩きます。
別院前の最後の石段は、地元の消防団員が駆け上がり、蓮如上人の御影は本堂へ入堂。午後7時30分、吉崎別院に無事到着しました。
本堂では、御影の入った御櫃の鍵を開け、御影を広げる「お腰延ばしの儀」が執り行われ、多くの参拝者と共に法要が勤まります。輪番挨拶、随行教導による法話の後、7日間歩き通した方に「完歩賞」が贈られました。
長い7日間の御下向、「ねてもさめても、いのちのあらんかぎりは、称名念仏すべきものなり」と御文で私たちに伝える蓮如上人と共に歩んだ道。
みんな身体はボロボロですが、それぞれに感じたこと、各会所の皆さんや道中の会話で得たものはなにものにも変えられません。
《御影道中「御下向」を終えての感想》

御下向の全行程の自主参加として初めて参加させていただきました。参加にあたって、東本願寺から大津までを何度か歩いて、万全の準備で臨んだつもりでした。ところが始まってみると三日目から両膝の痛みが発生。この頃から他の自主参加の方も各々足の痛みとの闘いが始まりました。供奉人さんから「そうなったら歩いて治す(笑)」と助言をいただき、最後まで痛みに耐えながらの道中となりました。それぞれ痛みを抱えながら、それでも皆で励ましあいながらお供を続けていくことに何か温かいものを感じたことは強く印象に残っています。
綱を引きながらの参加者同士の会話では、これまで出あった人や教えの話になることもあり、この歩く寄合談合の場も道中の醍醐味であることを実感しました。また、難所の木ノ芽峠では、「蓮如さん、きっと笑ってるよ」と自然と会話に出てくることもあり、蓮如上人を身近に感じたことも印象的です。
江戸時代から続くこの唯一無二の仏事がこれからも継承され、出あいの場が生まれ続けることを願わずにおれません。
(企画調整局主事・真宗教化センター寺院活性化支援室寺院活性化支援員 牧野尚史)
蓮如上人御忌法要(4月23日~5月2日)
「蓮如上人御影道中」、京都・東本願寺から約240㎞の道のりをお供の方々と共に旅をされた蓮如上人の御影をお迎えした吉崎別院。
道中の到着から一夜明けた24日の晨朝には、道中のお供をされた供奉人さんたちも参詣。
蓮如上人がお勧めになった「正信偈」「和讃」のお勤めに続き、蓮如上人が吉崎の地で記された『御文』1帖目第1通「或人いわく」が拝読され、晨朝・日中・逮夜・初夜と勤まる「蓮如上人御忌法要」が本格的にはじまりました。
御忌法要期間中、境内では能登半島地震を支援する「災害支援バザー」(4月25日・27日~29日)が行われたほか、この期間限定の酒まんじゅうも販売されました。また、ゴールデンウィーク前半に重なった4月27日から29日までの間は、吉崎別院門前でGobou市が開催され、吉崎別院門前には出店が並び、参拝者を出迎えました。
《御忌法要中の法話講師》
・4月23日 平等良香氏(御下向随行教導)
・4月24日 林拡氏(小松大聖寺教区)
・4月25日 熊谷二郎氏(福井教区)
・4月26日 伊藤俊作氏(小松大聖寺教区)
・4月27日 佐々本尚氏(福井教区)
・4月28日 一楽真氏(小松大聖寺教区)
・4月29日 加藤雅輝氏(小松大聖寺教区)
・4月30日 佐々木正博氏(福井教区)
・5月1日 芳原里詩氏(小松大聖寺教区)
・5月2日 東金慈氏(御上洛随行教導)※晨朝のみ
御上洛(5月2日~9日)
御上洛1日目(5月2日)
《吉崎別院(福井県あわら市)~坂井市~福井別院(福井県福井市)》
蓮如上人ゆかりの吉崎東別院(真宗大谷派吉崎別院)における10日間に渡る「蓮如上人御忌法要」を終え、5月2日、蓮如上人御影道中(御上洛)が、京都・真宗本廟(東本願寺)に向けて出発します。
蓮如上人御忌法要の最後の晨朝(じんじょう)のあと、御上洛の随行教導・東金慈氏よりご法話があり、御忌法要中内陣に奉掛された蓮如上人の御影の「お巻き納めの儀」、そして、地元消防団の方々によって担がれた御輿で、蓮如上人の御影が吉崎別院を出発されました。
出発にあたって、責任者である宰領をつとめる堀出幸子さんから「御影道中にお供をすることを通して、自己を明らかにする歩みにしたい」との挨拶があり、いよいよ吉崎の地を出立します。
吉崎の町をぐるりと周ったあとは、昔ながらの切り通しを進みます。
道に咲く花々も美しく、緑深い山々を望みながら一行は福井に向けて歩みを進めました。
吉崎から芦原温泉、坂井市、福井市と、この春開業した北陸新幹線の横を御輿車と徒歩で歩く道中。
どんなに時代が変わっても、人間の営みの限界を知らされながら、蓮如上人の御教化に運ばれる世界がある、そんなことを感じさせていただきました。
吉崎別院御出立から12時間半後の午後8時過ぎ、福井別院に無事にお着きになられました。
【御上洛2日目(5月3日)】
《福井別院(福井県福井市)~鯖江市~武生~圓宮寺(福井県越前市)》
福井別院を出発後、福井市内を流れる足羽川を渡ります。九十九橋のたもとには、江戸時代の道中の際、川の洪水で濡れた御影を乾かしたと伝えられる会所(※諸説あります)があります。その会所では、御下向・御上洛ともに、蓮如上人の御影を納めた御櫃に掛けられた朱色の毛氈が外され、乾かすような作法が伝わっています。
そして、一行は福井市内を周りながら進みます。この日は、お寺の子ども会の子どもたちが、一つ前の会所のお寺に蓮如上人をお迎えに来られ、次のお寺まで、蓮如上人につながる綱をひく場面もありました。
また、大型連休後半の初日である今日は、親子でお参りされる姿にも多く出あいました。
「今年はもうお参りできんかと思ったけど、こうしてお参りできた。ナンマンダブツ」と、念仏をとなえるおばあちゃんの横では、御影道中に初めてあう2歳のお子さんが「レンニョちゃん?レンニョしゃん」と手を合わせる姿もあり、この蓮如上人御影道中が次の世代につながる世界がありました。
随行教導の東金慈氏からは、「練習をして道中にのぞんだが、間に合わん。道中で足は疲れるが、自分の都合ではなく、道中では蓮如さんの都合に合わせければならない。蓮如上人に連れて行っていただいて、なんとか京都にたどり着きたい」との法話があり、自分の都合で生きる私たちの姿を確かめられました。
御上洛3日目(5月4日)
《圓宮寺(福井県越前市)~南越前町~湯尾峠~今庄~浄念寺(福井県南条郡南越前町)》
御上洛3日目は、越前市から南越前町に入り、北陸道の古くからの要所・湯尾峠を越え、北陸道と北国街道が交わる宿場町・今庄まで進みます。
まずは、武生のご門徒さん宅で大切に保管されている「武生の御輿」で圓宮寺さんを出発(前日の夕方の会所・光澤寺様から蓮如上人の御影は「武生の御輿」にお移しして、圓宮寺様まで地元の方々と歩んできました)。武生の朝の市街地を「蓮如上人さまのお通り〜」の触れ声を先頭にゆっくり進みます。
大型連休にも重なり、この日も沿道では帰省された子どもたちの姿が多く見られました。子どもの頃に御影道中に出あったことがきっかけで、今では親子で参加するようになられたご門徒さん(息子さんが中学生の頃作られた『蓮如新聞』は当ホームページでも紹介しています)や、子どもの頃に御影道中に参加、今では成人した方が、会所でスーツを着て蓮如上人をお迎えする姿にも出あわせていただきました。
御下向では木ノ目峠を通りましたが、御上洛では、北陸道の要所・湯尾峠を進みます。
湯尾峠では、背負子で蓮如上人の御影の入った御櫃を背中に背負い、自主参加の方々も交え、道中にお供をする方全員で交代しながら「ナンマンダブツ ナンマンダブツ」と一歩一歩進みます。背中には、蓮如上人によって伝えられた教えの重さのようなものを感じながら、土の道を歩んでいきます。
そして、湯尾峠の先には、古くからの宿場町・今庄宿の街並みが見えてきます。
御下向(京都→吉崎)では、西近江路を通った一行は、御上洛では今庄宿から先は北国街道(東近江路)に入り京都まで歩みを進めます。
御上洛4日目(5月5日)
《浄念寺(福井県南条郡南越前町)~余呉~木之本~明樂寺(滋賀県長浜市)》
この日は御上洛における1日に歩く距離が一番長い日です。今庄宿から北国街道の難所・栃ノ木峠を越えて滋賀県長浜市余呉に入り、宿場町・木之本まで歩みを進めます。
今庄を6時に出発した一行は、「蓮如の道 北陸道/北国街道」の石碑も建つ宿場町・今庄の町を進みます。
御下向では、湖西ルートを通りましたが、御上洛では旧北国街道を通り、今日は御上洛最大の難所ともいうべき、栃ノ木峠を越えます。栃ノ木峠は標高538メートル、頂上までは急な坂道が続きます。
3日間歩き通した供奉人をはじめとした参加者の足の疲労もある中、難所越えのこの日を目掛けて駆け付けた途中参加の方々も加わってくださり、みんなで「ヨイショ ヨイショ」と声を合わせながら急な坂道を登って行きます。
中には供奉人さんの息子さんや、御下向の供奉人をつとめたベテランの供奉人さんが娘さんとお孫さんを誘って参加したりと、今日もまたこの御影道中が世代をつないでゆく姿にあわせていただきました。
若い力も加わって坂道を登ると福井県と滋賀県の県境です。
御影道中恒例の記念写真撮影をして、次なる宿泊の地、宿場町・木之本に向かって進みます。
山間の余呉の街並みをすすみ、いよいよ宿場町・木之本が見えてきます。夕暮れに映る木之本の街並みはとてもきれいです。
この御影道中は「蓮如上人さまのお通り〜」の触れ声が印象的ですが、朝には朝の触れ声の響き、夕方には夕方の触れ声の響きがあるように感じます。明日は雨の予報も出ていますが、雨の中の触れ声はどんな響きがするでしょうか…。
御上洛5日目(5月6日)
《明樂寺(滋賀県長浜市木之本)~高月~湖北~虎姫~びわ~長浜別院(滋賀県長浜市)》
滋賀県に入って2日目、「蓮如上人さまのお通り〜」の触れ声と、町の方が蓮如上人の出発を町に知らせるベルの音の中、朝の宿場町・木之本の街並みを道中はゆっくり進みます。木之本は7時半の出発ですが、家々からはお賽銭の包みを手に、ご門徒さんが蓮如上人をお見送りされます。
今は長浜市として合併していますが、今日は木之本から高月、湖北、虎姫、びわのご門徒宅やお立ち寄りの寺院に立ち寄り、一つ一つの会所で、勤行と法話が行われます。
お寺での子ども会も盛んなこの地域の会所では、お寺の子ども会の子ども達が、この蓮如上人御影道中を思い思いに描いた絵をのぼり旗にプリントした旗でのお出迎えもありました。
そして、お立ち寄り会所には、蓮如上人直筆の「南無阿弥陀仏」の名号が掛けられていたり、蓮如上人にまつわるエピソードのあるお宅やお寺もあります。
この日は御上洛はじめての雨。一行は強風の中、カッパを着て、さらに歩みを進めます。
晴れの日は晴れがよかろう、雨の日は雨がよかろうの世界です。
本日のお宿、長浜別院に着く頃には雨も上がり、別院に集まったご門徒さんに迎えられ、長浜別院大通寺の門を蓮如上人をお乗せした御輿車がくぐられました。
御上洛6日目(5月7日)
《長浜別院(滋賀県長浜市)~米原市~彦根市~豊郷町~愛荘町~寶満寺(滋賀県愛知郡)》
昨夜からのお宿・長浜別院大通寺さんのお朝事では、宮戸弘輪番より「御影道中という仏事を通して、蓮如さんのなされた真宗再興がこの私の身に起こっているのだと受けとめさせていただいています。この道中は、感動の追体験の仏事であり、念仏せよとの声を受けとめた方々が351年続けられた仏事です」との挨拶があり、6日目の道中が始まりました。
この日も朝から雨は降ったり止んだり…。長浜別院大通寺を出発した一行は、長浜市から米原市へ。北国街道に別れを告げ、中山道に入りました。そして中山道を米原から彦根へ。
左手に北陸自動車道、右手に東海道新幹線、その間を人の力によって蓮如上人をお乗せした御輿車が時速5キロ前後で進みます。
中山道では、前輪のタイヤが故障。
供奉人さん達が協力し合って補助タイヤに交換していると、通りがかりのバイクに乗った若い方が止まってくださり、修理を手伝ってくださる一コマも。たまたま通りかかったその方はお立ち寄り会所のある町に住んでおられ、いつか御影道中に遇いたいと思っていたとのことで、不思議なご縁を感じました。修理が終わって再び出発する蓮如上人に手を合わせるその方の姿に、山あり谷ありの人生を歩む中で、念仏が確かに伝わった瞬間を感じさせていただきました。
午後には雨も上がり、日が暮れ掛けた頃、愛知川宿に続く橋のたもとまで提灯でお迎えくださったご門徒の方々の先導で、蓮如上人は今夜のお宿・寳滿寺様に無事到着されました。
御上洛7日目(5月8日)
《寶満寺(滋賀県愛知郡)~東近江市~近江八幡市~野洲市~守山市~傳久寺(滋賀県草津市)》
昨夜一行を宿場町の入口までお出迎えしてくださったご門徒さんにより、今朝は宿場町の外れまで旗の先導によるお見送りをいただき、愛知川宿を出発しました。
御上洛7日目は、愛知川宿から東近江市、近江八幡市、野洲市、守山市を通り、草津宿まで進みます。
お立ち寄り会所の寺院やご門徒宅では、心尽くしのおもてなしをしてくださいます。
これも蓮如上人をお迎えするお気持ちで、長い年月をかけて、お供の方々をお迎えされてきた歴史の表れのように思います。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、ここ数年御斎が出せず、今年は久しぶりに御斎ができたと喜んでくださる会所の方々の声も聞かせていただきました。食事をいただきながら語り合う、これも、生活の中で教えを語り合う「寄合談合」を大切にされた蓮如上人の道中の一つのご教化のような気がします。
御影道中のお供で歩く方、おもてなししてくださる方、沿道でお待ち受けされる方、道中の先になり後になりサポートしてくださる方々のおかげでこの御影道中は続いています。皆さんの蓮如上人を思う心に導かれながら、真宗本廟(東本願寺)に向けて、いよいよ明日は御上洛最終日です。
御上洛8日目(5月9日)・御帰山式
《傳久寺(滋賀県草津市)~大津市~東本願寺(京都府京都市)》
いよいよ真宗本廟(東本願寺)御帰山の日。
ご門徒さんの心のこもった朝食に、住職さん手作りのお漬物も振る舞っていただき、皆さんに見送られて草津を出発。
琵琶湖の姿を少し目にしながら一行は歩みを進めます。草津市から大津市に入り大津別院に立ち寄ります。
大津別院では、仏教讃歌のコーラスに迎えられながら到着しました。このように各会所それぞれが、心を尽くして蓮如上人の一行をお迎えします。
逢坂の関を越え、山科別院へ向かう道中はいよいよ京都市に入ります。そして、蓮如上人の御廟にお参りした後、山科別院に入ります。山科別院では多くの方が待ち受けておられました。
山科別院からは真宗大谷派の新入職員も加わり、供奉人さんからは「若い人も加わって、真宗再興の始まりや」との声も聞かれました。
東山を越えるといよいよ真宗本廟・東本願寺に近づいてきます。
烏丸通には多くの方が蓮如上人一行のお着きをお出迎えされました。「蓮如上人さま真宗本廟・東本願寺にお着き」の声でお念仏が響きます。
一行は阿弥陀堂門から御影堂前に移動して拝礼、その後、堀出幸子宰領から挨拶がありました。堀出宰領は、「ここに来るまでいろんな道のりがあり、人間が共に生きることがこんなにも難しいことかと思った。歩みが揃わず、お声明も揃わず、意見が合わないこともあったが、たった一つのことが重なり合って本日真宗本廟に到着できたと思っている」と述べられました。
引き続き阿弥陀堂にて御帰山式が執り行われ、「お腰延ばしの儀」にて蓮如上人の御影が掲げられる中、門首挨拶、正信偈のお勤めの後、木越渉宗務総長及び東金慈随行教導からの挨拶がありました。
最後に「御影お巻き納めの儀」にて御影がお納めされ、御帰山式は閉会。
351回目の「蓮如上人御影道中」の全日程を無事に終了しました。
《御影道中「御上洛」を終えての感想》

この春敦賀まで延伸したばかりの北陸新幹線と北陸自動車道の間を時速5kmで歩む御影道中…。
現代に生きる私たちは、旅といえば時速260kmの新幹線に乗り、時速100kmの車に乗り、あの町からこの町へと運ばれます。しかし、そんな今日でも、人間の歩く速度を限界値として、蓮如上人の御影道中は進みます。
アスファルトの上を、江戸時代とほぼ同じ行程で歩く現代人の足は痛み、時に泣きそうになりながらも沸き起こる「こんなに辛い思いをしても、乗り物ではなく自分の足で歩いているぞ!」という自負心は、愚かな私の束の間の思い上がりでした。ズキンと痛む足の痛みから「自分の力で歩いているようでいて、歩かされている…。新幹線であっても、車であっても、徒歩であっても、どう頑張っても人間は運ばれるしかない存在である」ということに最終的には気づかされました。
蓮如さんの御輿につながる綱につかまり、道中の皆さんに励まされ、痛いとはいっても歩を進められるだけの身体の状態もすべて頂き物でした。
晴れの日は晴れの中、雨の日は雨の中、自分の力で歩いているというのは錯覚で、お供をしている私の方がむしろ蓮如さんの御影によって運ばれる旅路です。
こうして蓮如上人御影道中は、「自力無功」、すなわち握りしめた自分の力の間に合わなさを知らされる「他力の道中」でありました。
(企画調整局参事・真宗教化センター寺院活性化支援室寺院活性化支援員 松田亜世)