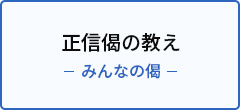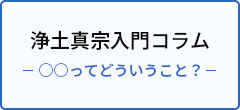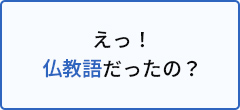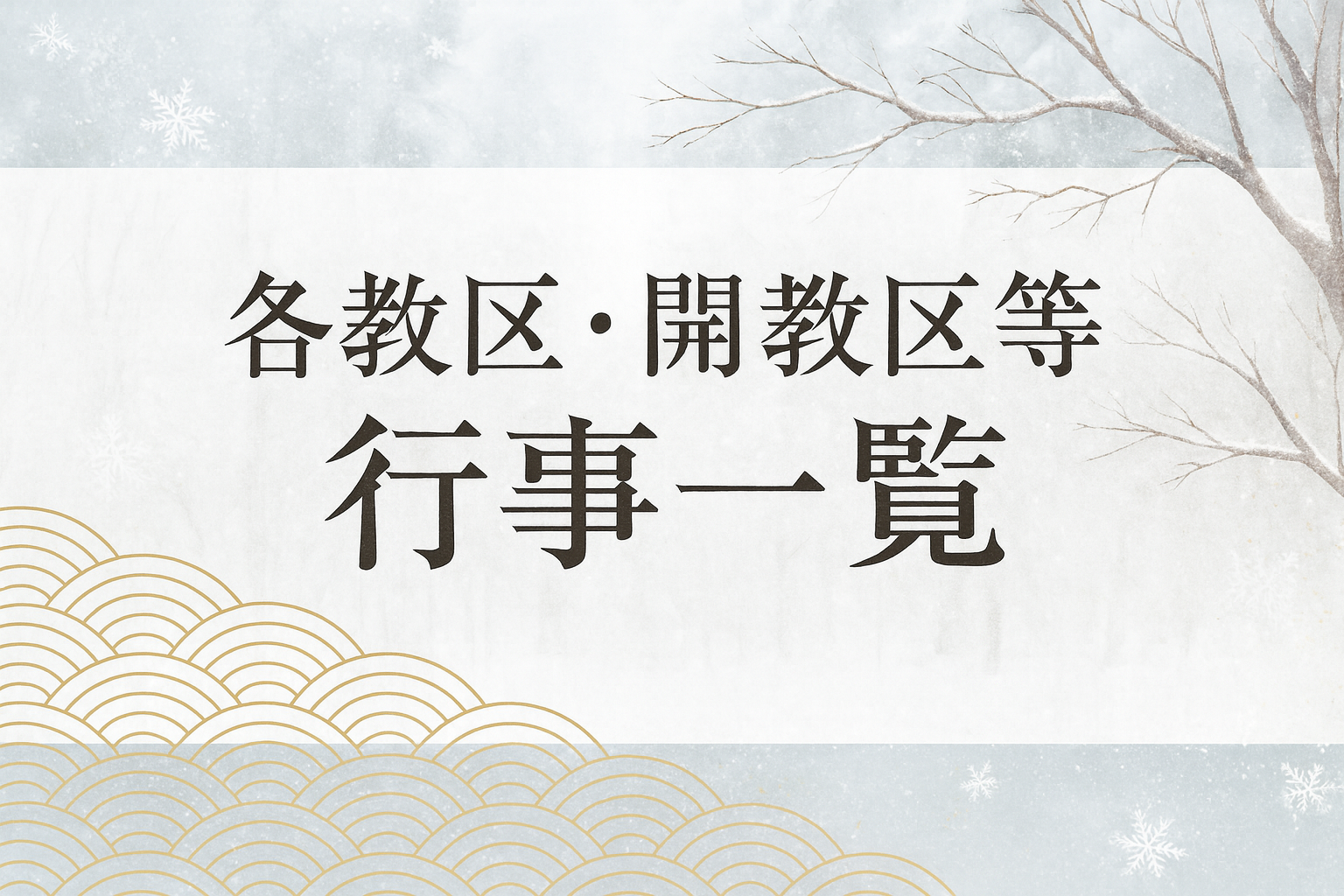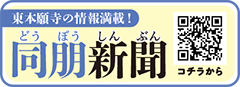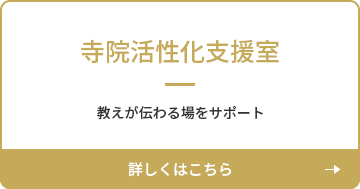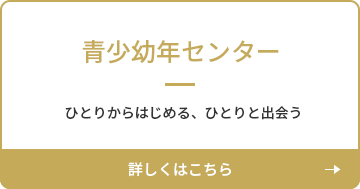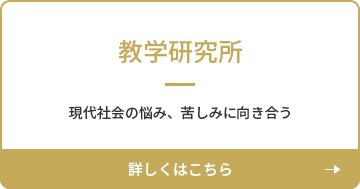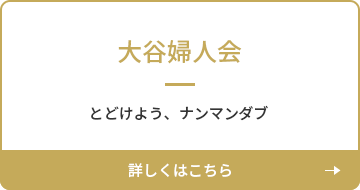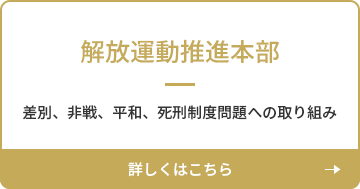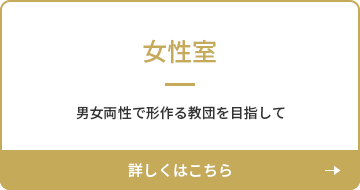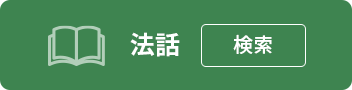四国教区慶讃テーマ:宗祖親鸞聖人のまなざしに学ぼう〜私の心の距離を問う〜
桜の花が満開の青空のもと、3月28日に「四国教区第39回同朋大会」が高知市文化プラザかるぽーと四国銀行ホールで開催されました。
今大会は、慶讃テーマ「南無阿弥陀仏〜人と生まれたことの意味をたずねていこう〜」のもと開催され、宮武真人氏(慶讃事業推進委員会委員長)による開会挨拶の後、正信偈草四句目下同朋奉讃が勤まり、会場内にお念仏の声が広がりました。
その後、趣旨説明に続き講演が行われました。久保博巳氏(東讃第1組深妙寺)司会のもと、講師の武田鉄矢氏(歌手、俳優)と真城義麿氏(東予組善照寺)には「南無阿弥陀仏〜人と生まれたことの意味をたずねていこう〜」をテーマに対談いただきました。
武田氏は、坂本龍馬や西田敏行氏との出会い、また自身の母親について語られました。特に母親との思い出には真宗の生活を感じられるものがあり、その名言の数々に会場では笑いが起き、終始和やかな雰囲気で進行しました。
真城氏は、人が老いることについて、人には付加価値と本体価値が存在し、「できる」とは付加価値であり、老いによってその付加価値が無くなり本体価値が露わになる。そんな自分の本当の尊さとは何かを考えていく必要があると述べられました。
また、武田氏の「私たちはどうしても自分の物差しで物事を判断してしまう」との発言に対し、真城氏は、「私たちは“生まれた”という受け身で生を授かる。“私”を考える時、つい“私は”で考えてしまうが、“私の”という所有の意味で人生を振り返ることが大切。“私は”とは本人が物心ついてからであり、“私の”は母親のお腹の中でさまざまな縁をいただいた頃からの見方だから」と掘りさげました。
代々伝わってきたお経のように、私たちにとっての本当の依りどころとは何かを考えていくことが人と生まれたことの意味をたずねていくことに繋がると対談を締められました。
対談の後、土佐組長宮﨑善之氏より閉会の挨拶があり、恩徳讃を唱和し閉会となりました。
翌日29日には土佐別院にて「宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要並びに土佐別院設立100周年記念法要」が勤まりました。始めに浜口和也氏(土佐組誓願寺)より法話をいただき、その後、法要が勤まりました。
法要は庭儀に始まり、山陽教区鸞聲会の雅楽演奏に続き、多くのお稚児さんや僧侶が土佐別院に隣接する幼稚園から堂内に向けて出発しました。庭儀が終わると再び僧侶が入堂し、楽が奏でられる中、門徒で満堂の土佐別院に大きなお念仏の声が響きました。
勤行の後、髙山崇土佐別院輪番は、「四国教区として最後の法要が、四国唯一の別院であり地域にとって大切な場の一つでもあるこの土佐別院で勤まったことは、これまで100年にわたって継承されてきた本願念仏の教えを後世に手渡していく節目になることだろう」と挨拶し、法要を締められました。
2日間にわたる今回の法要日程を終え、昨今の不安定な世界情勢や不満が募る時代を生きる身として、自分自身にとって親鸞聖人をとおし「人と生まれたことの意味をたずねる」とは何か考えさせられました。また、高知市文化プラザに団体参拝等で集まった多くの方々や土佐別院を満堂にした門徒の方々、そうした法要の場をととのえるために協賛いただいた企業の方々や四国各地から集まったスタッフの方々の熱量がとても印象的でした。
最後に、今回の法要パンフレットの末には『安楽集』を記した『教行信証』のお言葉が引用されています。先人たちによってこの地に根付き、継承されてきた本願念仏の教えを自分自身が訪ね直すと共に、次の世代へ手渡ししていく大切な役目をいただいていることが感じられる法要となりました。
(四国教区通信員 河野有信)