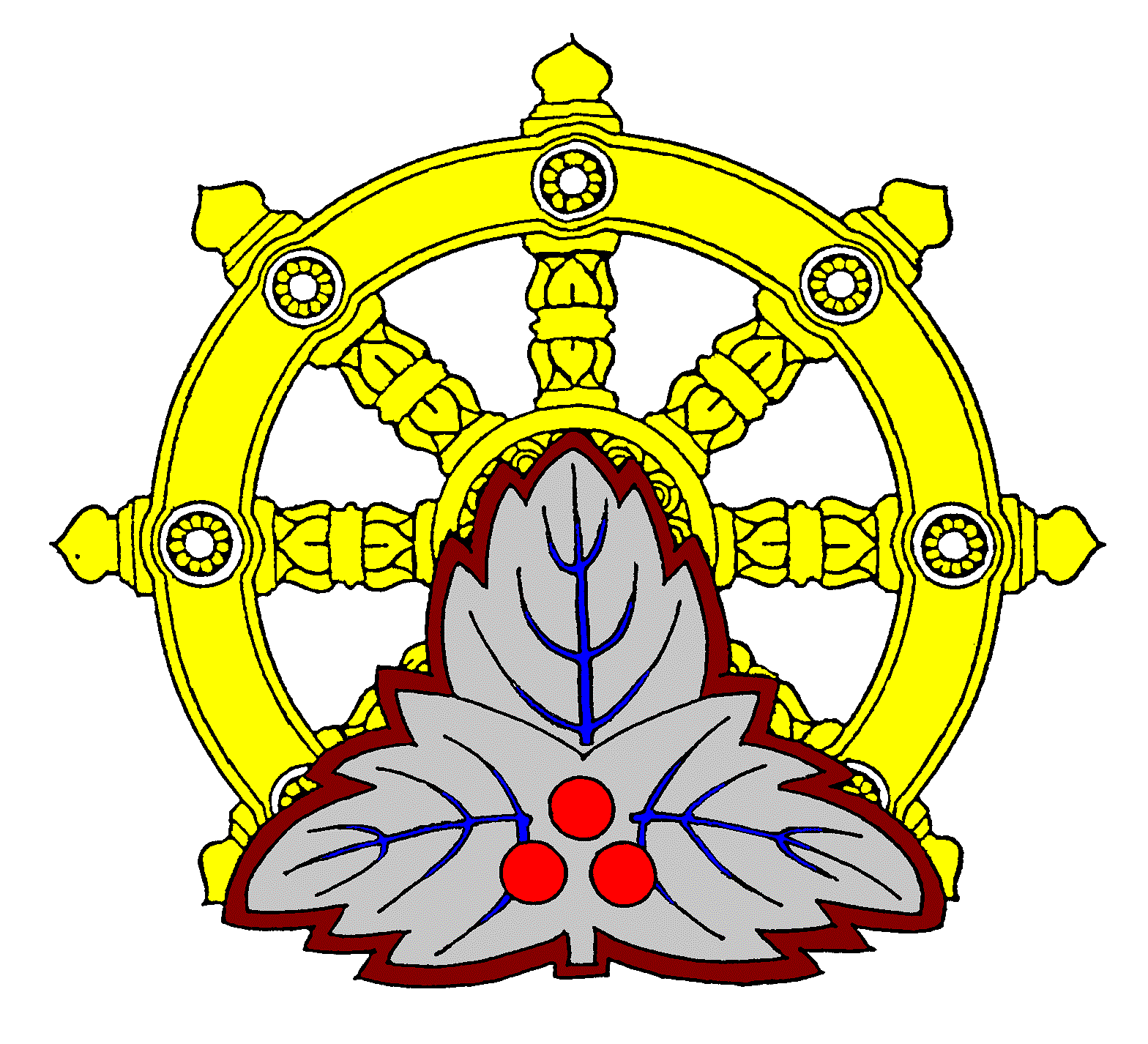良(まこと)に傷嗟(しょうさ)すべし、深く悲嘆(ひたん)すべし。
(『教行信証』「化身土巻」・『真宗聖典』三五六頁)
親鸞聖人は、本願に帰依してもなお、そこに自力の心が雑じる在り方を明らかにされ、自力で念仏を捉えることを課題とされた。聖人はその在り方について、「自ら、ずっと昔から流転してきた輪回をはかれば、どれだけ長い時間を尽くしても、仏の願力に帰依することは不可能であり、信心の大海に入ることも出来ない」と言われた。
これは、結局凡夫は本願に帰依できないことを表す文であろうか。いやそうではなく、むしろ本願力に帰依し、信心を獲得する機縁となることを表す文と言えないか。というのも、この文は、いわゆる「三願転入」の文の前に述べられた言葉で、これに続いて聖人は自力のあり方をでて、如来の本願に入ると言われるのである。では、なぜここでこのようなことを言われるのであろうか。
ここで「流転輪回」と表現されていることに注目したい。輪回とは「六道輪回」とも言われるように、ずっと生と死を繰りかえし、迷いの生をへめぐることである。このことは様々な角度から考えることができるが、ここではどうして自力の迷いが「輪回するもの」として表現されたのか、その意味を考えたい。
それは、自己には思いも及ばない広大な過去の背景があることを知らせるものである。これによって、今の自分の善悪だけで物事を判断することは出来ないこと、それでも自力の根性はいかに根深いかを示されたのである。つまり、私はこのような自己の背景を見ないで、自分の領域でものをはかり、自分の都合であらゆるものを判断している。それで本願念仏をも捉えようとしているのである。
だから聖人は、輪回する自分を傷み嗟(なげ)き、悲歎すべしと言うのであろう。自分は自分で決めた善悪の判断で見ているだけであり、しかもその分別でものを見ている習性はどれだけ根深いか、その自分の習性を傷み、悲しむことが聖人から勧められるのである。
しかし、この「悲歎」はただ自分を悲しむということではない。そこには如来のあわれみ、大悲がある。曽我量深は、如来の大悲は「かなしむ」という意味があり、「法蔵菩薩が一切衆生の罪を自分の雙肩(そうけん)に荷うて立って行かれる心持といふものは、もう永遠に浮ぶ瀬がないところの深き悲しみであります」(『曽我量深選集五巻』三二一頁)と言う。実は自分に、広大な背景としての流転の過去があるとの悲しみは、同時に、そこに如来の共に悲しみ、救おうとするはたらきがあるのである。この輪回する自己は、如来の智慧に照らされて明らかになる自分のすがたであった。
輪回は一見、本願力に帰依できない理由のように思われるが、実はそこにこそ本願との出遇いの機縁がある。自分の現実とは別に、その背景となるような広大な時間がある。このことを知らされることが大切なのであろう。なぜなら、知らされることが自分のはからいを超えた姿であるからである。自力とはどこまでも自分で為した過去の行為にとらわれ、そこから未来の結果を求める現在の問題である。このような時間範囲によって、自分や他者を価値づけようとする。しかし、人間の価値とはそのような思いやはからいで捉えられるものではない。自分では思いも及ばない不可思議な過去と未来との時間によって、現在の自分が位置付けられるのである。それが本願との出遇い、本願に帰依することではないだろうか。ここで言う「流転輪回」とは、本願によって、自分の存在の深さに「うなずく」ことを表しているのである。
(教学研究所所員・武田未来雄)
[教研だより(161)]『真宗2019年12月号』より
※役職等は発行時のまま掲載しています。