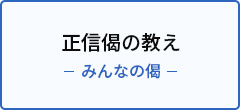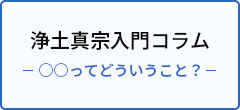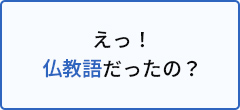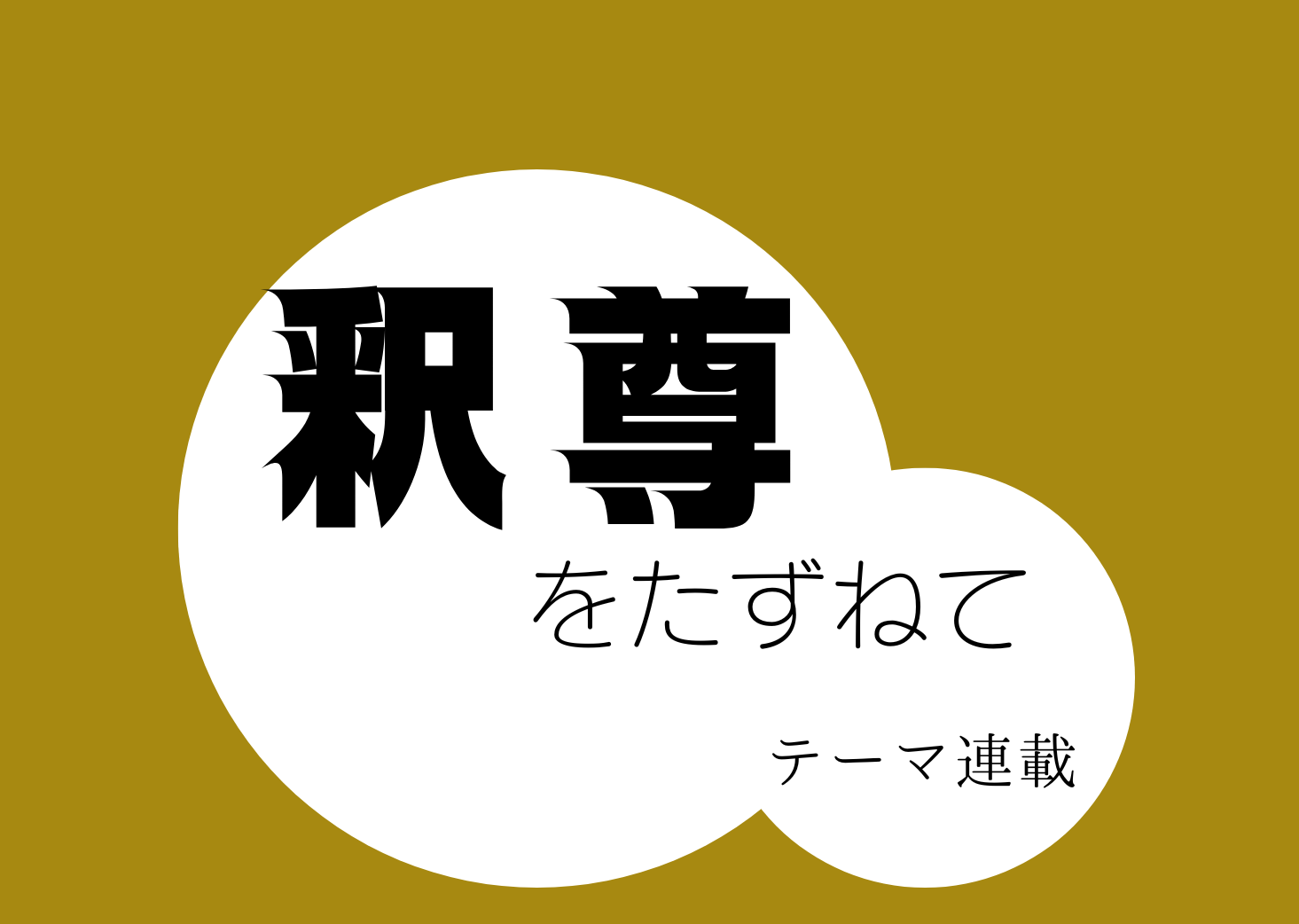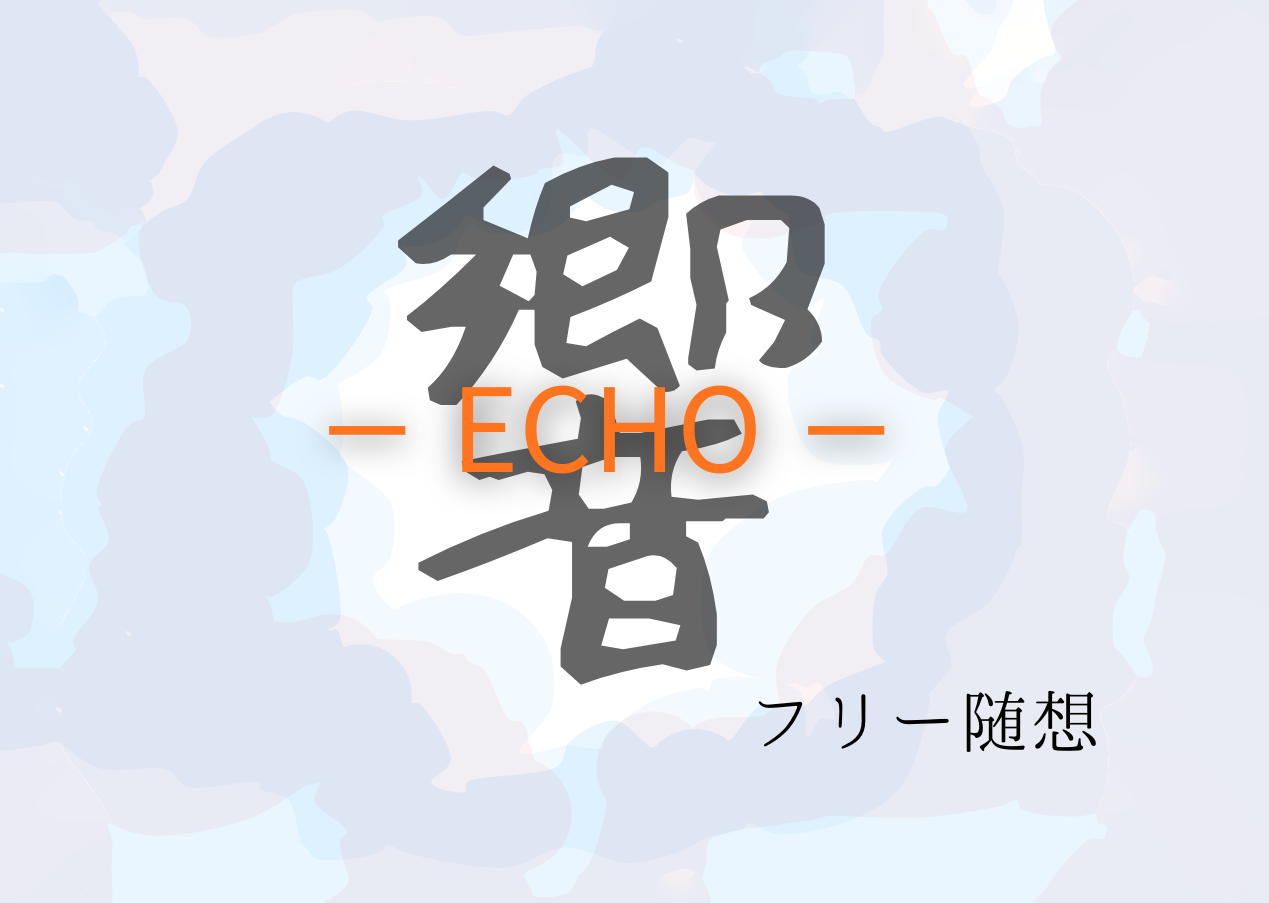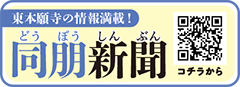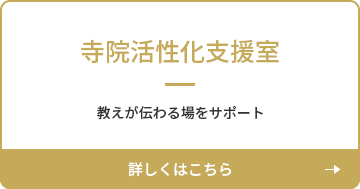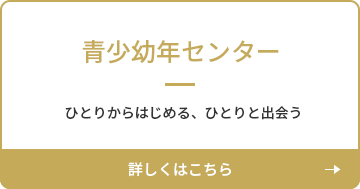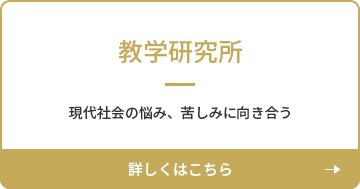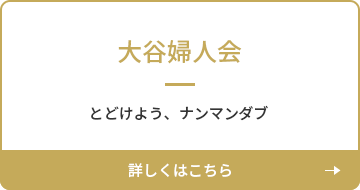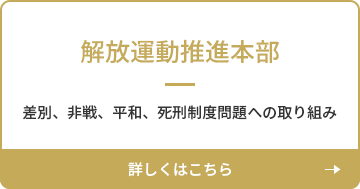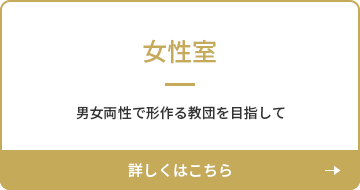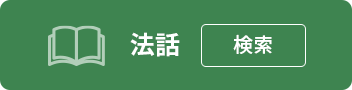そんなにうまくいくはずがない
(藤井 祐介 教学研究所嘱託研究員)
一 同「……」
三十郎「早い話がよ……大目付の菊井が黒幕かも知れねえぜ」
(『全集黒澤明』第五巻、岩波書店、一九八八年、一二〇頁)
黒澤明監督の映画『椿三十郎』の一場面である。『椿三十郎』は江戸時代を舞台に、ある藩のお家騒動(城代家老派と大目付派の対立)を描いている。右の場面では、主人公の三十郎が城代家老派の若侍たちを前にして、大目付派の陰謀を看破する。その後、よそ者の三十郎もお家騒動に巻き込まれて、陰謀を阻止するために奔走することになる。最終的に、三十郎の機転によって陰謀は阻止される。
今、陰謀に関する言説が世にあふれている。そういった言説には暗黙の前提があるように思われる。それは、陰謀は計画したとおりに進行する、という前提である。しかし、陰謀がいつもうまくいくとは限らない。英国の哲学者、カール・R・ポパーは陰謀に関して次のように指摘している。「陰謀は決して――あるいは「めったに」――意図した仕方では進行しない」(『推測と反駁』、藤本隆志他訳、法政大学出版局、一九八〇年、一九九〜二〇〇頁)。『椿三十郎』に限らず、陰謀が露見して計画が失敗に終わるという話は多い。策を練りに練っても、失敗する時は失敗する。暗黙の前提には問題があるようである。
とはいえ、陰謀に関する言説は魅力的である。その魅力も陰謀が計画したとおりに進行するという暗黙の前提によるところが大きいのではないか。
日々の生活の中ではうまくいくこともあれば、そうならないこともある。うまくいくかどうかわからないということは、不確実であることを示している。一方、陰謀に関する言説の中では、陰謀はつねにうまくいく。つねにうまくいくということは、確実であることを示している。「陰謀が失敗したらどうなるのか」などと心配する必要はない。
確実なものは魅力的である。不確実な日々に耐えられない人間にとって、確実なものは一時的な拠りどころとなる。陰謀に関する言説もそれになり得る。言説の中では、不確実な世界に振りまわされることなく、陰謀が確実に進行する。また、確実なものは人々をひきつけるとともに、人々を強く結びつける。陰謀に関する言説を多くの人々と共有することによって、不確実な日々が生みだす不安を忘れることができるかも知れない。だが、言説を共有する人々は、言説を受け容れない人たちに対して排他的になりやすい。
陰謀に関する言説から浮かび上がるものは、うまくいかない日々の中で拠りどころを求める人間の姿ではないか。それは、見ず知らずの他人の姿ではない。
(『ともしび』2025年4月号掲載 ※役職等は発行時のまま掲載しています)
●お問い合わせ先
〒600-8164 京都市下京区諏訪町通六条下る上柳町199 真宗大谷派教学研究所 TEL 075-371-8750 FAX 075-371-6171