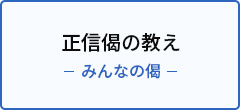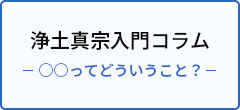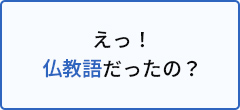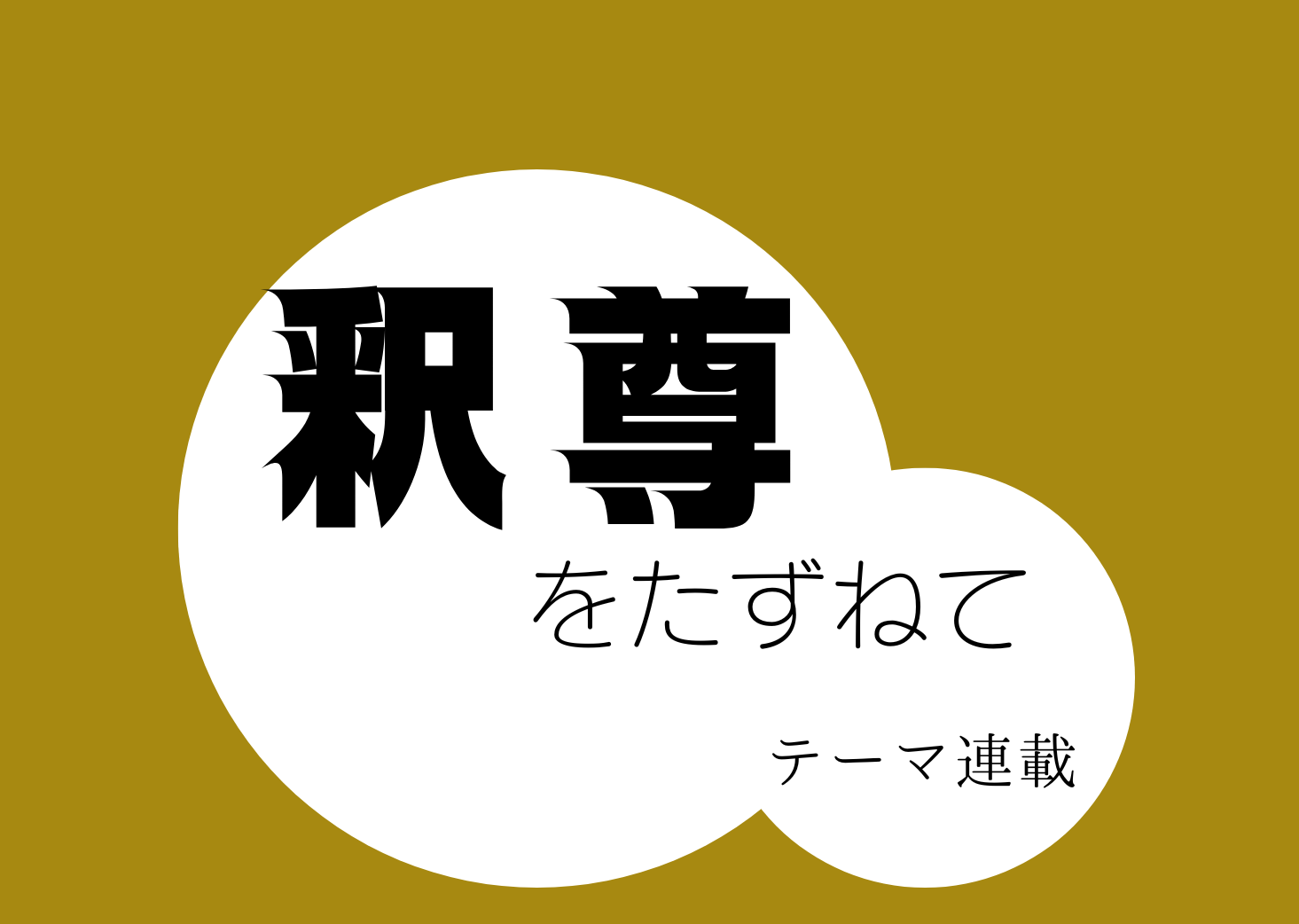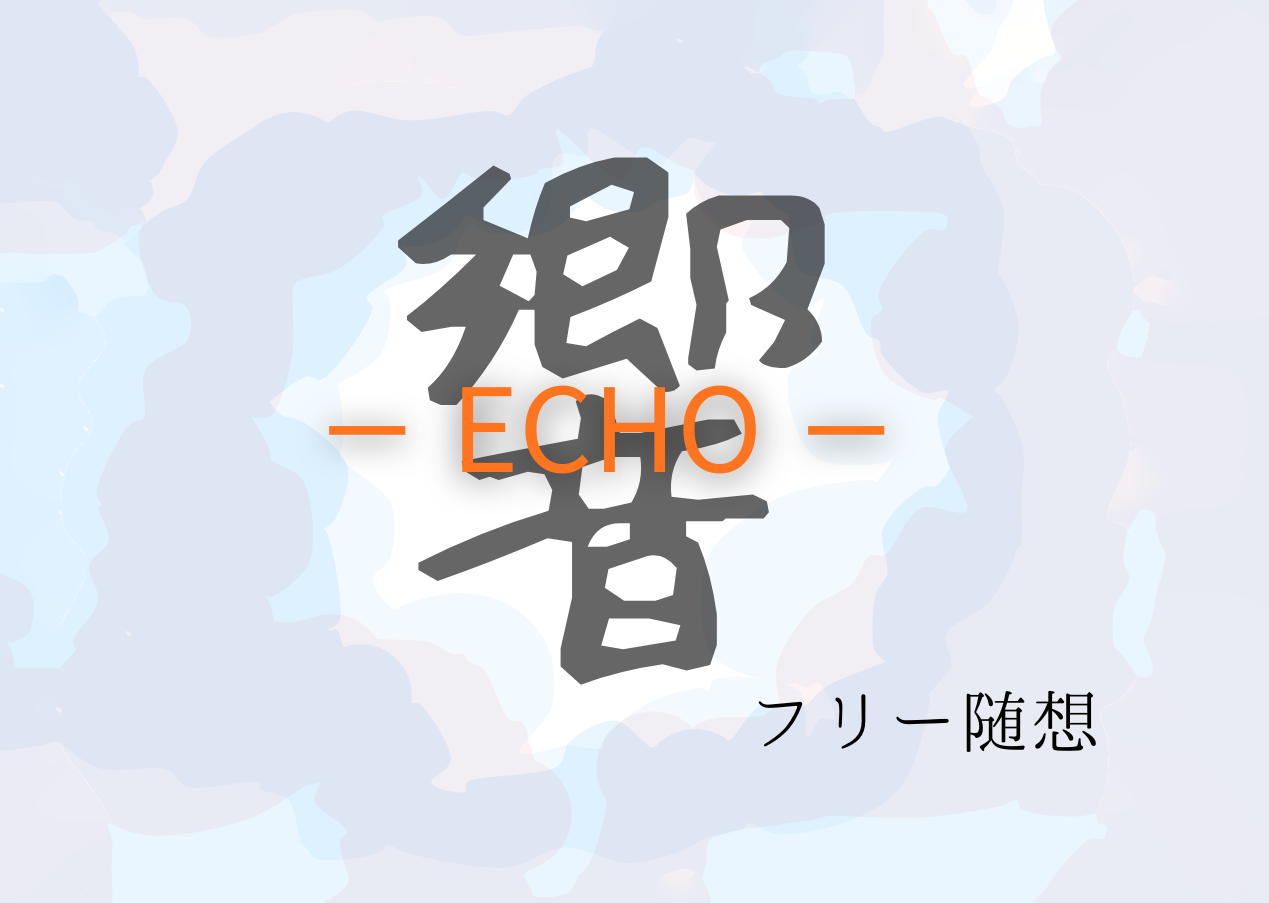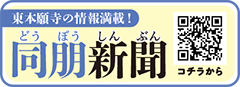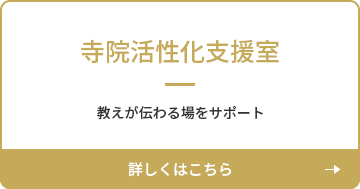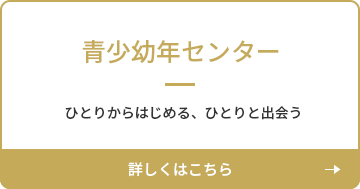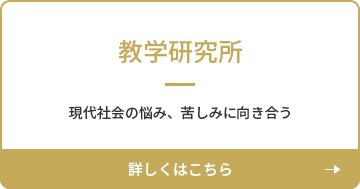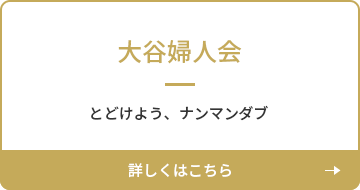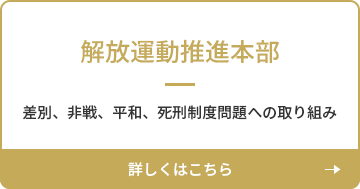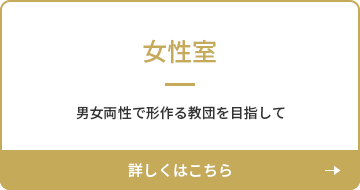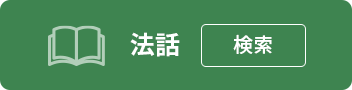世俗の王であり仏さまとしての聖徳太子
著者:織田顕祐(大谷大学名誉教授)
『大日本国粟散王聖徳太子奉讃』の第一首目は、
(『定本 親鸞聖人全集』二巻・二五一頁)
和国の教主聖徳皇
広大恩徳謝しがたし
一心に帰命したてまつり
奉讃不退ならしめよ
とあります。
聖徳太子を「聖徳太子」と呼ばないで、書名では「大日本国の粟散王」とお呼びになり、和讃では「聖徳皇」と呼んでおられます。ですから、単に聖徳太子の聖徳を奉讃するという視点から一歩進んで、太子ではなく、王(皇)としていただかれているということなのです。
王というのはどういうことかというと、王子が即位して王になったということです。つまり太子が仏さまになったということではないかと思うのです。つまり自分にとっての王になった、仏さまになったという意味です。ですから、「大日本国の粟散王」であるというようにおっしゃるのだと思うのです。
そして、粟散王とはどういうことかといいますと、これは、インドの伝統で理想的な政治を行う王さまのことを転輪聖王といいます。この名前は、仏さまの名前ではなくて、世俗の王さまのことです。そして、この転輪聖王は、治める国の大きさによって、名前がかわっていくのですが、最後の最後、とても小さい国を治める時の名を粟散王というのです。粟が散ったような小さく細かな国を治める王、つまり、日本の国を治める王ということです。ですから、「大日本国粟散王聖徳太子」という名前になるのです。
その王さまは何をするのかというと、仏法興隆です。お寺を作ったり、お坊さんを養成したり、お経を一生懸命写したり。そうした仏法が広まる環境を整える王さまのことを転輪聖王というわけです。
一方、こちらは、仏さまの仕事になるのですが、衆生済度という仕事があります。教えを説いて人々を済度する、導くというお仕事です。
こういうように、役割分担ではないですけれど、課題が異なるわけです。お寺があっても、誰も教えを説かなかったならば、お寺はただの建物です。しかし、建物がなければ、場所がなければ、その教えを説くこともできません。ですから二つのものが相まって、仏法が人々のところへ届いていく。こういう二つの要素のことを仏法興隆、衆生済度というのです。転輪聖王の役目は仏法興隆、仏さまの役目は衆生済度。しかし、聖徳太子という方は、日本の伝統の中で、どちらとしても呼ばれてきたわけです。仏法興隆の人であり、衆生済度の人としても呼ばれてきた。つまり、聖徳太子は世俗の王でもあり、仏さまとしてもいただかれてきたのです。
『親鸞聖人と聖徳太子』(東本願寺出版)より
東本願寺出版発行『真宗の生活』(2020年版⑪)より
『真宗の生活』は親鸞聖人の教えにふれ、聞法の場などで語り合いの手がかりとなることを願って毎年東本願寺出版より発行されている冊子です。本文は『真宗の生活』(2020年版)をそのまま記載しています。
東本願寺出版の書籍はこちらから