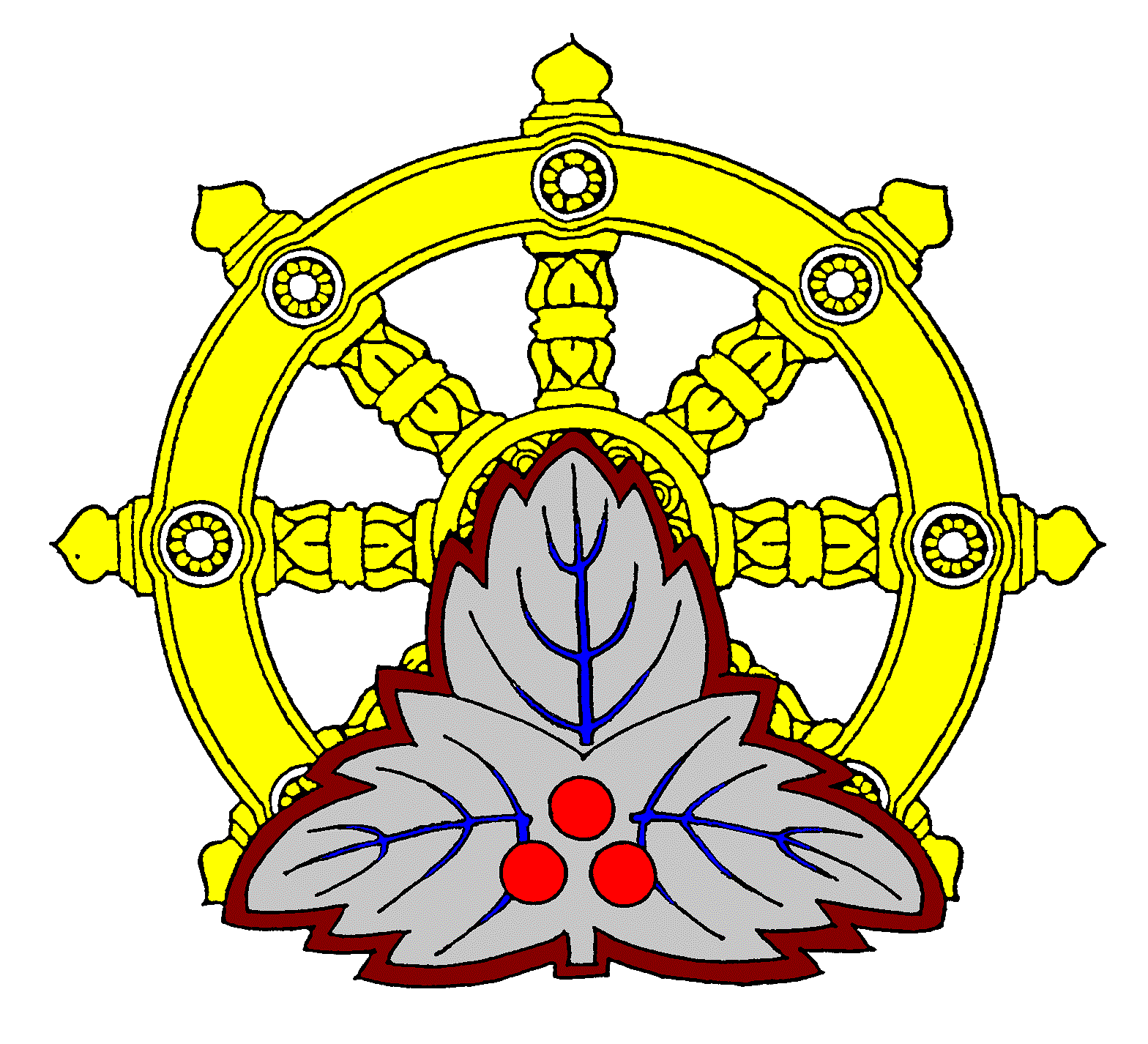恩徳讃へのざわめき
(鶴見 晃 教学研究所所員)
如来大悲の恩徳は
身を粉にしても報ずべし
師主知識の恩徳も
ほねをくだきても謝すべし(聖典五〇五頁)
報恩講の最後に勤まる和讃・恩徳讃は、真宗門徒の心の歌ともいうべき和讃である。私は宗祖が作られた数々の和讃の中でも、特に力のこもった一首ではないかと思っている。しかしその言葉に頷けない、違和感があるという声を時折聞くのも実際である。正直に言って、私もこの和讃に心がざわめく一人である。それは特に「べし」の語の響きについてである。
「べし」は、推量や適当、可能、義務、勧誘、命令の他、自分の行動に対しての意志や決意の意を表すなど、文脈によって様々な意味を持つ。浄土真宗を学び始めた頃の私にとって、この「べし」は、自らの意志や決意を伴わない中で命令や義務の声に聞こえた。そこにあったのは、たとえ仏恩・師恩への報謝であれ、強制への拒否感であった。しかし、単なる拒否感ではなく、恩徳に対する報謝が人生を尽くしてもなお足らざるものであることについては、そうであるに違いない、そうでありたいという、憧れに近い感情も共在していた。そのような、「べし」の一言に対する拒絶と憧憬の感情のはざまに、今なお私にとって恩徳讃に対する心のざわめきがある。
この和讃は、身と骨が入れ替わるが、先輩聖覚法印の、「つらつら教授の恩徳を思えば、実に弥陀の悲願に等しきものか。骨を粉にしてこれを報ずべし、身を摧きてこれを謝すべし」(法然上人御仏事表白文)という言葉を元としているといわれる。粉骨砕身の語は、仏典にも用例があり、力を尽くして努める意の慣用句ではある。しかし、法然上人の恩徳を弥陀の悲願に等しいものとしていただき、報謝の志を表白した先輩の言葉は、呼びかけの声となって宗祖の心に響き、「私も」という心を呼び起こしたに違いない。そのように報謝の志が聖覚法印から宗祖へと共鳴したところに恩徳讃の言葉が成ったのではなかろうか。
恩徳讃を記す宗祖に思い出されたのは、法然上人の主著『選択本願念仏集』を書写したことであろう。書写を通して師から弟子へと教えの流通が依託され、宗祖は、名を改め、新しく「善信」を名のることによってその依託に応えた。それは、それ以後の人生を私物化することなく、師から書を託された人生として、どこまでも「教えを善く信じて歩まん」という意志、決意として受け止めていく、師への全身をあげての応答であったのであろう。その依託と応答は、聖覚法印の言葉に呼応して恩徳讃を記した宗祖の原点であり、三十三歳以後の人生の時間の意味ではなかったのではないか。
人としてのいのちが尽くされるまでの時間。その時間をどう生きるのか。人生を自分のものだと執着し、時間を捧げることを惜しみ、拒んでいる。人としてのいのちを私有化していることの現れが、私にとって恩徳讃への心のざわめきである。そのざわめきは恩徳讃があの言葉であるからこそ起こる。そこに私にとっての恩徳讃がある。
(『ともしび』2016年12月号掲載 ※役職等は発行時のまま掲載しています)
「聞」のバックナンバーはこちら
●お問い合わせ先
〒600-8164 京都市下京区諏訪町通六条下る上柳町199
真宗大谷派教学研究所
TEL 075-371-8750 FAX 075-371-8723