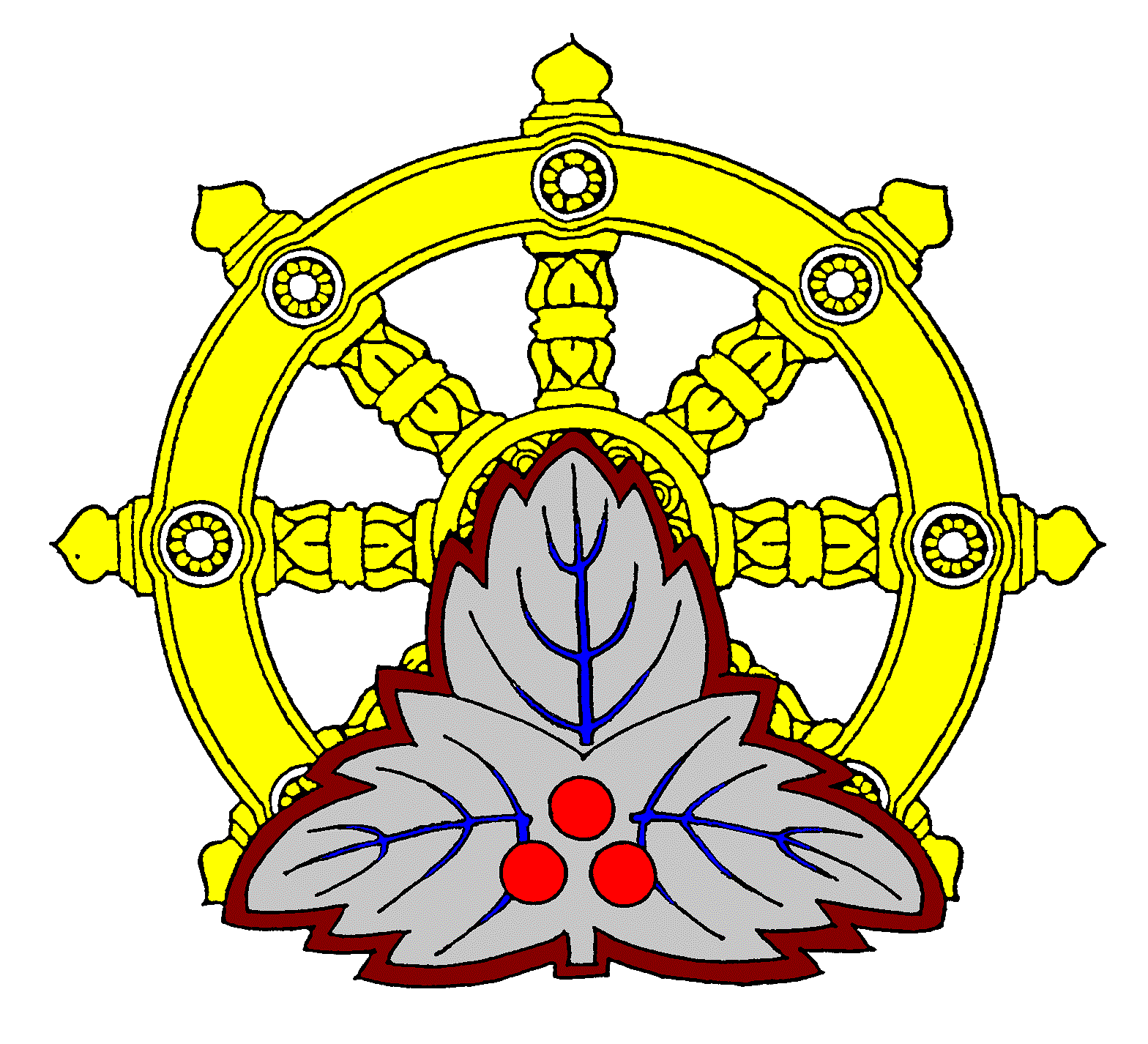弱さに宿る主体性
(中山 善雄 教学研究所研究員)
幼少時、家の事情があり、住んでいた町から隣村の幼稚園までバスで通っていた。元々気後れする気質でもあり、私はその幼稚園にうまく馴染むことができなかった。ある時、大人の目がない中で、何人かの子に囲まれて乱暴されたことがある。子どもにはよくあることなのであろうが、私は幼稚園に行くことを畏れるようになった。それでも居場所を得るために、周囲に何とか合わせ、流れについていこうとし始めたのが、その頃であった。
年齢を重ねる中でそのことは忘れていった。しかし、他者の眼差しを畏れ、弱い者・暗い者と思われないために装う中で、いつの間にか「強い者・できる者でなければならない」という価値観(ものさし)が身についていった。その結果、人から暴力を振るわれることはなくとも、私自身のものさしが私を監視し、裁くようになったのである。
自分がもっている「こうあるべき」「こうありたい」という思いは、畏れの中で自ら内に取り込んでいった世間の観念であるにもかかわらず、それを自分の確かな主体として自明視していた。ある時期から、その生き方が虚偽であることは感覚し始めていたものの、自我意識の中で作られた「私」は、限りなく「私」を確固なものとし、支配権を広げることを主張する。その妄執に、私は手もなく翻弄されていった。
そのなかで道標となったのは、他ならない、自分が一番嫌悪していた、自分の弱さと脆さである。強く自分を固めようとしても、そうあることができないためらいが残り、小さなことに悩む、割り切れない自分の心がある。それが「こうあるべき」と自ら抑圧する私に、「それでいいのか」「本当にそうなのか」と微かに問いかけてきていた。
自らの弱さを、自分の生き方への問いかけとして聞くようになったのは、ある人から「本当の主体性は、うずくまってしまうような弱さの中にいきづいている」という言葉をかけていただいたことから始まった。そこには人間の弱さを限りなく尊ぶ眼差しがあった。その眼差しを受けて自分の弱さが、弱い自分を嫌悪する私を痛む問いかけの声となり、その中で、記憶から消し去っていた幼い頃の光景と、強弱で裁く世界に悲しさを感じていた自分の心が少しずつ蘇ってきたのである。
親鸞は、「門余」という言葉を掲げ、「余はすなわち本願一乗海なり」(『教行信証』化身土巻、『真宗聖典』三四一頁) と記している。この「余」は、私的な解釈であるが、「聖道門」という「こうあるべき」という観念の中で、人が抱える「余り」の感覚、すなわち「割り切れなさ」でもあろう。そこに「本願」が宿るということであろうか。どれほど自己軽蔑の中で弱さや悲しみを消そうとしても、それゆえにこそ、その身を痛み、自己を回復せしめようとする確かな呼びかけがそこにある。
私たちが余計なものとして軽蔑し見捨ててしまう割り切れなさ・弱さにこそ、本願の兆し・主体の根拠を見出していく眼差しを仰ぎ、弱さは弱さのままに安んじて生きていける世界を明らかにしていきたい。
(『ともしび』2018年8月号掲載 ※役職等は発行時のまま掲載しています)
「聞」のバックナンバーはこちら
●お問い合わせ先
〒600-8164 京都市下京区諏訪町通六条下る上柳町199
真宗大谷派教学研究所
TEL 075-371-8750 FAX 075-371-8723