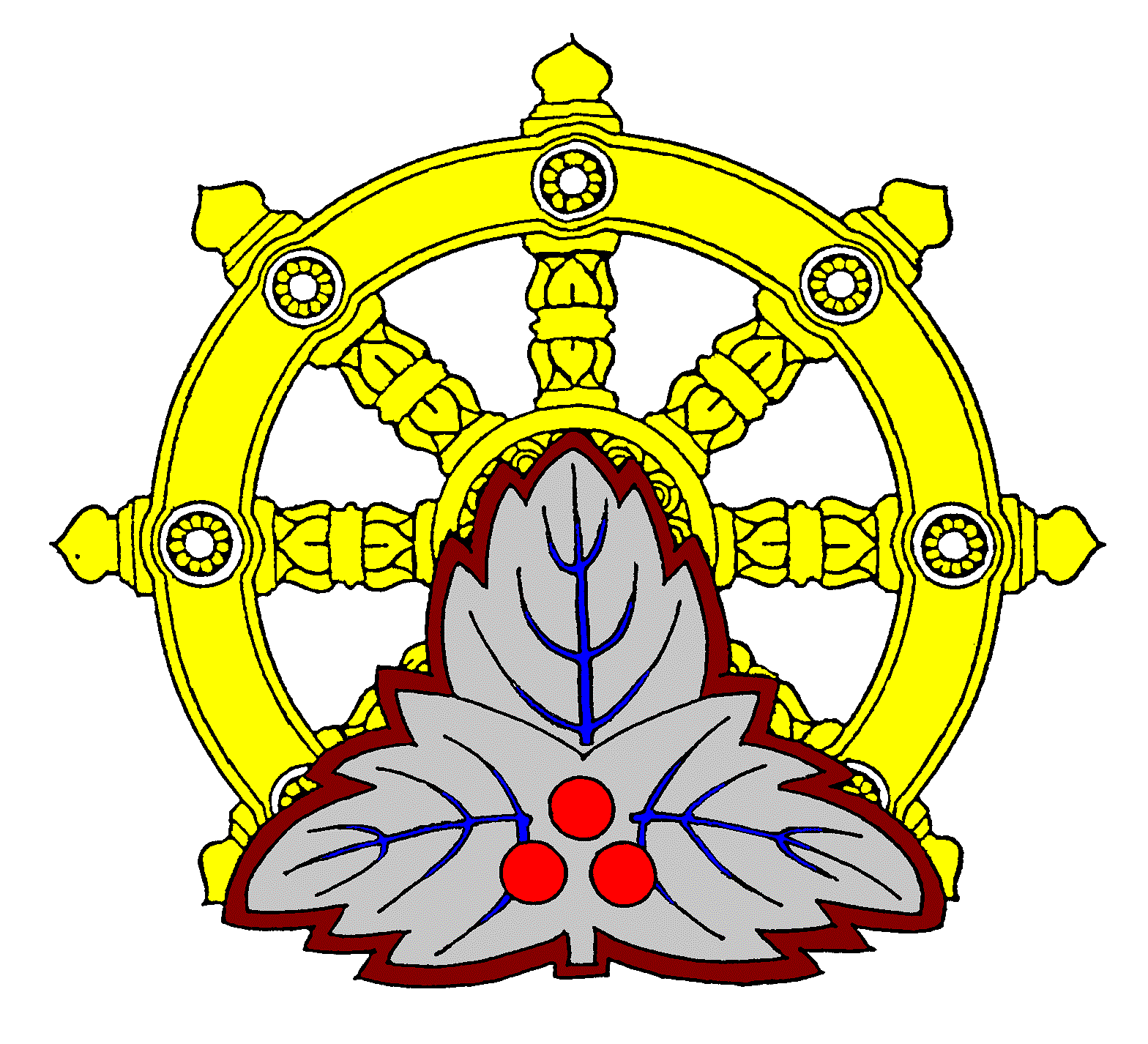如来二種の回向に すすめいれしめおわします
(『正像末和讃』・『真宗聖典』五〇八頁)
この七月、富山県の砺波地域を訪れた。聖徳太子信仰の調査のためであったが、折に触れて、同朋奉讃式の太子和讃を思い出した。
太子和讃の中でも上記の和讃が、私には印象深い。私は、子どもの頃から長い間、「聖徳皇のあわれみに」と思っていた。後に間違っていたことに気づいたが、同時に発声のしにくさに閉口するようにもなった。その二つの意味で印象深い和讃であったが、今回もう一つ印象深さが加わったような気がする。
砺波地域には、聖徳太子の石仏が太子堂や道ばたに数多く安置されており、その数は二四〇体をこえるという(尾田武雄『とやまの石仏たち』、桂書房、二〇〇八年)。石仏は南無仏太子像と呼ばれ、上半身が裸で赤い袴を着け、合掌する姿をしている。これは太子二歳の時、東を向いて合掌し、南無仏と三回称えたという伝記に基づく。井波別院瑞泉寺太子堂の太子像がこの南無仏太子像であり、石仏はこれに由来している。
一八七九(明治十二)年、瑞泉寺は火災で焼失し、太子堂も焼け落ちた。本堂は一八八五(明治十八)年に再建されたが、引き続き太子堂再建のため、太子像の巡回、太子伝の絵解きが行われるようになった。その巡回が熱狂的に迎えられたのにつれて、太子堂が再建された一九一八(大正七)年までの約三十年間に集中して、主として若衆によって石仏が作られたという。
石仏造立の理由は、地区のためであったり、何らかの記念であったり、戦没者の慰霊や供養、健康祈願等であったという。石仏造立が人々の生活の祈りに根ざしていることを、訪れる前は不思議にも思わなかった。だが石仏を巡りながら、近世ではなく近代の時代に、それも若い人々によって石仏が造られたことを考えさせられた。
近代は、大きくいうと宗教の社会的位置が後退してきた時代である。そのような近代の時代に育った、近代人の祈りが砺波では太子信仰の形をとった。そして、その信仰が今に伝わっている。それは近代社会に残った前近代的なものの名残とも考えられる。しかし私には、近代の中に興り、息づいてきた太子信仰が、時代が変わってもなお人々の祈りを受けとめ続ける真宗の姿を示しているのではないかと思われた。
勿論、造立理由に見るように、石仏は、「ただ念仏」と「信ずる」(『歎異抄』)という真宗信仰の原型からすると、過分に民間信仰的な側面があることは否めない。太子を祀る人々の多くは、篤信の念仏者でもあったが、その側面から見れば、篤信の真宗地帯が、生活の地平では民間信仰的なものを色濃く有しているということでもある。しかしそれは否定すべきことというよりも、人々の祈りを受けとめる真宗の持つ包容性と、念仏へと人々を導くはたらきを示すものではないのか。その意味で、人々にとって太子は、「あわれみ」をもって祈りを受けとめつつ「護持養育」し、如来回向の念仏に「すすめいれしめ」てくれる、生活の祈りと念仏を繫ぐ存在だったのではないか。
砺波の人々は、「太子さま」と「さま」をつけて太子を呼んできた。そしてどの石仏の前にも花が手向けられていた。その人々にとっては今も、太子の「あわれみ」は、「お」をつけずにおれないものであるのではないか。砺波の太子信仰に、和讃の具体的な姿を見るような思いがした。
(教学研究所所員・鶴見 晃)
[教研だより(159)]『真宗2019年10月号』より
※役職等は発行時のまま掲載しています。