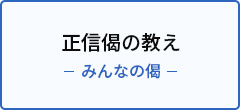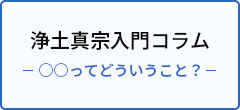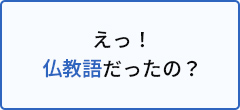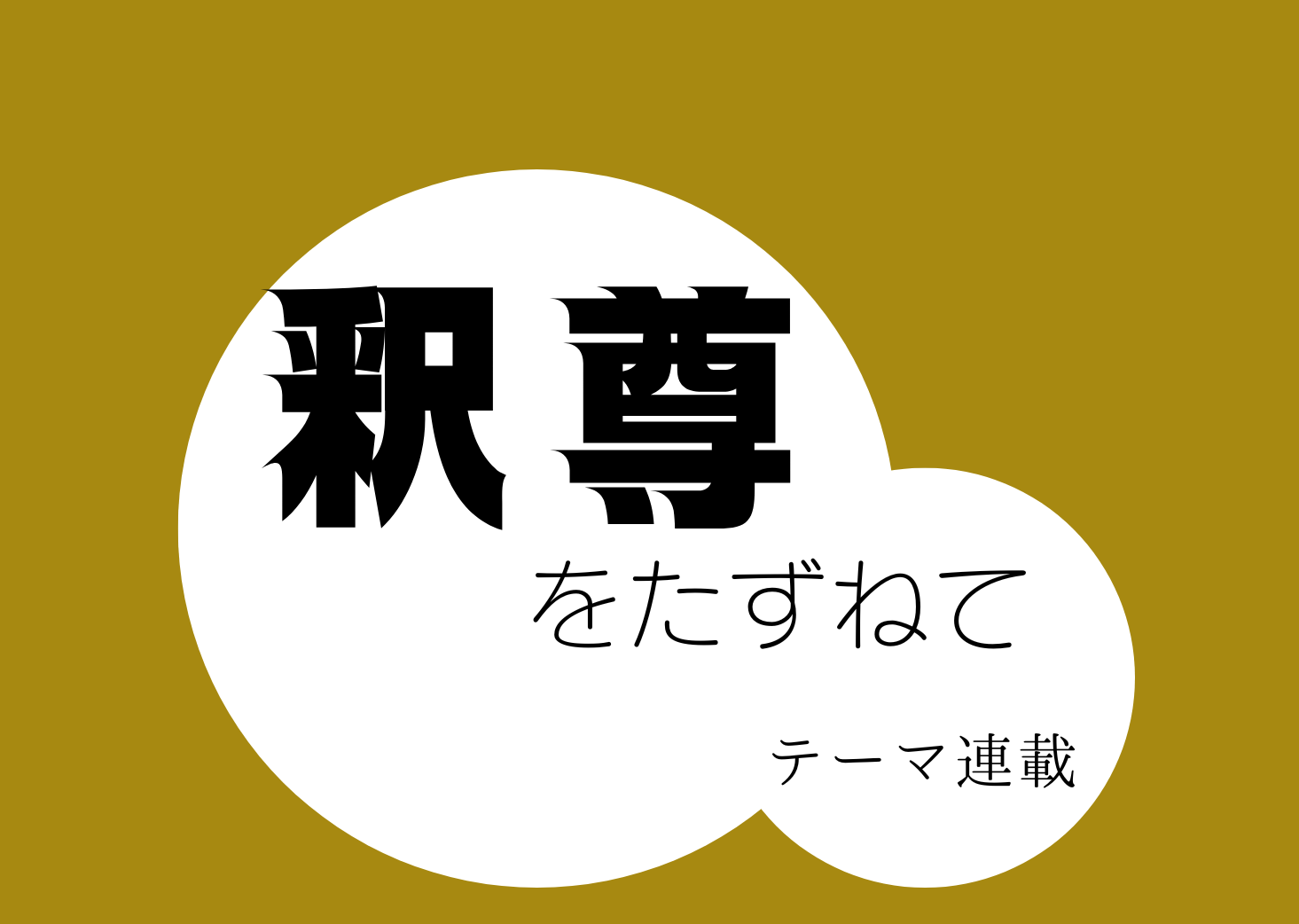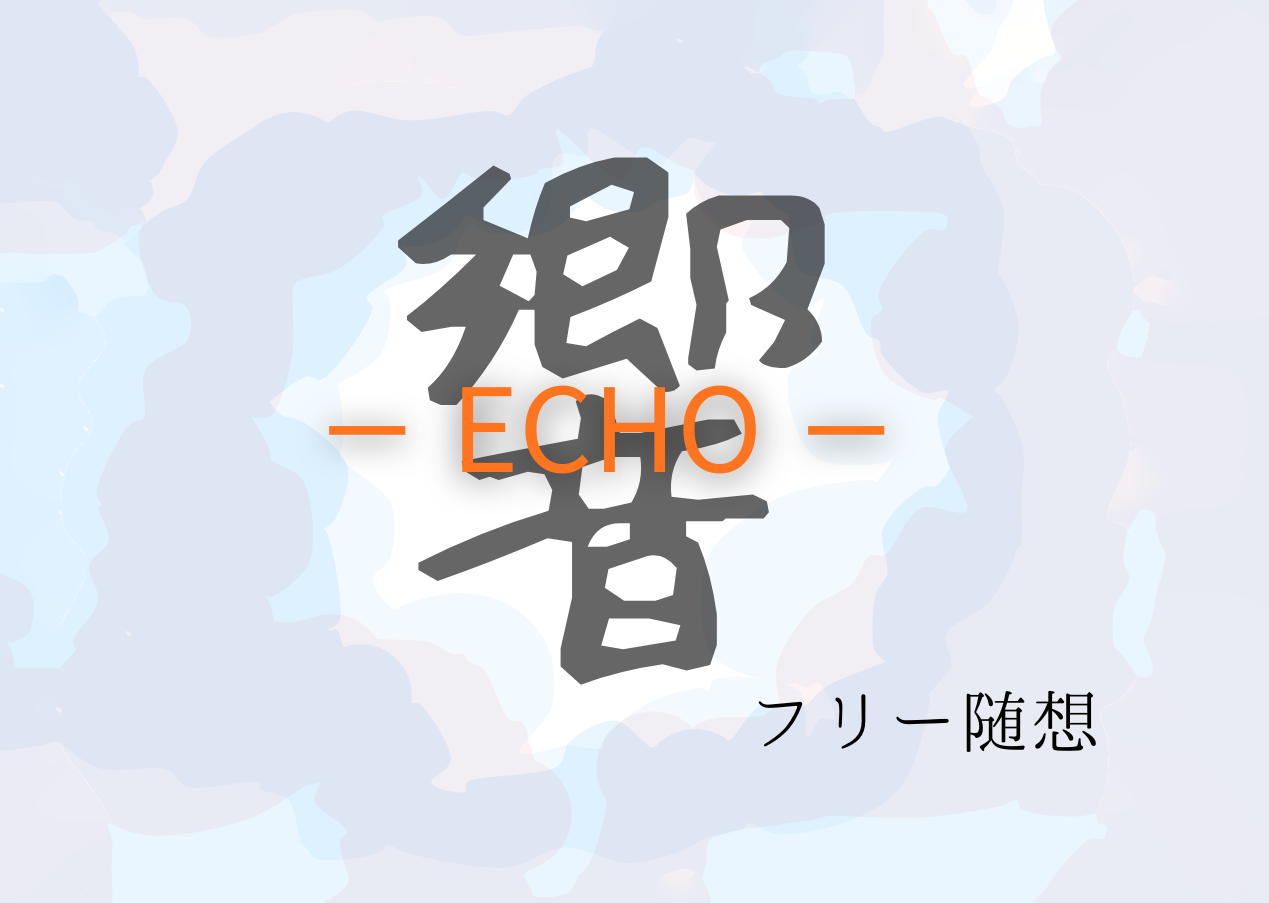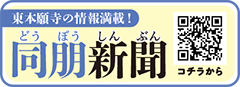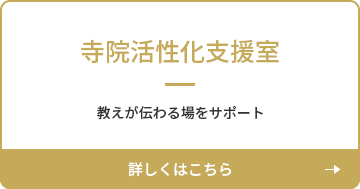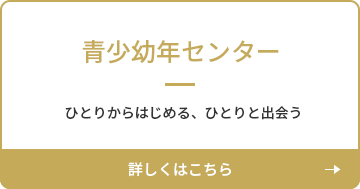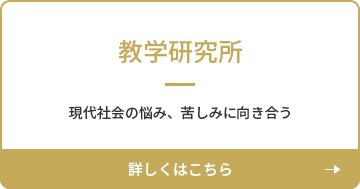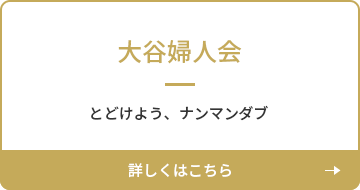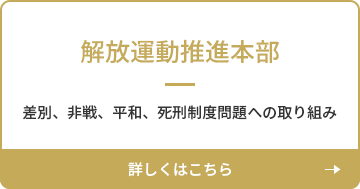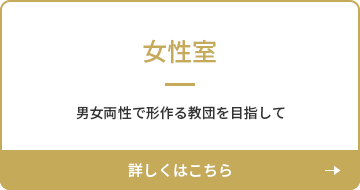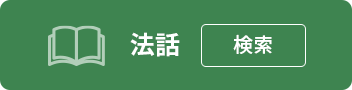拝まない者も おがまれている 拝まないときも おがまれている
法語の出典:東井義雄
本文著者:志慶眞文雄(しげま小児科医院院長)
この言葉は、東井義雄先生の
(『東井義雄詩集』探究社)
「無理をせんといてください」/「無理をしないで休んでいてください」/腰が曲がって/ひどく小さくなってしまった老妻に/何べんも気づかってもらいながら/土手の草を刈る/何だか/うれしく/何だか/しあわせで……/「拝まない者も/おがまれている/拝まないときも/おがまれている」/「ここが/み手の/まんなか」/と、/土手の草を刈らせてもらう/何だか/うれしく/何だか/しあわせで……。
という「何だかうれしく」という詩の一節です。すぐに疲れてしまう東井先生への奥さんの心づかい、腰が曲がってひどく小さくなってしまった奥さんへの先生の温かいまなざし。阿弥陀さまと共にある、ご夫妻の豊かで深くて穏やかな日常の一コマが浮かんで来てまぶたが熱くなります。
この詩は、「拝まない」「おがまれている」と、漢字とひらがなが使い分けられています。一般的には、「拝む」とは人間が神仏を礼拝することですが、引き続いて「ここが/み手の/まんなか」と人間が阿弥陀さまによって摂取されているという視点への転換があります。その視点を明確にするためにひらがな「おがまれている」が使われています。
真宗聖典には、「もろもろの衆生は、みなこれ如来の子なり」(『教行信証』真宗聖典二六七頁・第二版三〇三頁)、「十方の如来は衆生を 一子のごとく憐念す」(「浄土和讃」真宗聖典四八九頁・第二版五八八頁)とあり、さまざまな悩みをいだきつつ生きるすべてのものは、如来大悲によって一人ひとりが一子のごとくかけがえのない大切な仏の子として念じられているとあります。
その如来のまなざしに背を向けて生きて来た自分の姿が思われます。私は十歳のある日、いずれ自分が死んでいなくなるという恐怖と悲しみにおそわれました。どこから来てどこに去って行くのかも知らず、ただ死んで消えてしまう人生には何の意味もないとしか思えず虚しい日々を送っていました。せめて小さい頃から興味があった天文学か素粒子物理学を学べば、何らかの展望が開けるかと広島大学大学院に進学し素粒子研究を始めました。しかし科学的な方法では道は開けないことがわかり博士課程を退学しました。
そのように生きるのに四苦八苦している私の姿を見て、浄土真宗と縁があった熊本出身の妻が、広島大学会館で開催されている「歎異抄の会」に誘ってくれました。大学院を退学し紆余曲折あって医学部を再受験、その合格発表の日に「歎異抄の会」があり参加しました。それが浄土真宗の聞法を始めるきっかけでしたが、分別を超えた阿弥陀さまの世界をいただくための悪戦苦闘の日々の始まりでもありました。
聞法の歩みの中で、「死ぬも南無阿弥陀仏、生きるも南無阿弥陀仏、ただこのこと一つ」と、すべてのものを分け隔てなく救うと誓願された阿弥陀さまにおまかせする以外、生死を超える道はないことを知らされました。おおいなるものと共にある東井先生ご夫妻のお姿に、あらためて生と死にゆるぎない安住の地が開かれてあることを思います。
東本願寺出版発行『今日のことば』(2020年版【11月】)より
『今日のことば』は真宗教団連合発行の『法語カレンダー』のことばを身近に感じていただくため、毎年東本願寺出版から発行される随想集です。本文中の役職等は『今日のことば』(2020年版)発行時のまま掲載しています。
東本願寺出版の書籍はこちらから