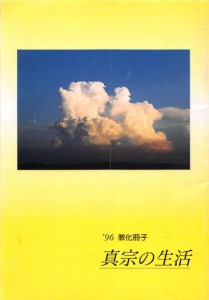1996(平成8)年 真宗の生活 11月
<報恩の心>
病院のべッドの上で死ぬより、畳の上で死ぬのが本望でしょうとの医師のはからいで、寝返りも許されない絶対安静の父は担架に乗せられ、病院の窓から運び出されて、家に帰って来た。そこは田と畑に囲まれ、松林の向こうに日本海の広がる小さな農村であって。海から松林を通り抜けて窓にそよぐ風がさいわいしたのであろうか、年とともに結核は固まっていった。一命を取り止めたのであった。しかし生涯働くことは許されなかった。
十二人の子供に恵まれはしたものの、わずかの田畑からの収入だけでは生計は賄えなかった。恵まれた才能を生かすどころか、働くことさえできなかった父の苦悶は激しいものであった。暁烏敏に出会ったのはそんな苦悶のなかであった。
五十代に入つて、母と長兄の田畑仕事をわずかではあるが手伝えるようになった。そのころからてあろう。父は暁烏敏のお寺へ、夏の講習会と報恩講に、荷車にあるいは西瓜を、あるいは大根を、さつまいもを積んで、三里半(十四キロ)の道を運ぶようになつた。夏は炎天のなかを、晩秋は冷たい時雨のなかを、穴ぼこの砂利道を、肩で息をし、何度も休憩しながら。父にとってそれは死を覚悟のことであったように見えた。子供心にもそう見えた。坂道のある途中まで後押しを手伝ったこともある。家を出発するときの喜ぴに満ち溢れた父の顔が、そしていそいそと荷を積む母の顔が、およそ四十年も前のことであるのに、あたかも昨日のことであったかのように、私の脳裏に今もありありと思い浮かぶのである。
三里半の道のりはそのまま暁烏先生への道であり、清沢満之先生への道であり、親鸞聖人への道であり、阿弥陀仏への道であり、妻への、子供たちへの道であり、そして父そのものへの道であった。それはまた暁烏敏先生の道であり、清沢先生の道であり、親鸞聖人の道であり、阿弥陀仏の道であり、妻の、子供たちの道であり、父そのものの道であった。それは無量の世界への道であり、無量の世界の道であったのだ。いのちそのものであったのだ。
いのちを得たものに、身を粉にしても、骨をくだいてもなお、およぴ得ない喜びの情が、報恩の心が燃えたぎる。父の先生への感謝はまた、先生の父への感謝であったのだ。そしてその感謝はそのまま、十方の衆生を拝まれる阿弥陀仏の慈悲であったのだ。
いもつ久里
いもをつくりて 久るまひき はるばる佛の もとにきたるか
敏
先生にいただいたお歌を抱きしめて父は世を去った。
報恩の心が今、私に乗り移ってくるのを感じて、涙を流している。
『真宗の生活 1996年 11月』「報恩の心」