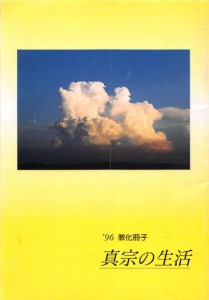1996(平成8)年 真宗の生活 8月
<”亡霊”に悩まされて…>
(問)
姑の兄が亡くなって以来、姑は「兄が毎晩のように枕元に立っている」と言います。私は亡霊など信じていませんので、「それはお母さんの妄想妄想でしょう。そんなことに迷わず、もっとしっかりしてください」と言いますが、姑は納得してくれません。
真宗の教えでは、霊信仰は否定していると聞いていますが、姑にとってはそれが亡霊であろうがなんであろうが、毎晩のように枕元に立っている事実は否定できないようです。私はこの問題をどのように受け止め、姑と話し合ったらよいのでしようか。
(答)
身近にあった人が亡くなりますと、私たちは時として「さぞかしいろいろと心残りもあっただろうに」と思いやることがあります。そして、時には死者が、そのことを誰かに知らせたいと、何らかのはたらきかけをするのではないか、などと考えたりもします。ところが、ついには、そうした死者からのはたらきかけや催促に対して、適切な対処をしないと、今度は自分たちに祟るのではないかと、亡くなった人よりも、自分たちに対する心配に悩まされることにさえなるわけです。
ところで、「自分が生きている限り自分には死はない。そして、死が訪れた時には、自分はすでにいない」というエピクロス(古代ギリシヤの哲学者)の言葉は、私たちが、自分の死について知ろうとしても、それは直接体験できず、ただ、他人の死からそれを学ぶ以外にない、ということを示しています。
私たちは、親子・夫婦・兄弟・親族・師弟・友人・知人など、多くの人たちとさまざまな関係を結んで生きています。そして、身近にあった人が亡くなりますと、私たちは、その人と共にあった日々のことを思い起こし、今は亡きその人と、「日ごろから、おたがいの関係を誠実に尽くしてきたであろうか」とふり返ります。そこには、後悔や反省ばかりが多く、共に生きた月日のうちに悔いなき日々などとても見いだせない場合も少なくありません。そして「棺を蓋いて事さだまる」という言葉のとおり、柩の蓋を閉じれば、その人の生涯は、どんな内容であれ、それで「完結した」と覚悟せねばならないのです。
どのように生きられたかも知れない人生を、私たちは、いつたい何に向かつて生きてきたのでしようか。そして、自らのいのちを尽くすべきものが明らかにならないさきに、人生が尽きはてていつてしまうとしたら、それこそ一大事です。
仏陀は「諸行無常」(すべて生じたるものは必ず滅し、永久不変なるものはあり得ない)と教えられました。そして、亡き人もまた、私たち一人ひとりが、同様に「死」
をもって終わっていかねばならない身であることを教え示してくださっているのです。他者の死を「人生無常」と受け止め、「自らの死を迎えるまで、いましばらくのあいだ限りある人生を何に尽くさせていただくべきか」- 。この問いの真正面に私たちが立つとき、私たちの前には、死者・生者、共に生きる道が開かれてくるのではないかと思います。
『真宗の生活 1996年 8月』「”亡霊”に悩まされて…」