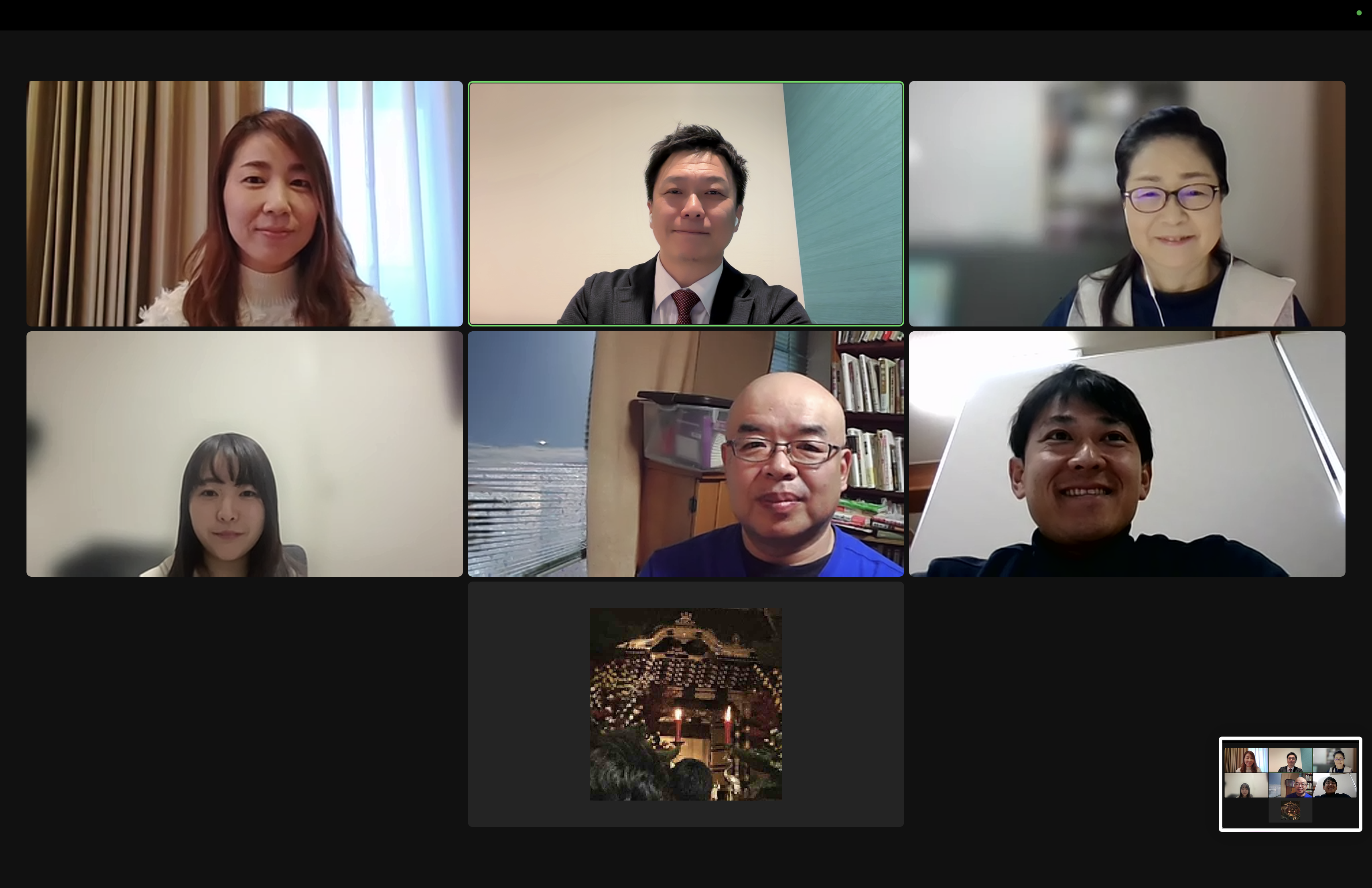光あるうち闇の中を歩め (名和 達宣 教学研究所研究員)
二十年ほど前の夏、真宗本廟・御影堂門の前で夜を明かしたことがある。 当時、私は大学の四年生で、人間関係のもつれから行き詰まり、気がつけば住まいのあった大阪の街を離れて京都にたどり着いていた。 門前の薄明りの中で、三冊の文庫本を読んだ。中島敦『山月記』、芥川龍之介『羅生門』、そしてトルストイ『光あるうち光の中を歩め』である。なぜその三冊を選んだのかはよく覚えていない。 ただ、後になって読み返してみると、前二冊は、いずれも主人公が夜闇の中に消えて終わる結末であるのに対し、後の一冊は、光(キリストの教え)に出会ってめでたく物語が結ばれていることに気づかされた。 洋の東西を問わず、宗教において救済は、しばしば光と闇の比喩をもって説かれる。先のトルストイの作品はまさにその典型で、欲望や名利心など、世間の愛欲に浸っていた青年ユリウスが、ついには信仰を得て、光に包まれる中で人生を閉じていくまでの遍歴が、やや単調に描かれている。 ところが、その一見わかりやすい光の物語よりも、絶望的なほどの闇に貫かれた物語に、当時の私は強烈に惹きつけられた。旧友に別れを告げて夜の叢(くさむら)に消えていった虎(李徴)が、しがみつく老婆を死骸の上に蹴落として夜の底へ駆け下りた下人こそが、私ではないかと。そして彼らが救われなければ、私の救いもないのではないかとも。
翌年の春、京都の大谷大学へ入り、真宗の学びを始めることになった。御影堂門の前で過ごした時間が、進学に至る契機となったため、おのずから光と闇にまつわる表現に目が向いていった。たとえば「正像末和讃」に次のような一節がある。
無明長夜の燈炬(とうこ)なり
智眼くらしとかなしむな(聖典五〇三頁)
この言葉を、私は親鸞聖人による励ましの声として積極的に受けとめ、いつの頃からか、得意げに引用するようにもなった。しかし後年、ある友人のこぼした「無明の夜は、長いんだね…」という深い落胆の声を聞いた時、自身が安易な救済観(らしきもの)に留まっていたことに気づかされ、同時に、闇の中に消えた虎や下人を想い出した。 今、あらためて案ずるに、確かにかの和讃では、「無明長夜」が一気に明けるとは説かれていない。弥陀の本願は、闇の中を歩んでいく上での灯である、と言われるのみである。しかし、やはりそれで十分だというのが、真宗の救済ではないか。 元来、私たちは、どこで迷っているのかを知らずに、もがき苦しんでいる。夜を照らす灯とは、闇を闇と知らせ、夜を生きることに落着させるとともに、その夜が──たとえすぐに明けなくとも ──「必ず朝が来る」という流れ(道理)のうちにあることを知らせる智慧の光を表すだろう。 闇を闇と知るとは、光を失った状態ではなく、闇の世界に差し込む一閃の光と遇うことにほかならない。このような光と闇の関係を、親鸞聖人は「無碍の光明は無明の闇を破する恵日なり」(聖典一四九頁)と言い表したのだろう。 (『ともしび』2019年9月号掲載 ※役職等は発行時のまま掲載しています) 「聞」のバックナンバーはこちら
●お問い合わせ先
〒600-8164 京都市下京区諏訪町通六条下る上柳町199 真宗大谷派教学研究所 TEL 075-371-8750 FAX 075-371-8723