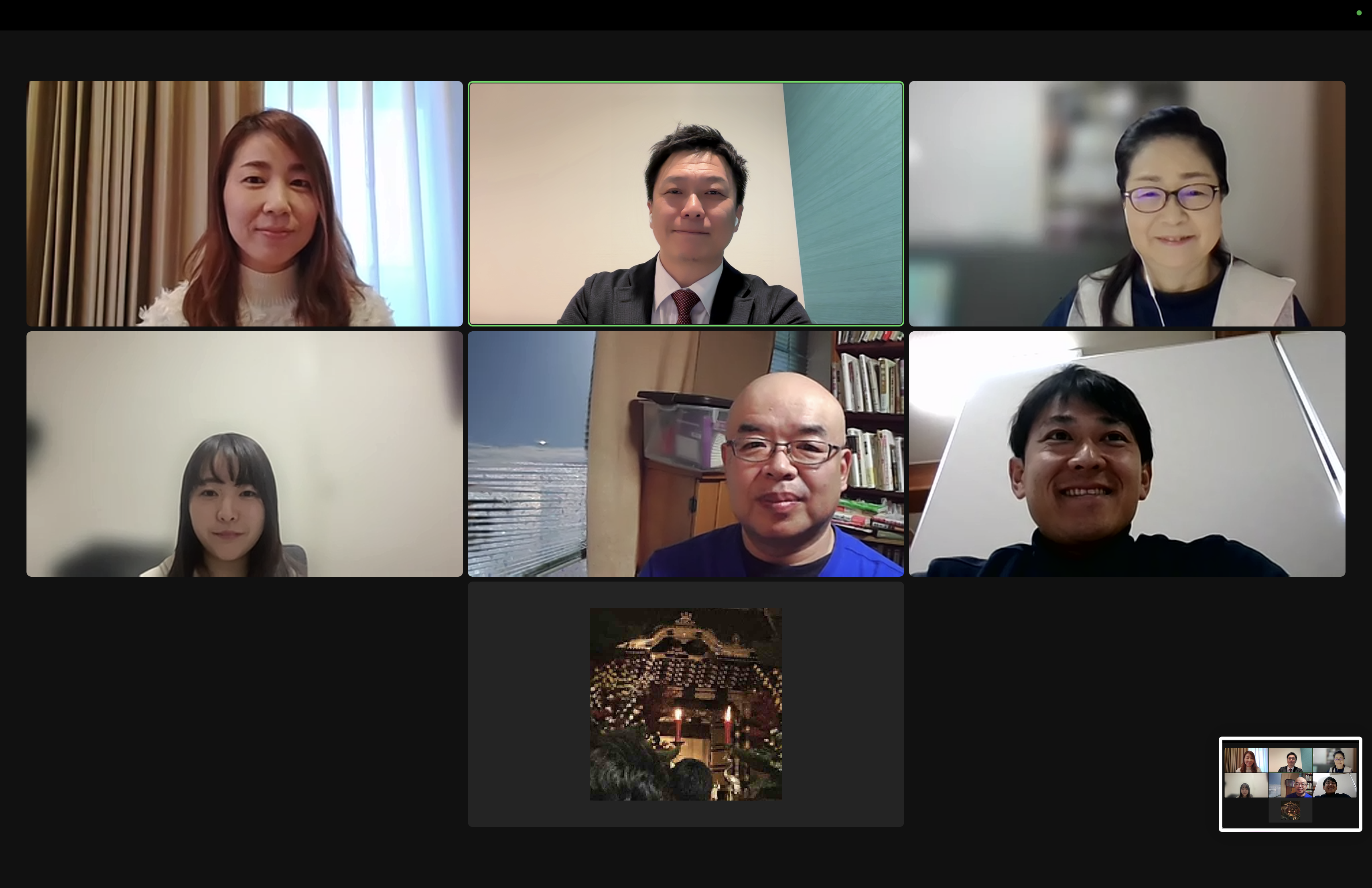< 真宗大谷派ハンセン病問題に関する懇談会交流集会部会委員 中杉 隆法 >
2013年夏、国立ハンセン病療養所邑久光明園に子どもたちの声が響き渡りました。「ただいま!」そして「おかえり!」。第1回目の昨年とはちょっとちがうあいさつで、子どもたちは光明園に帰ってきました。
昨年夏、さまざまな期待と不安の中で、たくさんの感動と課題が生み出された「ワクワク保養ツアー」から、あっという間に1年が経ち、子どもたちはみんなひとまわり大きくなって、再び光明園の地を踏んだのです。
おどおど、きょろきょろという印象の1年前とはちがい、前回からの保養ツアーがずっとそのまま続いていたかのような様子、まるでここは私たちの遊び場所というかのごとく、本当にいきいきとしたものでした。
「うみでおよぐことができたのが、いちばんうれしかったです」。
昨年に引き続き参加された小学校1年生の綾菜ちゃんが書いた感想文の1行目です。
「おかやまで海にいって、うきわにういたり深いところまでいきました。くらげや魚もいました。お友だちといっしょに思いきり泳ぎました」。
小学校3年生の栞里ちゃんも、海で遊んだ思い出を手紙に書いて送ってくれました。同時に「やはり今の福島では、夏休みに海で遊ぶという当たり前のことをさせてあげられないのです」と、お母さんは本当に悔しそうに小さな声でつぶやかれました。
ちょうどこの原稿を書いている時、2020年東京オリンピック開催が決定。直前の招致スピーチで、安倍首相は「海に漏れた汚染水は完全にコントロールされています」と発言しました。私は驚きと同時に、本当に楽しそうに光明園の海で遊んでいた子どもたちの姿が思い浮かびました。

穏やかな瀬戸内海にぽつんと浮かぶ小島に邑久光明園はあります。それを囲む海は、かつてハンセン病患者を隔離するのに適した環境としての海でした。隔離のための「海」だったということです。その海に、今年も子どもたちのうれしそうな声が響き渡りました。隔離のためではなく、福島の子どもたちを放射能から守る場所としての「海」がそこにありました。
大きくて、豊かで、足を入れると冷たくて、ちょっと怖くて、でも楽しくて、すごくしょっぱい、本来の海とはそういうものです。でも残念ながらそんな海を、人と人とを切り離してしまうための象徴にしてしまいました。人間の都合で海をそんなものにコントロールしてしまったのです。しかし光明園の海は、今、そっと包み込むように「おかえり」と福島の子どもたちを受け入れてくれました。
入所者の方々も本当にうれしそうに、子どもたちを迎え入れてくれました。昨年に引き続いて参加された親子が6組中5組ということもあり、子どもたちが光明園に帰ってくるのを今か今かと待ってくれていました。思えばこれらの動きの始まりは、2011年3月21日東日本大震災から10日後に、神美知宏(全国ハンセン病療養所入所者協議会会長)さんから、私たち大谷派に発信された一通のメッセージでした。
「ハンセン病患者の強制隔離絶滅政策の被害者であり、帰るべき場所のない私たちではあっても、被災者への思いと共に、どのような支援ができるかを現在検討し実行に移しております。平均年齢80歳をこえる身であるゆえ、大きなことは申せませんが、これまでハンセン病問題に対してご理解をいただいてきた皆さまと共に、この苦難にぶつかっていきたいと決意しております。現在、すでに全国の療養所に呼びかけて取り組んでいることとして、被災者に送る義援金を募っております。さらに、被災者の救護所として療養所の一部を開放できないかと検討しています。この措置には、国の方針として厚生労働省も動いており、私たちもその実現を心より願っています。ハンセン病療養所が、被災者のために用いられることは、大変有意義なことであると受け止めております。2009年4月に施行された「ハンセン病問題基本法」は地域への療養所の開放を指針としており、ハンセン病問題の解決にも資することであると考えております」(一部省略)。

このメッセージこそが私たちが療養所で保養活動に取り組む原点となっています。その中の「帰るべき場所のないわたしたち」という言葉が、今あらためて大きく心に響きます。
今回の保養ツアーで初めて出てきた「ただいま」、「おかえり」という言葉があらわす関係の豊かさと、それを奪われたハンセン病回復者と同じく帰るべき場所を原発事故によって奪われた福島の方々が、今度は光明園でその関係を取り戻されたということです。光明園が、入所者の方々が、そしてそれらを取り囲む海が、子どもたちを「おかえり」と迎え、帰るべきひとつの場所となっていきました。
すべての川が海に流れ込み、ひとつとなってそこにまた新たなるいのちが生み出されるように、ハンセン病回復者の方々と福島の親子が同じ悲しみを持つものとして出会い、つながっていく、そのことでお互いが生き合うという関係が生まれていくのを私は確かに感じました。
そのはたらきに私たちももう一度帰っていくと同時に、そのことをずっと表現しつづけていきたいと思っています。
真宗大谷派宗務所発行『真宗』誌2013年11月号より