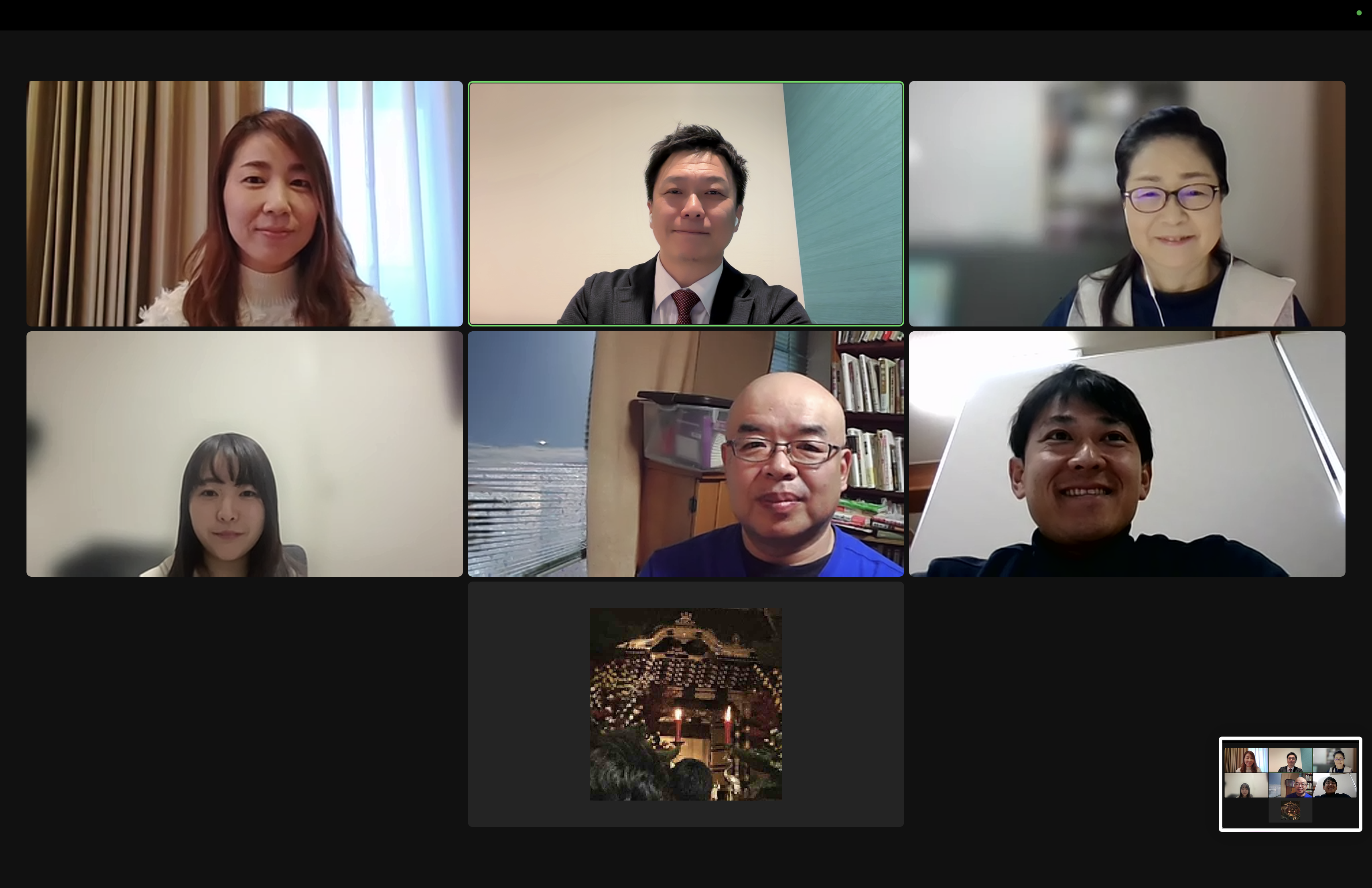<あおばの会(元ハンセン病療養所東日本退所者の会) 柴田 すい子>
らい予防法廃止二十年、ハンセン病国家賠償請求訴訟に勝利して十五年。
私は一九五一年に十四才で入院しましたが、一九六八年に退院しました。
当時は、終身強制隔離のらい予防法が生きていたし、その法律にがんじがらめに傷めつけられて、私たちは社会内では生きていけない療養所だけの生活を強いられました。退院したといっても、法律が生きていて、公には退院は認められていません。多くの人は、帰省の形での長期社会内滞在ですので、傷などができると療養所に戻らざるを得ません。私も当時、調布での生活で、二十四時間営業の薬局に、よく外科材料を買いに行きました。
健康な人と結婚して、子どもも生まれ育てた人は、病気のことは子どもや親戚に言わない人が多いです。そのため法律が廃止されても、病気を明かすことは難しいのです。
よくハンセン病にかかった人は、大きく生きられないと言います。やはり隠した部分があるとどうしても遠慮し、小さく生きることになります。職場でも自分の話はあまりせず、他者の話を聞いている時が多かったと思います。まして女性は子どもの話が多いので。でも私は、知らない世界を知ることができることに興味をもち、いつも輪の中にいることができました。
裁判によって、国がこの法律の誤りを認めてから、一般の人の知るところとなり、隠さなくても、職業を失う怖れ、アパートを追われる不安、病院に行ったら療養所に行けと言われるのではないかという恐怖感などはなくなりました。
そして、らい予防法の下で生きた経験を語り、また話を聞いてくださる人も出てきました。講演に行ったり、語り部になったり、大きく生きる人も出てきました。このことは、裁判前と後との大きな違いです。
私は、社会に出てからすぐ仕事をし、七年位はパートで近所の人と働いていました。ハンセン病のことは隠しての生活でした。
その後、東京コロニー(印刷業)に務めて定年まで二十三年間働きました。
一九七七年に、北欧に福祉を学びに十七日間、各施設長とその他の人たちに混ざって研修旅行に参加しました。「保護雇用」という、三分の一の能力があれば、三分の二は国が補填するといった制度を学びました。ハンディキャップの人たち、失業者、身体障がい者、妊婦さん等が皆さん一緒に働いていました。
ここで私は、自分は障がい者だということを自覚することができ、ハンセン病は自分の中から薄らぎました。また街の中を、腕のない若い女性がいきいきと歩いているのを見て、障がいは恥ではないと思いました。
それ以来、特別にハンセン病を隠すこともなく、またことさら言う必要もなくなりました。
二〇一一年には、社会福祉協議会の方の協力もあって、介護保険認定を受けました。
今は、週一回ヘルパーさんが来て、週十三時間の機能訓練でデイケアに通っています。年をとったらどうしても身体が弱り、医療、介護を受ける必要があります。裁判後、社会で生きることを認められても、療養所に戻った人が四十四人いらっしゃるとか。千二百名の退所者の年令は七十代から八十代です。九割の方が、ハンセン病問題にはあまり関わり合いをもたずに生活しています。そのためサポートが受けにくく、今も心の傷をひきずり、悩んでいる方もいらっしゃいます。老後の不安もかぶさり、これからも問題が山積しています。
私たち「あおばの会(元ハンセン病療養所東日本退所者の会)」は、一ヵ月半に一度のペースで、弁護士、ケースワーカーの方たちと会合をもっています。老いていく中で、心強い味方です。また私は、時々大阪の支援団体や、真宗大谷派の方たちと一緒に旅行に行きます。自然によりそってくださるので、ホッとし心暖くなります。
真宗大谷派は、らい予防法に随って国策に加担したことを謝罪してくださいました。誰も責任をとらないこの国の中で、そして長い間社会から排除されてきた私たちを受け入れ、共に行動し、それを続けていることの意義は大きいと思います。
らい予防法に傷めつけられた人生ですが、晩年はなんとか自分の足で歩けるうちは頑張りたいと思います。
地域やサポーターの支援を受けながら、そしてこの経験を若い人たちに知っていただくことも大切だと思っています。そのためには平和でなければいけません。
経済的基盤もでき、いつまでもよりそってくださる方がいて感謝です。

《ことば》
「何度も何度も、脱走した。」
療養所の交流会に参加させていただき、回復者の方々の強制隔離の当時の過酷な状況や現在の療養所内での高齢化に伴う介助・看護体制の不十分さ、療養所の統廃合への心配、また社会復帰の困難さを聞かせていただきました。その後の懇親会では飲食をともにしましたが、短い交流時間では私が聞けることはほんの僅かなものでしかありません。しかし、交流中の回復者の声音や表情に感じたのは、ハンセン病を患い、隔離の被害を受けた者として今のこの社会を生きる人間としての、柔らかさ、穏やかさ、静かさ、逞しさでした。「何度も何度も、脱走した。」回復者のこの言葉は、音楽を聞いて感動するように今でも私の耳に残っています。以前読んだ藤本和子さんの『ブルースだってただの唄─黒人女性のマニフェスト』でこんな一節があります。「あんた、ブルースなんていってもさ、ただの唄じゃないか。その言葉がずっと私の耳に残っていた」。人間のリアルな言葉はブルースがそうであるように人の心を揺り動かします。国の強制隔離政策と市民の差別・偏見の中を生き、そして人間は人間らしく生きたいというリアルな言葉に、今私が突き動かされています。
(日豊教区・来山哲治)
真宗大谷派宗務所発行『真宗』誌2016年6月号より