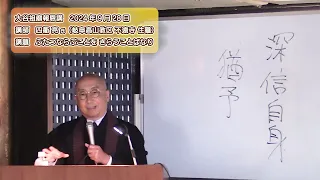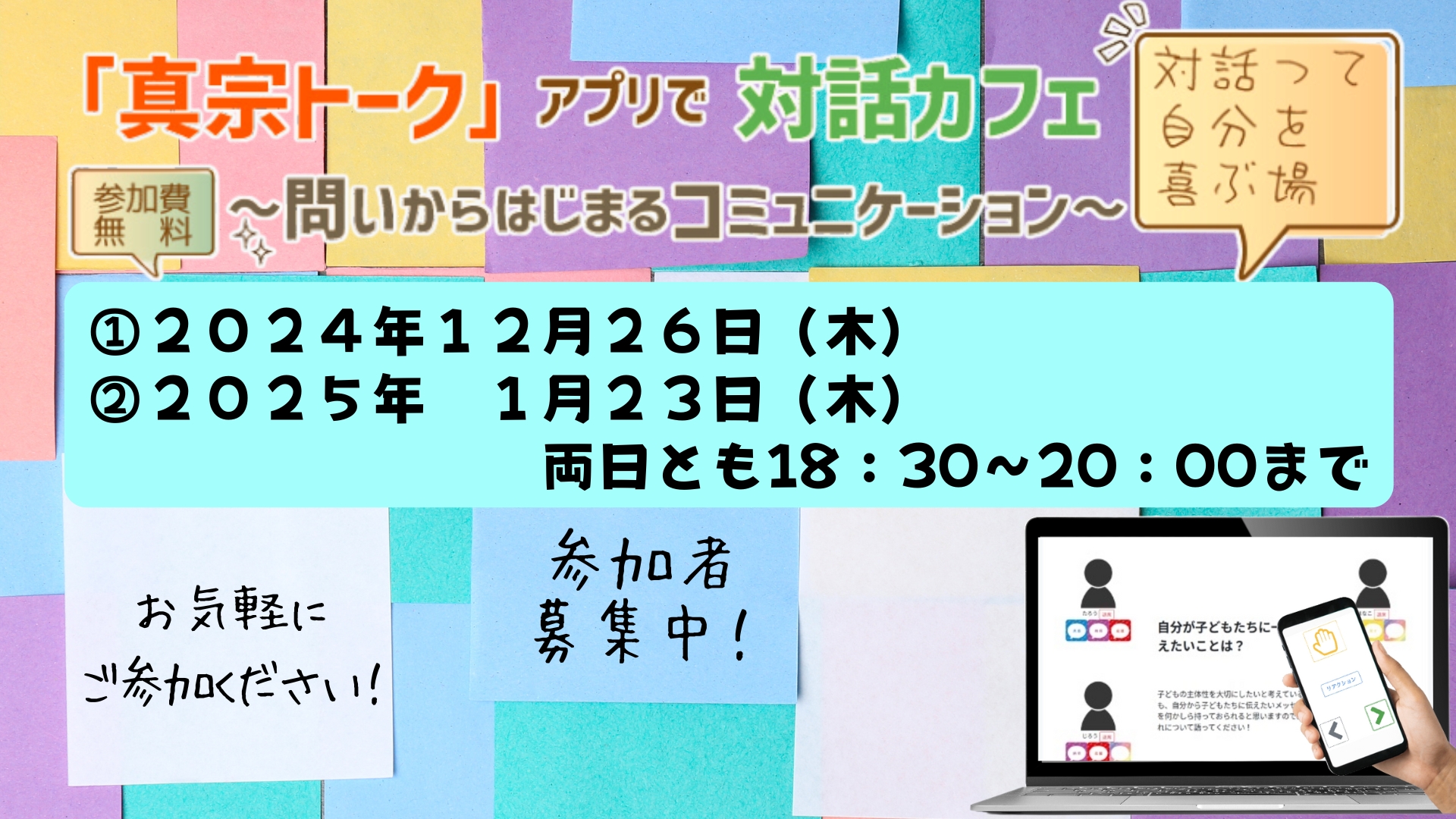─「すごい・えらい・かわいそう」のトライアングルを越えて
<カトリック相模原教会司祭 浜崎 眞実>
第十回真宗大谷派ハンセン病問題全国交流集会の講演において(本誌八月号掲載)、德田靖之弁護士の「当事者とは誰のことか。自分自身の関わりはどうなのか。自分に問うところから始まる」との言葉に呼応していくことを期して、「当事者を生きる」というテーマを設けました。六回にわたって、さまざまな立場でハンセン病問題に関わっておられる方々にご執筆いただきます。
(解放運動推進本部)
星塚敬愛園(鹿児島県鹿島市)に暮らす上野正子さんは、語り部として学校などへ出かけて、自身の体験に基づくお話をされています。園を訪ねると、そうした地域社会での実践を振り返るお話をしてくださるのですが、その際、「『かわいそうに』とか『たいへんでしたね』という反応が返ってきて、自分は同情されるために話したのではないのに…」と呟かれることがありました。
以前、原発事故で福島から相模原に避難した方の講演会に参加したことがあります。その方は各地での講演の際に、「いいお話をありがとう」との反応に違和感を抱くと言われました。原発被害にあった自分と聴衆に、ある種の断絶を感じるとのことで、「当事者とは誰のことなのか」 と問いかけられる出来事でした。
当事者と支援者とは対の関係で見られるようです。当事者が声をあげて問題を指摘し、それに支援者が対応し、声が小さいならもっとはっきり大きくと促し、困っているなら同情して助けてあげるのが支援者のイメージです。そこでは、まず活動自体が「すごい」とほめられ、次に支援者と呼ばれる人に視線が向けられ、「えらい」と称賛されます。また援助を受けている人に対しては「かわいそう」との同情から、場合によってはお金や物資の寄付が支援者に届くというパターンがあります。
私は学生の頃、神山復生病院を毎年訪問していました。そこでは救済する側、すなわち「困っている病者」に尽くす人の側に目が向き、その人たちに感動して模範としていました。まさに「すごい・えらい・かわいそう」のトライアングルの世界に浸っていたのです。
らい予防法廃止直後、カトリック教会は療養所で「らい予防法廃止感謝ミサ」を実施しましたが、その後提訴されたハンセン病国家賠償訴訟(以下、国賠訴訟)には沈黙し傍観していました。
第一回公判のあと、星塚敬愛園を訪ね、そこで原告として立ち上がった人たちからの「裁判が終わってから感謝ミサをするのではなく、裁判中から一緒に歩んでほしい」との発言に遇いました。療養所では、「予防法廃止で感謝なんかできない」との声も聞こえてきました。
星塚敬愛園の玉城しげさんは、国賠訴訟係争中に報告集会で「私は、『あなたたちをみなしごにはしない』(ヨハネ福音書14章18節)というイエスさまのみことばが支えです」と語ったことがあります。その発言に接して、聖書が単なる古典ではなく、今も人をいかす神のはたらきとして迫ってきました。しげさんが語った聖書の箇所を、私はそれまでは、すべての人に漠然と向けられた呼びかけとして抽象的に受け止めていたのですが、それが崩れました。同じことばでも、立ち位置によって違って聞こえてきたからです。私にはしげさんを通して、裁判などへ身を運び、原告の人たちの話しを聞くようにと促すことばになりました。これが「すごい・えらい・かわいそう」のトライアングルの世界を脱け出るきっかけでした。
その後、原告の方々から話をお聞きし、いろいろと関わるようになると、知らないことやそれまでの常識にはおさまらないことが次々とでてきました。
ハンセン病問題で問われていることは、病気と名づけられると、隔離され社会から排除されるという仕組みです。その社会構造は私たちと関係があります。
この被害をあたかも自然災害のように、自身の加害という立場を問われない問題として支援活動を続けると、「いい人」にはなれます。自分との関係は問われないからです。しかし、ハンセン病問題は自然災害ではありません。その苦しみは、病気に感染し発病したことだけではないことを、大谷派の謝罪声明では「病そのものとは別の、もう一つの苦しみ」と、問題の本質を的確に指摘されています。そのような中で、自分の立場は加害者であり、その加害責任をどう果たすのかということに関心が移っていきました。聖書との向き合い方も、いつでも誰にでも通じる客観的で中立な読み方はないことを自覚するようになりました。
加害責任の自覚のない善行、すなわち善意と正しさに基づいた慈善活動は、容易に思考停止に陥り、人権侵害に至ることさえあるというのがハンセン病問題から学んだことです。
また国の隔離政策を率先して遂行し、断種や堕胎などに直接に手をかして「人生被害」とも言われる究極の人権侵害をもたらしたのが、極悪非道な悪人であったのならわかりやすいのです。しかし、そうではなく、他者に尽くそうという崇高な志をもった者の実践が未曾有の被害をもたらしたというのがハンセン病問題の核心です。
そして、背景にあるのが「救らい思想」です。その根底には疑いのない善意と、自らの立ち位置は変えずに、視線を移すということがあります。救済する側とされる側に立場を固定化して、救済する側はハンティングでもするかのように、困っていると見える人を探し出して援助するのです。それに対してナザレのイエスが提唱したのは、自らの視点(視座)を、他者の痛みを共感できるところに移し、そこから社会の仕組みを見て行動を起こすことです。「視線を移す」ことと「視点を移す」ことは似て非なるものです。その意味で、当事者と「なる」ということは「救らい思想」の克服を目指すことでもあります。

《ことば》
「長い年月、私たちは社会の中で生きてはならない者だった」
柴田すい子(あおばの会・東日本退所者の会)
この言葉を第十回真宗大谷派ハンセン病問題全国交流集会の最後のリレー感話で聞きました。柴田さんは、ハンセン病を発症されてからの日々をこう表現されたのです。
私たちが生き、作っているこの社会は、ある病になった方々の生存、存在を認めてこなかった。私自身はこの社会を課題としているでしょうか?
フランスの作家ボーヴォワールは「私は人間を理解することがとても下手で、すぐ人間を判断してしまう」という言葉を残していますが、この言葉は、この社会を課題にしていくための歩みでは何を大事にしなければならないかを教えてくれているように思います。
「人間を判断する」とは、人間にレッテルを貼り、ひとくくりにする在り方。「人間を理解する」とは、一人ひとりと丁寧に出会い、息づかいや体温を感じながら、その人の苦しみを聴聞する在り方。我々は一人ひとりの苦しみの声を通してでしか、本当にこの社会を課題にすることなどできないと思います。私は、「人間を理解する」ための歩みのことを「交流」というのだと、ご縁のある多くの方々から教えられました。
(京都教区・谷 大輔)
真宗大谷派宗務所発行『真宗』誌2016年12月号より