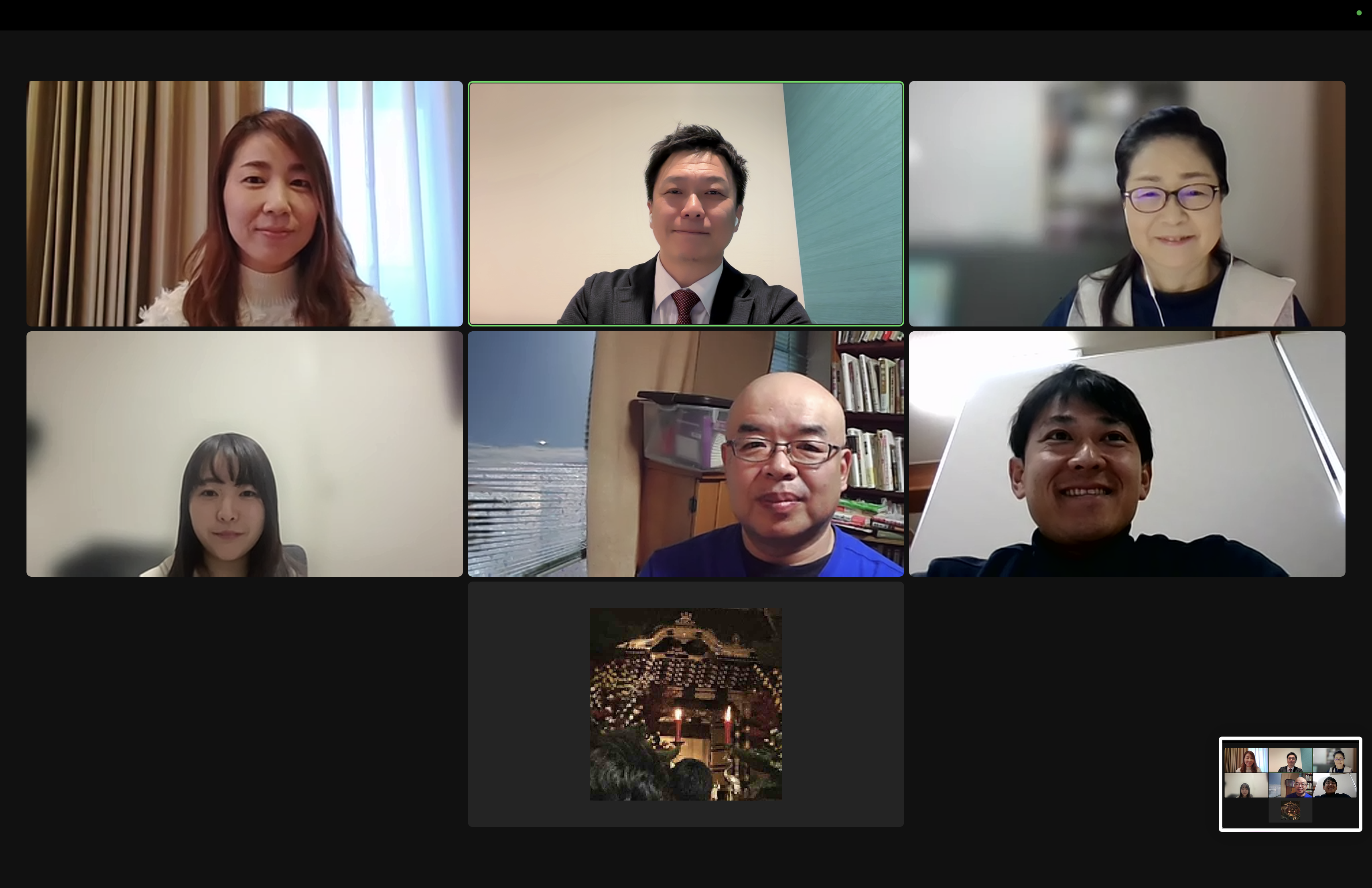知っている人は、もう誰もいないから
─次世代にバトンを渡す─
<社団法人ヒューマンライツふくおか代表理事 古長 美知子>
第十回真宗大谷派ハンセン病問題全国交流集会での德田靖之弁護士の問いかけを受けた「当事者を生きる」というテーマのもと、さまざまな立場でハンセン病問題に関わっておられる方々にご執筆いただいています。
(解放運動推進本部)
やわらかな薄紅の肌、抱きしめると寄せるぬくもり。吾子を抱くことを許されなかった人の悲しみは計り知れず、はどれほどのものだろうか。別れの言葉を呼びかける父に、応えることのできなかった少年の悔いは、老成した今も心の深い傷となり、やがて訪れる命の終焉まで続くに違いない。父がそうである。
祖父がハンセン病を患い、国立療養所星塚敬愛園(鹿児島県鹿屋市)で生涯を終えたと知ったのは、一九七四年発行『解放を問われつづけて』(林力著・明治図書出版)の父の文章だった。当時、父は福岡で教員をしていて部落差別から学び、同和教育運動を牽引していた。読むように勧める訳でもなく、黙って本を机に置いた。
時が経ち、その一文を目にした時、幼い頃の記憶が走馬灯のようによみがえり、家族に起こった出来事の意味がしだいに明らかになっていった。一九六二年、私が六歳の時、祖父の山中五郎は念願の寺の建立を発起し、真宗同愛会の方々と共に星塚寺院を落慶した五年後、庫裏の廊下に倒れ、脳内出血で他界している。
その夜、父はいつもの出張のような準備をして、夜行列車に乗るために家を出ようとしていた。玄関に見送る祖母、母、私。祖母が小さな声で「力、頼むね」と呟いた。それは、祖父危篤の電報で敬愛園に向かう父に託された言葉だった。他にも幾つかの場面が思い起こされ、私は家族の苦悩を思い、少し涙した。あの時ほど家族を愛おしく感じたことはない。生まれて初めてではなかっただろうか。
あの日から二十年の空白を埋めるように敬愛園を訪ねるようになったのは、祖父の形見の鐘を大切にしてくださっている上野政行さんとの出会いである。引き寄せられるように星塚寺院にお参りし、壁にかかった祖父の肖像画(死刑囚の西武雄氏による※)に語りかける。「来たよ」、「またね」、上野さんとの話は夜半まで尽きることなく続く。
病の苦しみに追い打ちをかける「癩予防法」。地域社会からはじき出され離散する家族。名を変え、転々と居を変え、息を潜めて生きる。自らの肉親を封印しながら生きていかざるを得ない歴史の現実に耳を澄ます。それは、祖母や父に降りかかった苦難そのものだった。
「知っている人は、もう誰もいないから、帰ってきてもいいよ」と。
元患者が、ハンセン病を“恥ずかしいこと”だと思っているとの前提に立ち、村人も世代交代し、家から患者がでて収容された事を知っている人は皆、亡くなった。周囲の目を気にすることのない環境が整い、な偏見、差別にあうことはもうないだろうから、帰ってきていいと言っている。同時に、里帰りを受け入れる家族も、嫌な目にあうことはないということだ。この言葉に含まれる問題の根深さを知る人は、果たしてどれほどいるだろうか。
入所して七十四年。母親の危篤の見舞いに闇に紛れて帰った四十年前以来、懇願の里帰りに臨んだ時、親族から発されたこの言葉は、当人を傷付けただけではなく、当事者家族の置かれた長い苦しみと地域社会の差別性を浮き彫りにしている。
患者が収容された後、残った家族に降りかかる差別被害の形は様々で、一様に苦しく厳しいものである。中でも哀しいのは親が子を捨て、子が親を疎み、「死んでくれればいい」とさえ思う“断絶の苦しみ被害”ではないかと思う。被害の背景にあるのは社会の排除意識である。
十五年前のハンセン病国家賠償訴訟・熊本地裁判決以降、課題解決にむけ専門家の検証や差別解消の取り組みは続けられている。しかし、誹謗中傷の言葉を発せずとも、触らぬ神にたたり無しとばかり、目をそらして来た社会の一員である“わたしやあなた”は、何を振り返ったのだろうか。
二〇一六年春、ハンセン病家族訴訟が始まった。原告五六八名のうち実名で提訴した者は三名だという。声を上げれば、社会の中で生き辛さを伴うのだから、名のりをう家族が大勢いる。差別、偏見は今も生き続けている。九十年に及ぶ隔離政策がした人間の尊厳を踏みにじる過ちを、知っている人は本当に少ない。
近い将来この過ちは風化するのではないだろうか。いや決してそうあってはならない。
大半の方が亡くなり、現役で描きつづけているのは一人となった菊池恵楓園絵画クラブ金陽会に、八百五十点を超す絵画が残されている。入所者が死亡し、引き取り手が無い遺品は焼却されるが、絵画は仲間に託される形で残った。今、私は、ハンセン病の歴史の過ちの中に身を置いた人たちの絵画を、多くの人に知って欲しいと思い保存に取り組んでいる。絵を見ることから、ハンセン病を生き抜いた人たちに近づくことができるのではないかと思うからだ。言い難い苦しみ哀しみの底にあっても、日常に歓びを見出す姿が尊い、生きるために描かれた「いのちのあかし」である。
ハンセン病から学び、そこに生きた人々の姿を次世代に伝えていくことは、今を生きる私の責任だろう。上手くバトンを渡さなければならない。当事者家族でありながら一切の偏見、差別にあうことなく生きてきた私はそう思っている。
※西武雄氏─福岡事件の元死刑囚、冤罪を訴え
「叫びたし 寒満月の 割れるほど」の句を残す。
 星塚敬愛園真宗同愛会のみなさんと
星塚敬愛園真宗同愛会のみなさんと

《ことば》
迎える立場から 出ていく立場、行く立場になった
鈴木幹雄
「らい予防法」廃止後に始まり十回を数えた真宗大谷派ハンセン病問題全国交流集会は、各地でそれぞれの願いが表現されてきました。その間にも、療養所内外に住まいする方々も、そして環境も変化の一途をたどっています。園の友人から「人が減り、鹿やたぬきが出るけものの島になりそうです」とのお便りが届きました。若い時のようには動けなくなったと。それでもなお「蝉は暑さにも負けず生きよ生きよと鳴き続けております‥、共生共死」と。怠惰を貪る私に、目を見開け!と叱咤の声に響きました。
鈴木幹雄さんのこの言葉も、それに先立ち、私自身が発露せねばならない言葉であったと痛感いたしました。交流集会を始めた当初、園に住まいされている方から「京都に参集せよとはどういうことだ。あなた方が園に来るのが筋ではないか」と、怒りにも近いお叱りを受けたことがあり、その言葉を思い起こしました。高齢により、外出もままならなくなった今、「ここに私はいるよ」の声を、私は心底に留めねばならないと、この言葉から聞きとりました。
(東京教区・旦保立子)
真宗大谷派宗務所発行『真宗』誌2017年1月号より