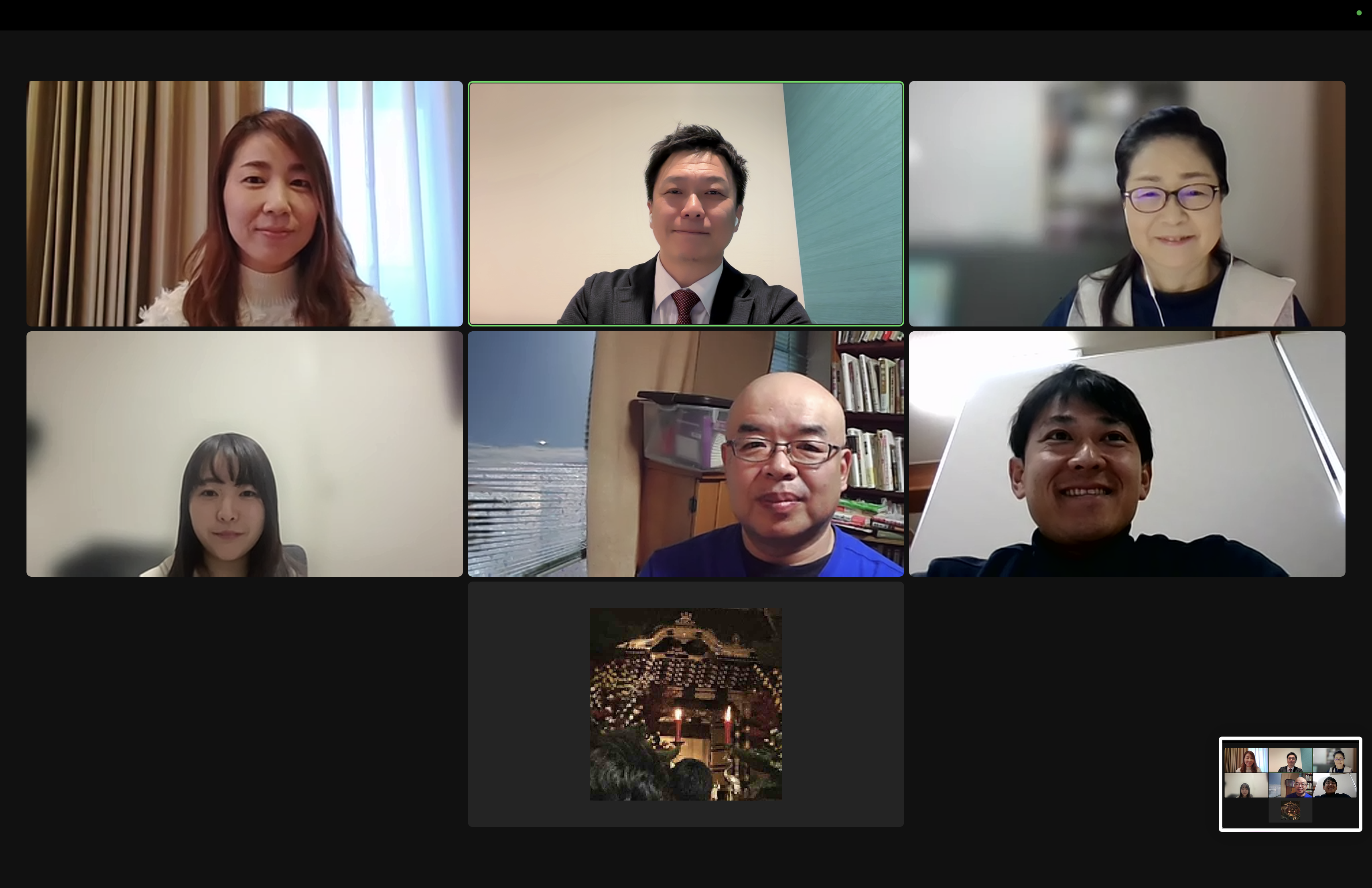ハンセン病家族提訴
─問われる市民一人ひとりの責任
<ハンセン病家族訴訟原告団副団長 黄 光男>
第十回真宗大谷派ハンセン病問題全国交流集会での德田靖之弁護士の問いかけを受けた「当事者を生きる」というテーマのもと、二〇一六年十二月号から六回にわたって、さまざまな立場でハンセン病問題に関わっておられる方々にご執筆いただいています。
(解放運動推進本部)
ハンセン病家族訴訟は、二〇一六年二月一次提訴で五十九名、三月の二次提訴では五〇九名の原告、合わせて五六八名が提訴した。この時期に提訴に踏み切ったのは、「らい予防法」が廃止された一九九六年から二〇一六年三月末をもって除斥期間である二十年が過ぎ、裁判に訴える効力がなくなるからだ。しかし、二十年が過ぎたからといってその被害は帳消しにはならない。二〇〇一年の国賠訴訟熊本地裁判決では、療養所に入所した元患者たちに対する被害が認められただけであった。今回の裁判の意義は、家族の被害を明らかにすることだ。
私の家族六人は大阪府吹田市で貧しいながらも仲睦まじく暮らしていた。私が生まれた一九五五年頃に母はハンセン病と診断され、大阪府の職員に執拗に入所勧奨を受けていた。しかし、母は、二人の姉と兄(その後死亡)と私の四人の子どもの育児を理由に入所を拒否していた。当時の患者台帳にはその時の様子が記されている。「強硬に勧奨せるも子どものことを言い立て聞き入れず」「訪問入所勧奨するも入所の意思ないものと考えられる」と、母は入所を拒んでいた。しかし、しばらくして突然入所を承諾したのだ。母がハンセン病であるということで、近所の銭湯に入浴を拒否された事件があったという。これで入所を決意し、母と下の姉は長島愛生園へ入所した。父と上の姉は吹田市に残ったが、一歳の私は岡山市内の育児院へ預けられることになった。岡山駅での別れの時、母は「光男は離さん!」と言って、狂うように泣き叫んだという。翌年には父と上の姉もハンセン病と診断され、愛生園へ入所した。そんな家族のことを何も知らないで、私は育児院でのびのびと育ったのである。
私が九歳の時、両親は社会復帰し、私も含めて家族五人が尼崎市で暮らすことになった。私にとっては、初めて出会った両親と姉たちだった。母はいつも薬を飲んでいたので、ある日部屋で母親と二人きりになった時、私は母に「何の病気?」と聞いた。すると母は、二人きりで誰にも聞かれるはずがないのに声をひそめて「らい病」と言った。これが私とハンセン病の出会いだった。なぜ声をひそめるのか。これを敏感に感じた九歳の私は、「この病気は誰にも言ってはいけない」と心に固く決めてしまった。小学、中学そして高校生活でもこの病気のことは語らなかった。高校卒業後、尼崎市役所に就職した以降もこの姿勢は変わらなかった。
一九八二年、同じ在日同胞と結婚した。しかし彼女にもこのことが言えなかった。子どもが生まれた結婚三年目の夜、家で晩酌をしていると妻が突然私を追及した。孫が生まれ毎週土日に私の実家に一泊し、家族そろって晩ごはんを食べるという幸せな生活を送っているはずなのに、母が妻に「長生きしてもしゃあない」「生きててもしゃあない」と愚痴を言うので、その理由を私に問いただしてきたのだ。家族四人がハンセン病で長島愛生園へ入所していたことを全部話すと、妻は突然の話でびっくりしたものの、それで母の気持ちが理解できたという。妻の嬉しい反応だった。
今も残るハンセン病問題を象徴するのが、全国の療養所内にある納骨堂だろう。死んでもなお、ふるさとの墓に入ることができず、納骨堂にお骨が安置されている。家族が遺骨を引き取らないためだ。国が進めた「無らい県運動」によって、患者、そしてその家族も地域社会から壮絶な差別を受けてきた。今も家族は差別を恐れて遺骨の引き取りを拒否せざるを得ず、また、本人も家族に迷惑をかけたくないとの思いから無理は言わない。結果、今も家族と本人が断絶されたままなのだ。
今回の家族の裁判では、家族の被害の全容を明らかにしたい。国は「らい予防法」という法律をもとに強制隔離政策を進めてきたが、隔離政策の責任は実は市民一人ひとりにもある。自治体の職員や市民が一体となった「無らい県運動」によって、患者と家族を社会から追いやった。十六年前、ハンセン病国家賠償訴訟において熊本地裁判決で国の過ちが認められ国は謝罪したが、一般市民、県や市の職員の中に、国と同様に謝罪し責任を感じた人が何人いただろうか。市民一人ひとりの加害責任を問うのが、この裁判の意義である。自分にも加害責任があったかもしれないということが問われる裁判になるのではないだろうか。
そしてこの裁判を通して、家族と元患者の断絶した関係が修復され、堂々と故郷を訪れ家族とふれあえるようにしたい。もし亡くなったとしても遺骨がふるさとに帰れるようになることが、この裁判の意義であると考える。そのためには、この裁判に勝って国の謝罪の言葉を聞き、「もう故郷にあなたを差別する人はいない、帰って来ていいんだよ。故郷の人たちや家族はあなたが帰るのを待っているよ」と宣言したい。
 熊本地裁に向かう原告団と弁護団。
熊本地裁に向かう原告団と弁護団。
前列右から三人目が黄光男さん、その右隣には原告団長の林力さん(2016年2月15日)

《ことば》
「自分の誕生日を忘れても、療養所に入所した日は忘れない」。
これは、多磨全生園のご門徒の集まり、真宗報恩会を訪ねた際にお聞きした言葉です。一人の言葉ではありません。参加されていた四人全員が口を揃え、そう言われ、私は言葉を失いました。
療養所に入所したその日、家族から引き離され、故郷を追われ、そして大切な自分の名前が奪われました。以来、その時の言いようのない苦しみや悲しみは、入所者にとって今もなお鮮烈な記憶として焼きついておられます。
療養所の方々お一人おひとりには、それぞれの「入所した日」があります。同時にそれは私たちが一人の人間を「隔離した日」でもあるのです。どんな思いで入所し、家族と別れたのか。その後、どんな人生を歩んでこられたのか。今、何を思っておられるのか。私は、涙を流しながらも、ひたむきに生きてこられた一人ひとりの人生と真正面から向き合い続けるとともに、私たちが一人の人間を隔離し排除した過ちを決して忘れてはならないと思っています。
(「ハンセン懇」広報部会・稲葉亮道)
真宗大谷派宗務所発行『真宗』誌2017年2月号より