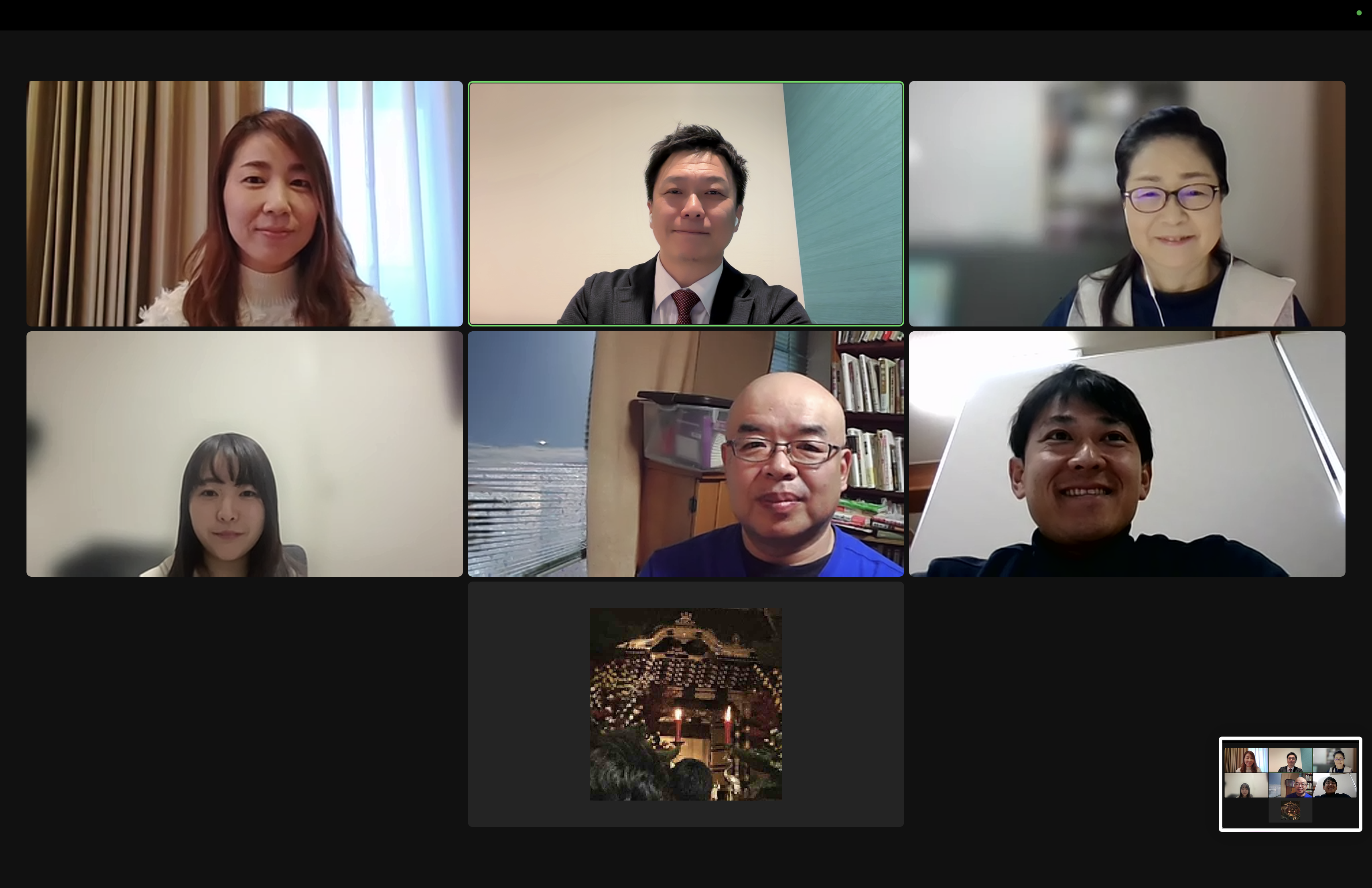二つの「緊急事態宣言」の狭間で
(御手洗 隆明 教学研究所研究員)
世界的疫災 本年四月二十二日現在、日本には二つの「緊急事態宣言」が存在する。
一つは、二〇一一年三月十一日十四時四十六分に発災した東日本大震災における、原子力災害対策特別措置法に基づく「原子力緊急事態宣言」である。これは東京電力福島第一原子力発電所の被災を受けて、同日十九時三分に出された。もう一つは、本年四月七日に新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)の急拡大を受けて出された、新型コロナ特措法に基づく「緊急事態宣言」である。
今、日本という国は原発災害と近年の相次ぐ自然災害に加え、新型コロナという世界的な疫災に見舞われている。急激な患者数の増加により、「医療崩壊」が現実になりつつある。
本年一月以降、顕著になった新型コロナの感染拡大により、教学研究所の「震災と原発」問題研究班が二〇一三年より続ける仙台教区(岩手・宮城・福島)被災地域への訪問は中止となった。現地でも、震災の日に東北別院などで勤められていた「3・11 東日本大震災追弔法要「勿忘の鐘」」は、一般に参加を呼びかけない「内勤め」となり、国や行政主催の行事も次々と中止や延期、また規模縮小となった。それでも九回目の震災の日は巡ってくる。
九回目の震災の日 東日本大震災による犠牲者は、全国で死者一万五八九九人、行方不明者二五二九人、震災関連死者三七〇一人を数え、現在も四万七七三七人が各地で避難生活を続けている(読売新聞、本年三月十二日)。昨年より死者は二人増え、行方不明者は四人減り、関連死者は三十六人増え、避難者は四〇四一人減った。この避難者数の減少は、本年七月開催予定であった「東京オリンピック・パラリンピック」に向けたJR常磐線の復旧のため、福島県双葉郡に残る帰還困難区域が解除された影響もある。避難指示が解除された地域からの避難民を、国は避難者とみなさないからだ。
九年前の原子力緊急事態宣言では「放射能が現に施設の外に漏れている状態ではありません」と繰り返し注記されている。しかし、発令翌日の十五時三十六分に原発は爆発事故を起こした。あの日に強制避難の対象となり、二〇一四年四月以降に避難指示が解除された福島県十市町村に住民票を置く四万六五二九人のうち、実際に居住する住民は二八・五%という(京都新聞、本年三月七日)。これには転入してきた原発や復興事業の関係者も含まれるため、実際に帰還した住民はさらに少ないという。
仙台教区浜組の正福寺がある双葉郡双葉町は全域が強制避難の対象となり、この三月に一部地域の避難指示が解除されたが、帰還を希望する住民は一割程度という(同、本年三月四日)。双葉郡の大谷派寺院は、浪江正西寺がある浪江町、西願寺がある富岡町も同様に厳しい情況にある。住民にとって、九年という歳月は長すぎたのだ。
大谷派原町別院のある南相馬市の居住率は五一・九%というが、これには復興事業関係者に加え、浪江町や相馬郡飯舘村から避難し、復興住宅などに住む住民も含まれる。今年の南相馬市主催の震災追悼式も規模を縮小して行われた。毎年、震災関係の企画がある南相馬市立中央図書館では「光のモニュメント写真展」が開催され、浜通り各地の施設や神社仏閣をライトアップした光景が展示されていた。
勿忘の鐘 あの日から二〇一六年七月まで、原町別院から三キロ南には、原発災害のため住むことが許されない地域が広がっていた。境内には現地復興支援センターの福島事務所があり、本堂は浜組や被災寺院の会所になるなど、原発最前線地の寺院としての役割を担い続けた。
この原町別院でも震災追悼会は内勤めとして営まれた。この頃、東北地方に新型コロナの大きな人的被害は見えていなかったが、参集した別院門徒には手製のマスクが配られ、間を空けて着座するなど感染防止の対策が取られていた。縮小した法要であったが、「全国に鳴り亘る勿忘の鐘の響きが、十方に谺する微妙の音となり、浄土往生の願いを共にせん」と誓う「表白」が今年も読み上げられた。
短い勤行と法話の後、大震災発生を告げるサイレンと同時に「勿忘の鐘」を、今年は一人三回衝き鳴らした。昨年九月以降に相次いだ大水害からの復旧も終わらないまま、新型コロナという疫災の気配を感じながらではあったが、今年も東北各地で「勿忘の鐘」が鳴り響いた。
世界中が当事者 最初に戻るが、現在日本には二つの緊急事態宣言が発令されている。浜通りの人々は九年前の宣言のもとで、放射能という分かりにくい物質に苦しみながら、向き合いながら暮らしてきた。「先が見えない」ということも聞かされ、その時その時を「普通」に、復興を模索しながら生きる様子もうかがった。
原発事故が放出した放射性物質は、元々自然界には存在しない物質で、人間が造りだしたものである。新型コロナは、一説に元々野生動物と自然界で共存していた所に人間が入り込み、世界中に拡散させる結果となったものという。放射能が徐々にでも減少していることは線量計の数値で知ることができる。しかし、新型コロナは感染した人間によって動き、もはや国も自治体も感染経路を把握できず、その拡大はとどまるところを知らない。
震災と原発災害では被災者と支援者という関係があったが、新型コロナの疫災は、世界中が被災当事者であり、いつ私が感染するのか、それ以上に自分が地域の感染源になるかもしれないという恐怖が広まっている。「死」が、誰の目にも身近なものになったのだ。
「共存」を目指す 放射能と新型コロナは、今の科学力では容易に克服できないという点で似ている。震災の日、長崎大学熱帯医学研究所の山本太郎教授による「感染症と社会 目指すべきは「共存」」(朝日新聞、本年三月十一日)を得た。山本教授は「感染症については撲滅よりも『共生』『共存』を目指す方が望ましい」という。病原体にとって感染した宿主である人間を殺すのは自らの死を意味するので、潜伏期間が長期化し、弱毒化する傾向があるという。医師として患者を救うことが最優先なのだが、今は徹底した感染防止策をとり、感染の速度を遅くし、「人類が集団としての免疫を獲得する」ことを目指すべきと述べる。そして、新型コロナはそれ自体の被害よりも、感染拡大という情報自体が社会や生活へ与える影響を危惧する。
山本教授の知見により、抗生物質など近代医学が存在しなかった時代の人間が、疫災を生き抜いてきたことを想うと、ウイルスとの「共存」という道もあるのかもしれない。すると今は、人間が免疫を獲得するまで、あるいは「共存」が可能になるまで、どれだけの時間が必要なのか分からないが、感染を避けるための用心を続ける時である。もし感染するとしても、一人一人がその日を一日でも先にのばすことで、少しでも医療現場の負担軽減に協力したい。
今、日本は二つの「法律による緊急事態宣言」の狭間にある。新型コロナの災禍がいつまで続くのか、今はまったく先が見えない。ワクチンが開発されるのかもしれないし、人間が生存する限り終わらないのかも知れない。
しかし、原発被災地の人々は、放射能に用心しながら、様々な風評を受けながら、この土地で生きてきた。そのことを想い起こせば、震災と原発事故による複合災害と、新型コロナによる疫災という違いはあっても、自分が被災者となった時の生き方はこの人たちが教えてくれている。これほど心強いことはない。
(教学研究所研究員 御手洗隆明)
(「教研だより167」『真宗』2020年6月号より)