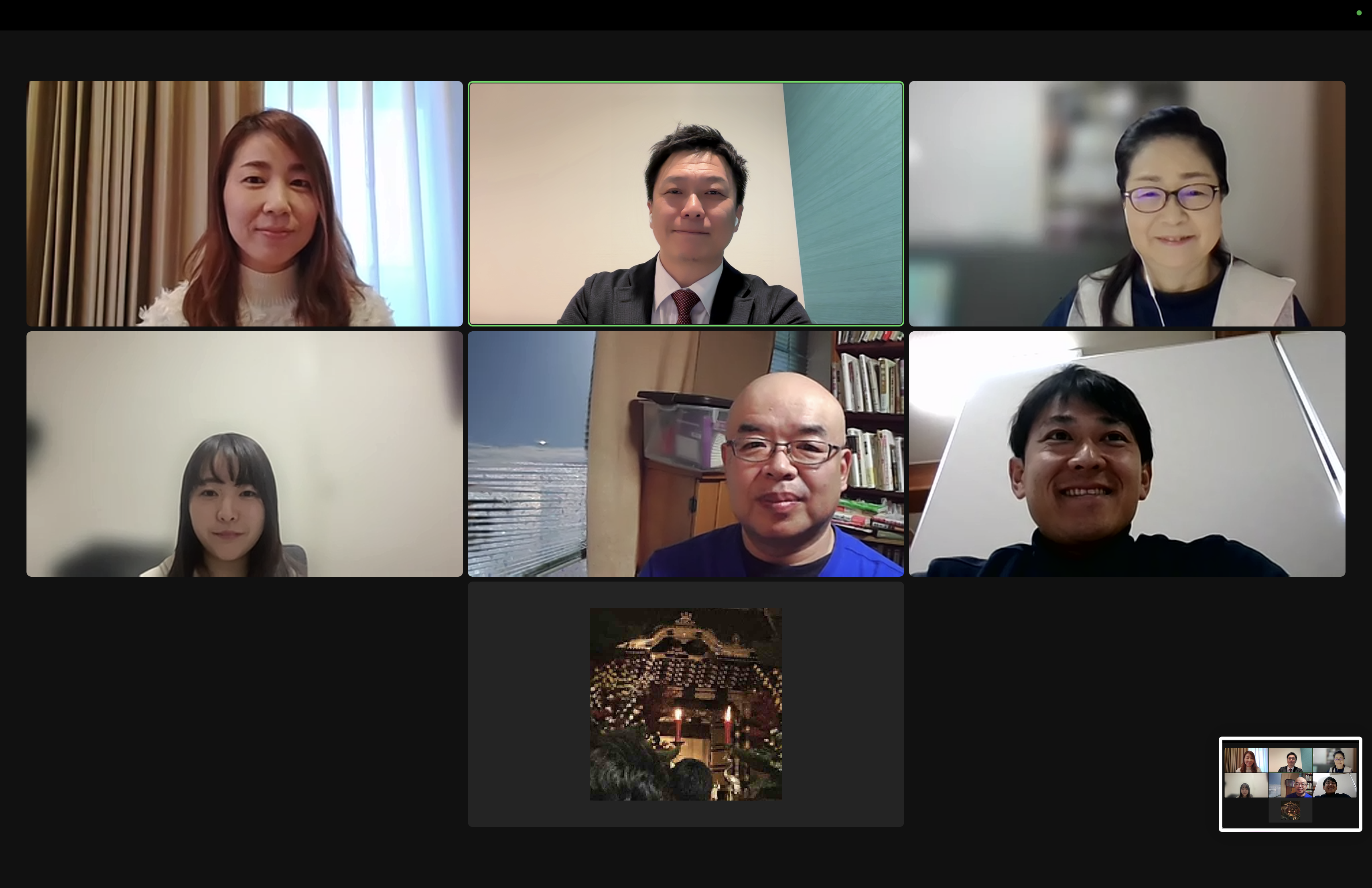かなしみにかなしみをそうるようには、ゆめゆめとぶらうべからず
(『口伝鈔』十八章 『真宗聖典』六七二頁)
宗祖親鸞の言葉は、日常生活を共にした家族によっても伝えられています。宗祖の長男・善鸞の子として誕生した如信は、六十三歳の宗祖にとって初の内孫でした。幼少より、京都で著述を続けながら門弟たちと語らう祖父・親鸞の間近で成長したようです。
如信は従兄弟たちのように寺で修行をしたり、学問に励んだりということはなかったようですが、生活のなかで祖父が語る教えを身につけ、他の宗教には関心を持たなかったと伝えられています。のちに如信は関東に向かい、父と行動を共にしますが、祖父への敬愛は変わることなく、その命日には上洛を続け、叔母・覚信尼の子で従妹の光玉を妻とするなど、京都の一族との交流は続きました。
やがて、如信は覚信尼の孫に当たる十八歳の覚如に、祖父の教えとそのすがたを物語ります。覚如は、如信が語る宗祖の「おりおりの御物語の条々」から浄土真宗の肝要を受けとめました。のちにその内容を中心に『口伝鈔』をまとめるとともに、如信を本願寺第二代に位置付け、自身も本願寺第三代を称することになります。『口伝鈔』には、宗祖が生活のなかで語った言葉が、様々なエピソードを交えながら散りばめられているのです。
近年は防ぎきれない災害が続き、疫病の流行が懸念されるなど、これまでの医学や防災では間に合わない時代になっています。大量死の時代が間近に迫っているともされています。長寿社会とも言われていますが、人間にとって死は避けようがないことに変わりはありません。また、災害からの復興が進んでも、悲しみが消えるわけではありません。
宗祖の時代は、現代よりはるかに死が身近にありました。大切な人との死別などによる喪失感や悲歎に、また悲歎に苦しむ人に、宗祖ならどのように向き合われるのでしょうか。如信はその場面に遇われ、祖父のすがたを胸に刻みつけていたのかもしれません。
『口伝鈔』十七章には死別の悲歎に苦しむ人を責める念仏聖が登場しますが、宗祖はそのような考えは自力の行者の考えであると断じます。歎き悲しみ続けることは往生のさまたげにはならない、と宗祖はお考えでした。
では、悲歎にくれている人にはどのように接したらよいのでしょうか。そのことは、次の十八章で語られています。宗祖は、
と仰せになりました。相手をますます辛い思いにさせてはならない。酒でもすすめて、少しでも笑みが浮かんだら立ち去りなさい、と仰せになったと如信は伝えます。 悲しみを無理に消そうとすると、ますます苦しくなる。悲しいのなら、心の底から悲しみつづければよい。その間、私はずっと待っている。笑みは、わずかにでも心がほどけたサインなのです。如信が記憶する宗祖のすがたには、悲歎の人と向き合い、ともにあろうとする姿勢が示されています。
(教学研究所研究員・御手洗隆明)
([教研だより(166)]『真宗2020年5月号』より)