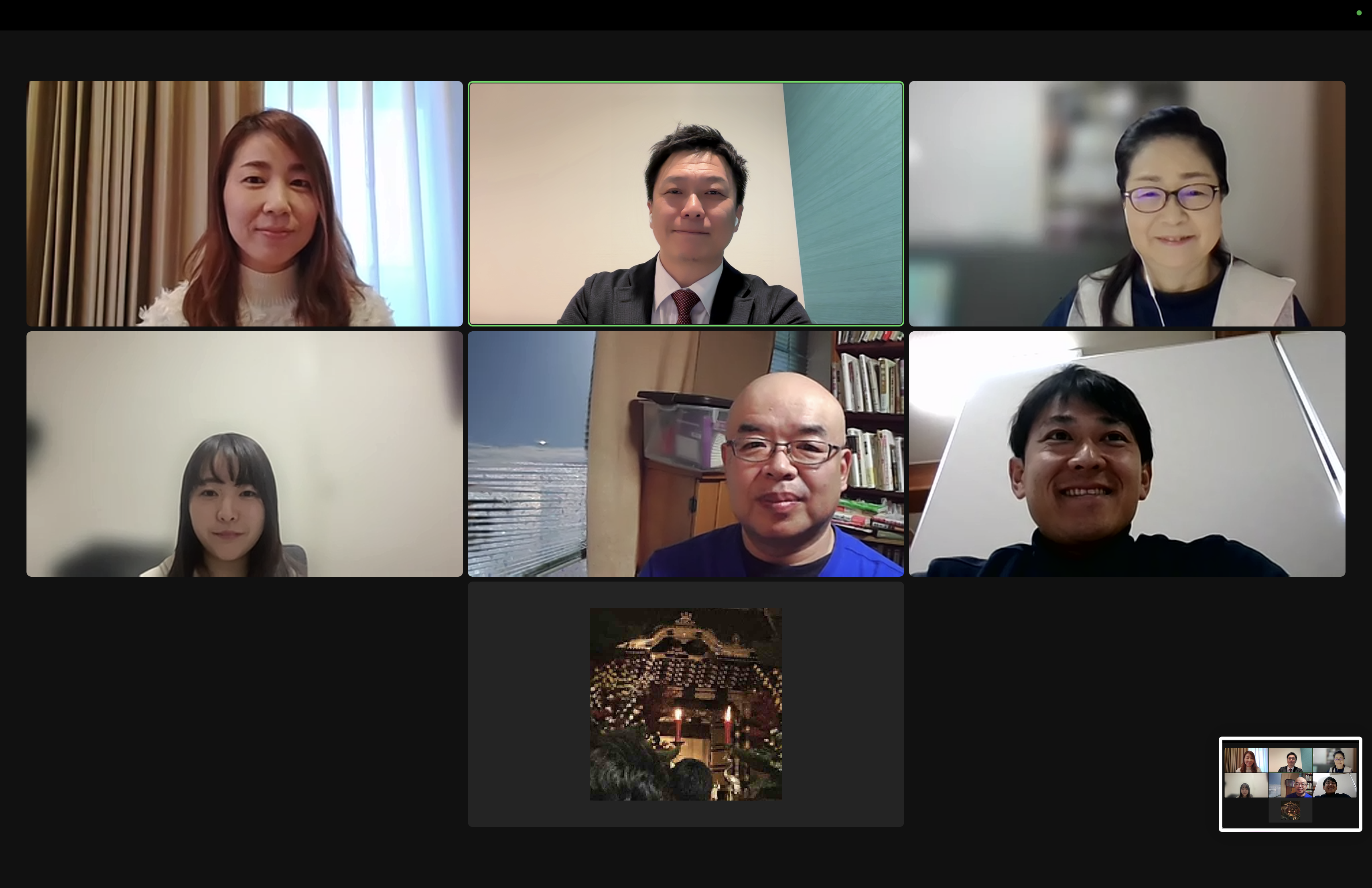日本の近代ハンセン病対策と京都大学―小笠原登の事績を中心に―
アイルランガ大学熱帯病研究所研究顧問 和泉眞蔵さん
日本の近代ハンセン病対策は、「絶対隔離絶滅政策」でした。これは全ての患者を生涯療養所に収容隔離して、死に絶えるのを待つことで千数百年続いた日本のハンセン病を最終的に解決しようとする政策でした。国はこの目標を達成するために、患者たちが一般社会で暮らせないよう「無らい県運動」を展開しました。これは日本独特の極めて残酷な国民運動で、多くの患者や家族に甚大な「人生被害」をもたらしました。また、全患者を隔離する目標を達成するために、国に協力した隔離論者たちは、ハンセン病は強烈な伝染力を持つ不治の病気だと医学的に誤った情報を流して人々の恐怖心をあおり、歴史的に形成されていた民衆の差別意識をさらに深めて偏見を強めたのです。
●小笠原登が学んだ京都大学
絶対隔離論者が国家権力と結び付いて強大な力を持っていた時代にも、それを批判した専門家がいた事実は一つの救いですが、京都大学皮膚科特別研究室(皮科特研)の小笠原登医師(以下敬称略)はその代表です。
あまり知られていないことですが、京都大学皮膚科では、創立当初からハンセン病の医療が行われており、小笠原が着任したときには、診療と研究ができる基盤がすでに固まっていました。
京大皮膚科の歴史は、1899年に京都帝国大学医科大学ができた3年後に「皮膚病学黴毒(ばいどく)学講座」として始まりましたが、当時の日本には3万人余のハンセン病患者がおり、大学病院などが扱う主要な皮膚病の一つでした。京大病院では、皮膚科第五診察室がハンセン病の診療を担当していましたが、1903年からの13年間に1,832人の新患が受診しており、皮膚科受診者の30人に1人はハンセン病患者だったのです。
京大皮膚科の二代目の教授は、感染性皮膚疾患の専門家である松本信一で、1919(大正8)年から26年間教授を勤め、ハンセン病の医療と研究の発展に尽力しました。また、小笠原登が活動した時期のほとんどは松本教授の在任期間と重なっており、松本は直属の上司として小笠原登の活動を支えたのです。
松本教授はハンセン病について二つの大きな仕事をしています。一つは、ハンセン病療養所以外で唯一入院施設を持った「皮膚科特別研究室」を作ったことです。小笠原登はここを拠点に活動しましたが、この施設は現在でも「皮膚神経外来」と名前を変えてハンセン病患者の診療を続けています。もう一つの仕事は、篤志家の寄付によって京大が開発したハンセン病の新薬である「金オルガノゾル」の臨床試験室を作り、小笠原の治療研究を支えたことです。
●医師・小笠原登の事績
1915年に27歳で京都帝国大学医科大学を卒業した小笠原は、まず薬物学教室で10年間薬学の研究をした後、1925年に皮科特研に転任し、1947年に定年退官するまで23年間、日本型絶対隔離絶滅政策に抗して外来と入院診療を続け、現在でも基本的に正しい科学的なハンセン病医学の理論を確立し、主流派の絶対隔離論者と学術論争を繰り広げました。
小笠原のハンセン病医学の基本は「体質論」です。小笠原は、患者の多くは貧しい農村の出身者で、生育期に十分な動物性食品を摂取できなかったために、細菌感染に対する免疫力が弱い「くる病性体質」になり、らい菌の感染を受けて発病すると考えました。そして、ここからが小笠原の独創性なのですが、このくる病性体質は、国民の生活が豊かになればなくなるから、日本のハンセン病は隔離などしなくても減らすことができると主張しました。
小笠原は隔離論者の主張に対し、「目下の研究は外的病因(らい菌感染)に傾き、内的素質(体質)をなおざりにして、治療もまた外的病因にばかりに偏って行き詰まっている。研究を内的素因に向けて、身体と外的な菌との相関関係を明らかにして初めて治療の要諦が確立する」と批判しました。
さらに小笠原は、ハンセン病は不治だという主張を批判して、ハンセン病は結核など他の疾病より治りやすい病気であると考えました。治るとは、身体を障害する特殊>がやむことで、発症前の状態に戻ることを意味しない。ハンセン病の場合は炎症症状が消失したら治ったと言うべきであり、菌が一つもいなくなり、再発しない確信がなければ治癒とは言えないとする、光田健輔ら絶対隔離論者の不治説を批判しました。
さらに小笠原は、自ら治療した患者を分析して、ハンセン病を強烈な伝染病とする主張は迷信であると切り捨て、迷信に基づくハンセン病対策は患者と親族を不幸にすると厳しく批判し、このような病気に断種や堕胎は必要ないと反対しました。
一方、小笠原学説には時代的制約による誤りもあります。例えば、くる病性体質になって、病原菌一般に対する抵抗力が低下した人にらい菌が感染すると発病するという学説ですが、これは誤りで、ハンセン病患者はらい菌に対してだけ抵抗力が低いのです。そのため、くる病性体質論に対する絶対隔離論者からの厳しい反論を論破する証拠を示せませんでした。
また治療についても、小笠原が臨床試験をしていた新薬「金オルガノゾル」は、当時広く使われていた大風子油を超える治療効果はありませんでしたし、漢方医学の理論に基づく「減食療法」も空腹に耐えかねた患者から受け入れられず効果もありませんでした。
1940年代に入ると、ダプソンなどによる化学療法が始まり、それ以前の治療法は過去のものとして忘れ去られ、全ての病型の患者が完治する本格的化学療法の時代になり、今日に至っています。
このような問題点があるとはいえ、ハンセン病を人体と菌との相互作用の中で見るという小笠原学説の基本理念の正しさは、その後の免疫学の進歩によってもいささかも揺らぎませんでした。
●小笠原医学の二人の後継者
小笠原のハンセン病医学の現在的意義が如実に証明されたのは、1998年から2001年まで熊本地裁で闘われた「らい予防法違憲国家賠償請求訴訟」(国賠訴訟)においてです。原告側の証人として証言台に立った4人の専門家証人の中の2人が、小笠原医学の直系の継承者だったのです。
証人の一人である大谷藤郎(ふじお)は、日本の絶対隔離政策は誤りだったと明確に証言して被告・国を追い詰めました。大谷は元厚生省医務局長で日本のハンセン病行政の中枢で絶大な影響力を持っていた人ですが、医学生の時から小笠原のハンセン病医学の精神を正しく理解していた人でした。
もう一人の専門家証人である筆者は、絶対隔離政策の時代にもたくさんの反対論があった歴史的事実を古い文献を発掘して証明し、「国はそれぞれの時代の学説に従っただけで過失はなかった」とする被告・国の主張の偽りを明らかにしました。
また、長年京大病院で診療した実体験をもとに、1996年のらい予防法廃止までは、絶対隔離政策が続いていた深刻な実態を明らかにし、戦後はらい予防法が柔軟に運用されており、絶対隔離ではなかったとする国の主張を打ち砕きました。国賠訴訟の原告勝訴は、2019年6月のハンセン病家族訴訟の原告勝訴につながり、ハンセン病問題を巡る現在の社会状態を形作っているのです。
現在日本ではハンセン病の新患発生は事実上ゼロになっていますが、これは人々の生活レベルが向上した結果であり、隔離政策の成果でないことが多くの証拠から明らかになっています。
いま私たちは小笠原登が80年前に予測した時代を生きているのです。
真宗大谷派宗務所発行『真宗』誌2020年7月号より