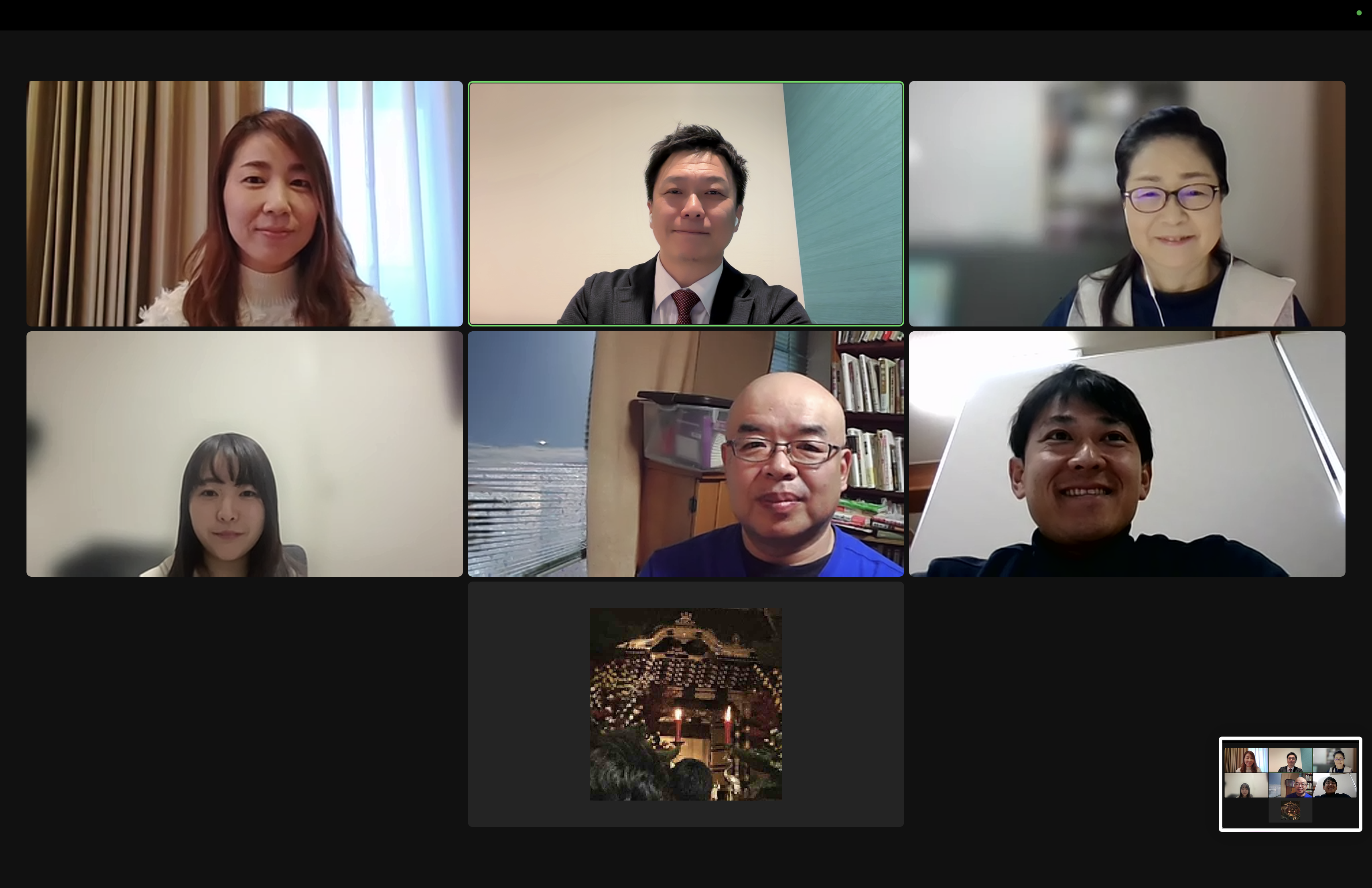「宗教者災害支援連絡会設立十周年記念シンポジウム『東日本大震災と宗教者の支援活動の新たな地平』」報告
(御手洗 隆明 教学研究所研究員)
二〇一一年三月十一日に発災した東日本大震災(三・一一)から十年が過ぎた。今年の震災の日までの犠牲者は、全国で死者一万五八九九人(昨年と同数)、行方不明者二五二六人(三人減)、震災関連死者三七七五人(十八人増)を数え、最大約四十七万人いた避難者は現在でも四万一二四一人(六四九六人減)に及ぶ(読売新聞、本年三月十二日)。また、発災の日に出された「原子力緊急事態宣言」は未だ解除されず、災害は今も続いている。
「宗教者災害支援連絡会」(宗援連)は、発災から間もない四月一日に、宗教者と宗教研究者による被災者支援の場として設立された。活動の中心となった情報交換会では、宗教者・宗教団体による救援・支援の情報共有や、記録や防災、学術や行政、地域住民との協働など、宗教を背景としながら現地で動いている人々からの多彩な支援活動の報告があった。
その成果は、二〇一六年に関係団体とまとめた「『防災と宗教』クレド(行動指針)」策定として、さらに『災害支援ハンドブック』(春秋社)として発信している。また、これまで計三十四回の情報交換会と計五回のシンポジウムを開催し、大谷派関係者も十人以上が登壇している。
本年四月一日、宗援連の設立十周年記念シンポジウム「東日本大震災と宗教者の支援活動の新たな地平」(後援・日本宗教連盟)がオンラインで開催され、七十名以上の参加があった。
はじめに、島薗進氏(宗援連代表)より挨拶として、宗教界や地域・行政が個別におこなっている支援活動や防災の動きを横につなげながら、被災者や被災地とつながっていくという、これからの本会の方向性が示され、続いて四人の登壇者からの発題があった。
戸松義晴氏(日宗連理事長・全日仏理事長)は「東日本大震災以後の日本宗教連盟の取り組み─宗教と公共性」と題した発題のなかで、「何ができたかより、何を感じ、被災者と共に何ができるかを学んだ」「遺族の悲嘆を前に、僧侶でありながら神も仏もないと正直、思った。それでも何かつながっていこうとした」と振り返った。
篠原祥哲氏(世界宗教者平和会議〈WCRP〉日本委員会事務局長)は「「つながり」が生み出す災害後の回復力:求められる「顔の見える支援」」と題し、被災者と共にいるという「寄り添い型サポート」は宗教者だから可能な支援であり、それを実践したのが宗援連の十年ではないかと述べた。
千葉望氏(ノンフィクションライター)は「コロナ流行下で迎えた陸前高田の震災十年」と題し、津波被災で避難所となり、のちに「親鸞教室」の会場となった実家・気仙組正德寺(陸前高田市)を通して、苦しい時にこそ「本気の法話」を求め、教えへの理解を深めていった門徒のすがたを語った。そこには、大災害で受けた悲嘆の塊を、聞法によって一つ一つ鑿で削るようにして自分で受け入れ、回復に向かう心の動きがあったという。
そして今、震災でも途絶えることのなかった「お講」や葬儀など「喪の儀式」、また「仏さまからのはたらきかけ」として勤めてきた法事などがコロナによる災害で継承の危機にあるという。それでも「今」になってあぶりだされる被災者の悲嘆や思いと向き合い、心の回復を助ける、息の長い支援の場としての役割が寺院にあると語った。
山尾研一氏(キリスト全国災害ネット世話人、クラッシュジャパン副代表理事・事務局長)は「東日本大震災後のキリスト者の災害支援について」と題し、この十年とコロナ下での支援活動を通して、これからの課題とし挑戦する「支援のかたち」が述べられ、また大震災を神の問いかけと受けとめた若い信仰者のエピソードなどが語られた。
四人の発題には、この十年間に培われた被災当時から今に至る支援のかたちがあり、住民や行政と平時から信頼関係を築くことの大切さがあった。
宗教者にしかできない支援があるとすれば、耐えがたい悲嘆と喪失による心の隙間に闇が入り込まないよう、人々の心を真実なる教えの世界に導くこと。これ以外にはないことを、この場であらためて想い起こした。
(教学研究所研究員・御手洗隆明)
([教研だより(179)]『真宗』2021年6月号より)