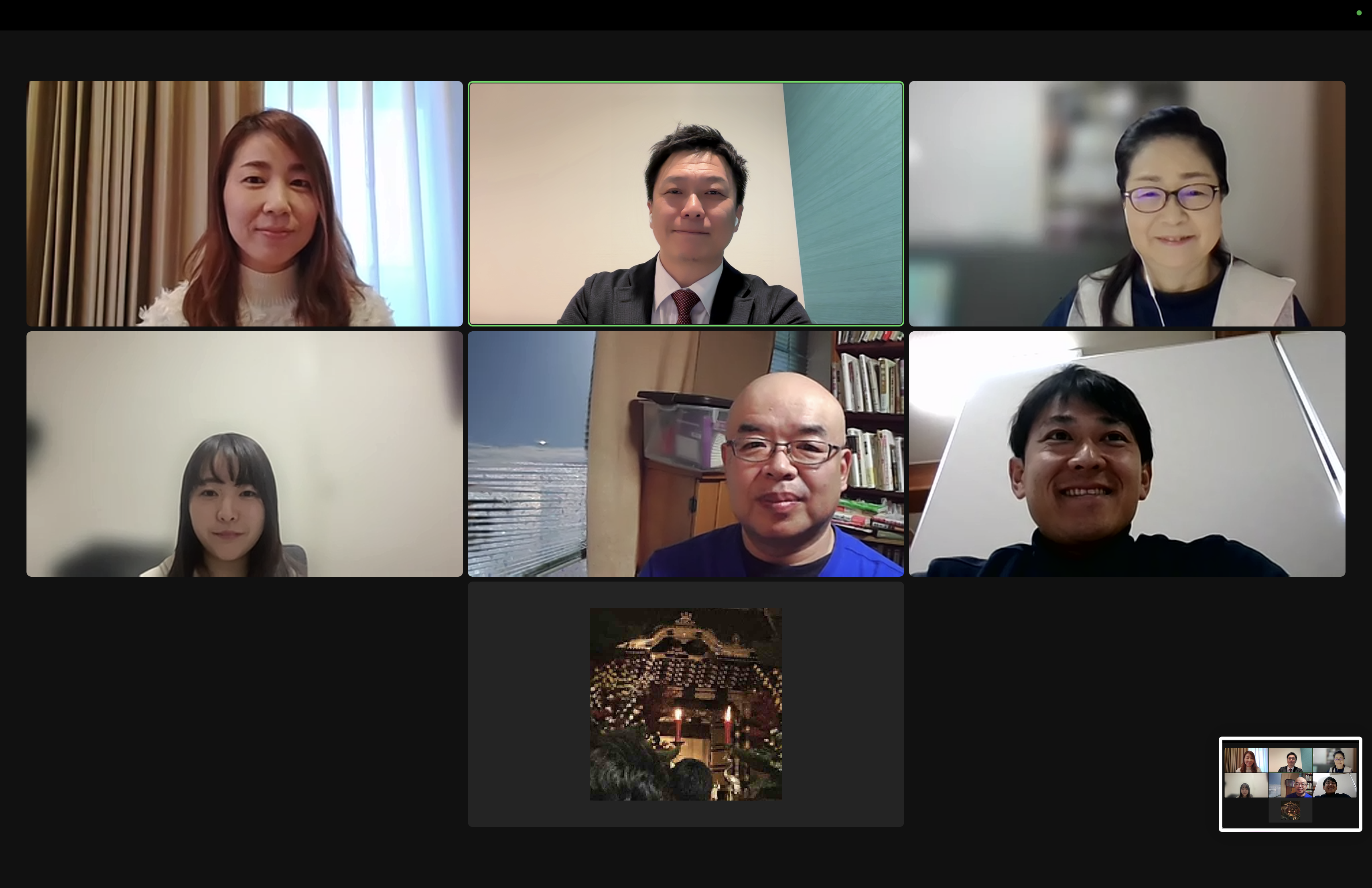教化伝道研修」第四期第二回(二〇二二年八月二十九日~九月一日)は、中山善雄研究員の発題、高柳正裕氏(学仏道場回光舎舎主)による課題別講義、亀谷亨研修長(北海道教区北第三組即信寺住職)より「聖教の学び」(『歎異抄』第二章)の考究が行われた。
また、第三回(二〇二二年十月二十五日~二十八日)は、名和達宣所員の発題、瓜生崇氏(京都教区近江第八組玄照寺住職)による課題別講義、亀谷研修長より「聖教の学び」(『歎異抄』第一章)の考究が行われた。以下、各回一名の研修生レポートを掲載する。
─────────────────────
第二回
佐々木 友美
(三条教区第十五組 光善寺)
今回の研修は『歎異抄』第二章を読み、そこから真宗同朋会運動の願いを尋ねた。真宗同朋会運動は、時代や価値観の変化の中で苦しむ人々に寄り添い、マルクシズムや民主化などの社会運動では応えきれない問題を問う、時代を超えた信仰運動である。
「真宗門徒一人もなし」という危機の表明から始まったこの運動は、単に教団の危機ではなく「私が真宗門徒でない」という危機を問い、どこまでも私の信を問う故に「純粋なる信仰運動」とも言われる。僧侶・門徒・門首すべての立場の者が南無の門をくぐる者であり、その門を開ける鍵は信である。にもかかわらず、阿弥陀仏に真向かう真宗門徒であり僧侶であるはずの私がそうなれていないではないか、と問われているのだ。『歎異抄』第二章では、関東の門弟たちが往生極楽の教えに不安を募らせ、はるばる京都までやってきたことが綴られる。「ただ念仏して弥陀にたすけられまいらすべし」という言葉の根底に「他力の念仏」が見えてこない門弟の姿は、私の実態とも重なった。
往生極楽は曇鸞和讃で「成仏の道路」と綴られ、その門は二つあるという。聖道門は、自力による救いを信じる向上の道だ。たとえ自力が地獄を作り出すとしても、聖道門では絶対にこの身の事実を見ようとしない。一方浄土門は、他力回向により浄土往生し成仏する道だ。自力では三悪道に陥るほかない私が、弥陀の本願によってはからずも打ち破られるというのだ。弥陀の本願は、念仏に込められている。私たちは念仏によって初めて仏陀の本願に触れ、「人」と生まれ、この身のまま仏になることができる。以前は先祖供養やお祓いの場面での「成仏」という言葉を、遠い絵空事に思っていた。そのような私に、「成仏以前にそもそも人間にすらなれていない」という問いが投げかけられ、人間性を失った自分の姿を思い出し、動揺した。
班別発表では「人身受け難し、今すでに受く。 仏法聞き難し、今すでに聞く」という三帰依文に立ち返り、往生極楽の道が「人となり仏となる道」であること、道を求めて私が立つ門は南無の門、すなわちただ念仏のみだということを改めて確認した。七祖の伝統も浄土真宗の権威を表すのではなく、どこまでも他力回向の教えの伝統であることを学んだ。しかし「なぜ弥陀の本願が立てられているのか」「なぜ阿弥陀仏ではなく南無阿弥陀仏が本尊なのか」「なぜ私の礼拝に先立って私に礼拝しているのか」ということは私のこれからの課題である。
「私が一番かわいい」という煩悩の身の事実は、親鸞聖人も関東の門弟たちも私も同じだ。そのような私に呼びかける真宗同朋会運動の願いは何か。「自分も他人も軽く見ない 命の重さにおいて向き合う いかなる人間も無条件に大切にできる人になってほしい」。亀谷亨研修長のおっしゃったこのお言葉に、私は「そうなれない私」をそのまま照らし出す弥陀の本願にうなずき、礼拝し念仏した先人たちの願いを感じた。
人を通して本願に触れ、私自身もうなずくとき、初めて礼拝や念仏に命が吹き込まれる。他力の念仏で穢土にいながら先人が繋いできた浄土と通じ、同朋の世界が開かれる。このことを親鸞聖人は往生極楽の道とおっしゃったのだと私はいただいた。
─────────────────────
第三回
望月 彌名子
(山陽教区第六組 浄泉寺)
生きていく迷いを晴らすための確かな答えが欲しいのが、私たち人間である。今回の瓜生崇氏の講義では、カルトは明確で論理的な答えを与えることで迷いが晴れたかのような気持ちにさせ、教団に引き込んでいくという話があった。そして、カルト問題を考えるために大切な点は、カルト宗教を「偽物か本物か」、「正しいか間違いか」と自分中心の考えで裁くことにあるのではない。そこに入信した一人一人が悩み苦しみ、真剣に答えを求めていたという事実に対し、宗教者としての自分が一体どの立場に立って目を向けるのかということにある。信仰の自由が私たちにはあって、個人の自由と尊厳を侵害せず、社会的に重大な弊害をもたらさないものであるのなら、どんな宗教であっても宗教者としてまずそれを敬うという姿勢が必要だということである。真宗の教えとは違うからという理由で批判するということは、自分自身を正しいものに仕立て上げているだけに過ぎない。
自分の「正しさ」で、間違っていると思う相手を批判するのは簡単だ。しかし、亀谷亨研修長は、自分が握りしめているその「正しさ」は、間違いを認めない頑固さやプライドという愚かさ、つまりは我執にしか過ぎず、そこをまず手放して相手と向かい合うことだと仰った。しかし我執を手放し、我執のない自分になるなどということは自分の力では到底できない。拒否や無視、対立を繰り返すことで私たちは自分が握りしめていたものにだんだん気付かされ、その存在を認めることを亀谷研修長は「我執は一番親しき友だ」と表現された。我執は影のようについてくる厄介なものであるが、私が「正しさ」に依存しないために、友のように大切なものである。我執を手放せない自分でしかないという自省に立って初めて、自分の立脚地が見えてくるのではないか。
この自分の立脚地ということについては、これまでの研修全体を通して何度も問われ続けていることである。冒頭で「確かな答えが欲しい」と書いたが、迷い続ける私たちにとって必要なものは「答え」ではなく、「確かな宗」を拠り所にして、迷いながら生きていく「生き方」である。迷う自分の姿を教えられ、そのままで生きていくということを確かめていくしかない。
名和達宣所員の発題において、「本願に帰る」とはどういうことかというお話があったが、「帰る」という言葉を咀嚼していくうちに、迷い苦しむばかりの自分でも、迷いのまま身を委ねてみようと思う心が私の中にあることに気付いた。迷いを大切にするという世界に、安心して身を委ねてみてもいいのではないか。
迷っていることを教えられ、そしてそこで安心して迷っていける世界というものを本願に知らされるのならば、なぜそこに安心できるのか、自分になぜそんな気持ちが起こるのかわからない。しかし亀谷研修長の「自分の抱える問題を引っ提げて、本願に飛び込んで欲しい」という言葉が私には自然に思える。自分の機の問題を抜きにせず、悶々と悩みながら、解決に至らずとも悩みを持ち続けていくと・はからずも・浄土の門がひらかれる、そのことが私に悩む力を与えてくれるのではないだろうか。
([教研だより(199)]『真宗』2023年2月号より)