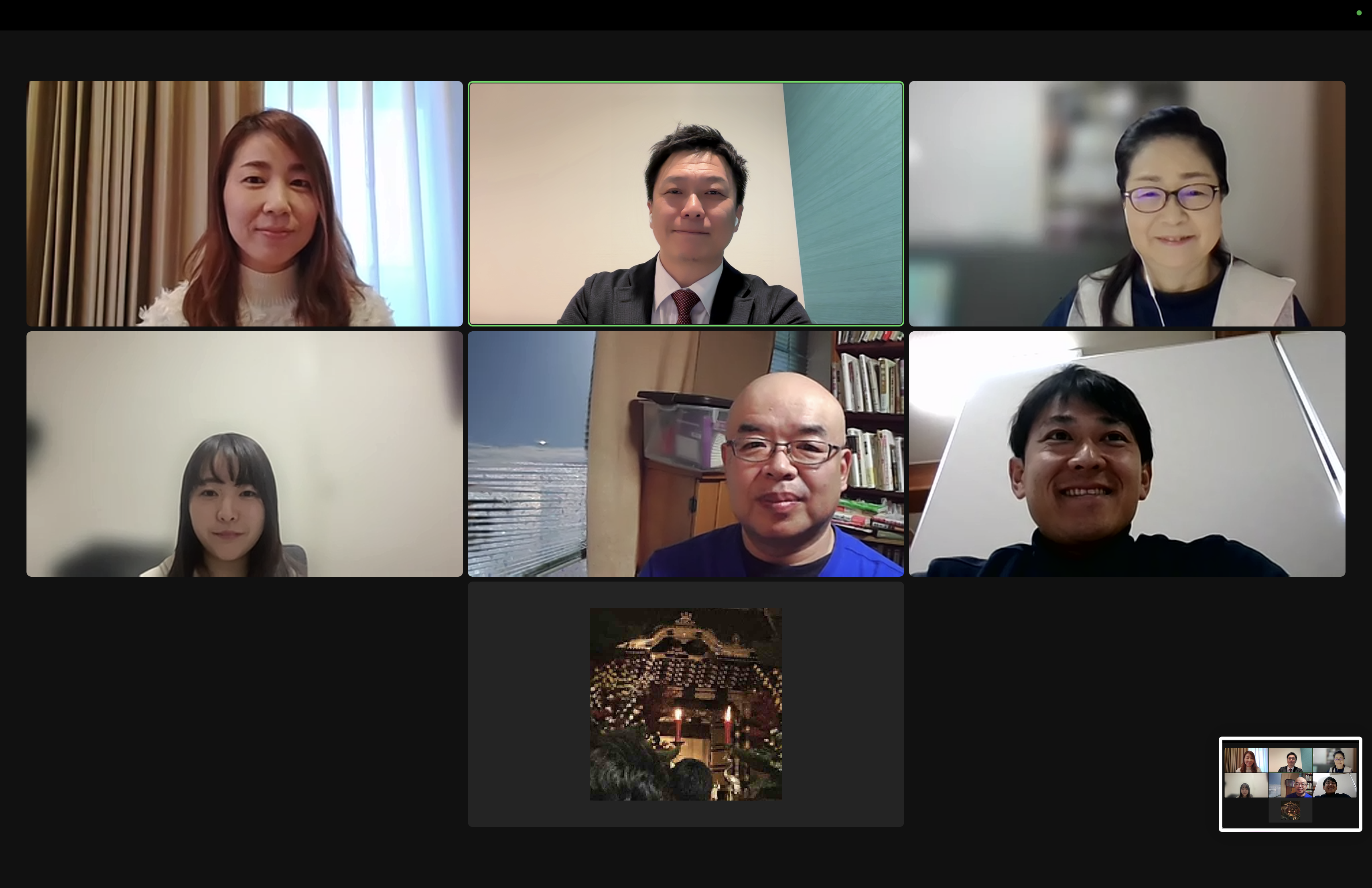生のみが我らにあらず 死もまた我らなり
法語の出典:清沢満之
本文著者:西本祐攝(大谷大学准教授。熊本教区正念寺衆徒)
清沢満之(一八六三~一九〇三)先生は三十歳の頃、当時、不治の病であった肺結核を患います。清沢先生は、すでに学生時代にも死についての思索を行っていますが、肺結核という病の身をとおして死を切実な問題として向き合い、差し迫る死の不安の中で、死についてのまとまった思索をしばしば日記に綴りました。標記の言葉は、清沢先生の日記「臘扇記」の一節をもとに、後に教え子が成文し、『精神界』という仏教雑誌に掲載した言葉です。
自らの命が永遠でないことは誰もが知っています。また、それがいつおとずれるとも知れないものであることも誰もが承知しています。ですから、清沢先生のこの言葉に初めて接した時の私の印象は、「そんなことはあたり前ではないか」というものでした。ですが、私自身の日常は、日頃から死とともにある生を自覚しているかというと決してそうではなく、むしろ、死を遠い未来のことと考え、死から目を背けて生きていると言わねばなりません。
さらに、生きている時に私はあり、死は私を終わらせるものでしかなく、「死もまた私たちである」とは決して受けとめていません。その意味でこの文は、死もまた私の人生の内容であることを、まずもって確かめる言葉であると言えるでしょう。
私自身の日常の意識は、どこまでも生と死を対立することとして捉え、生に執着し、死を厭い避けようとして生きています。ですから、死を身近に感じる出来事に遭遇したり、死の不安をともなうような病気になると、死の恐れの前で動揺し、苦しむことにもなります。
清沢先生は、仏教によって生と死とを相反することと認識しているうちは本当の安らぎに立つことはできないと述べます。なぜなら死の不安はどこまでも生に執着し死を避けたいと思うことから生じるからです。この執着から解放されていく道を説く仏教を人生の依り処とし、生も死もひとしく縁によって起こる事実であり、縁によって生まれ、生き、死んでいく自らの身の事実を受けとめることなくして、本当の安らかさはないと確かめていきます。
しかし正直なところ、その道理をあきらかにし、認識できたとしても、その身の事実を受けとめて生きることは、実際には困難であると言わざるを得ません。それは、生と死を含め自らの人生の内容をどこまでも自らにとって好ましいことか否か、都合の良いことか否かという相対的な価値判断で受け取ることを一歩も離れることができない者が私であるからです。このような私たちのあり方を悲しみおこされたのが阿弥陀仏の本願に他なりません。
清沢先生は、称名念仏に聞きひらかれる阿弥陀仏の本願を、絶対無限の妙用という言葉で語りました。それは、物事を相対的にしか受け取ることのない私たちのあり方を悲しみ、相対的な価値判断では量ることのできない身を生きている事実に、私たちをたえずよびさますはたらきとして阿弥陀仏の本願を受けとめられた言葉です。
生と死を人生の内容としてあわせもつその私が、どのような状況にある生も、どのようなおとずれ方をする死をも包んで、自らの一生をかけがえのないこととして受けとめて生きていく、そういう深い願いが満たされていく生き方が本願念仏の仏道に恵まれることを、清沢先生は思索し、語っていかれたのだと思います。
東本願寺出版発行『今日のことば』(2020年版【2月】)より
『今日のことば』は真宗教団連合発行の『法語カレンダー』のことばを身近に感じていただくため、毎年東本願寺出版から発行される随想集です。本文中の役職等は『今日のことば』(2020年版)発行時のまま掲載しています。
東本願寺出版の書籍はこちらから