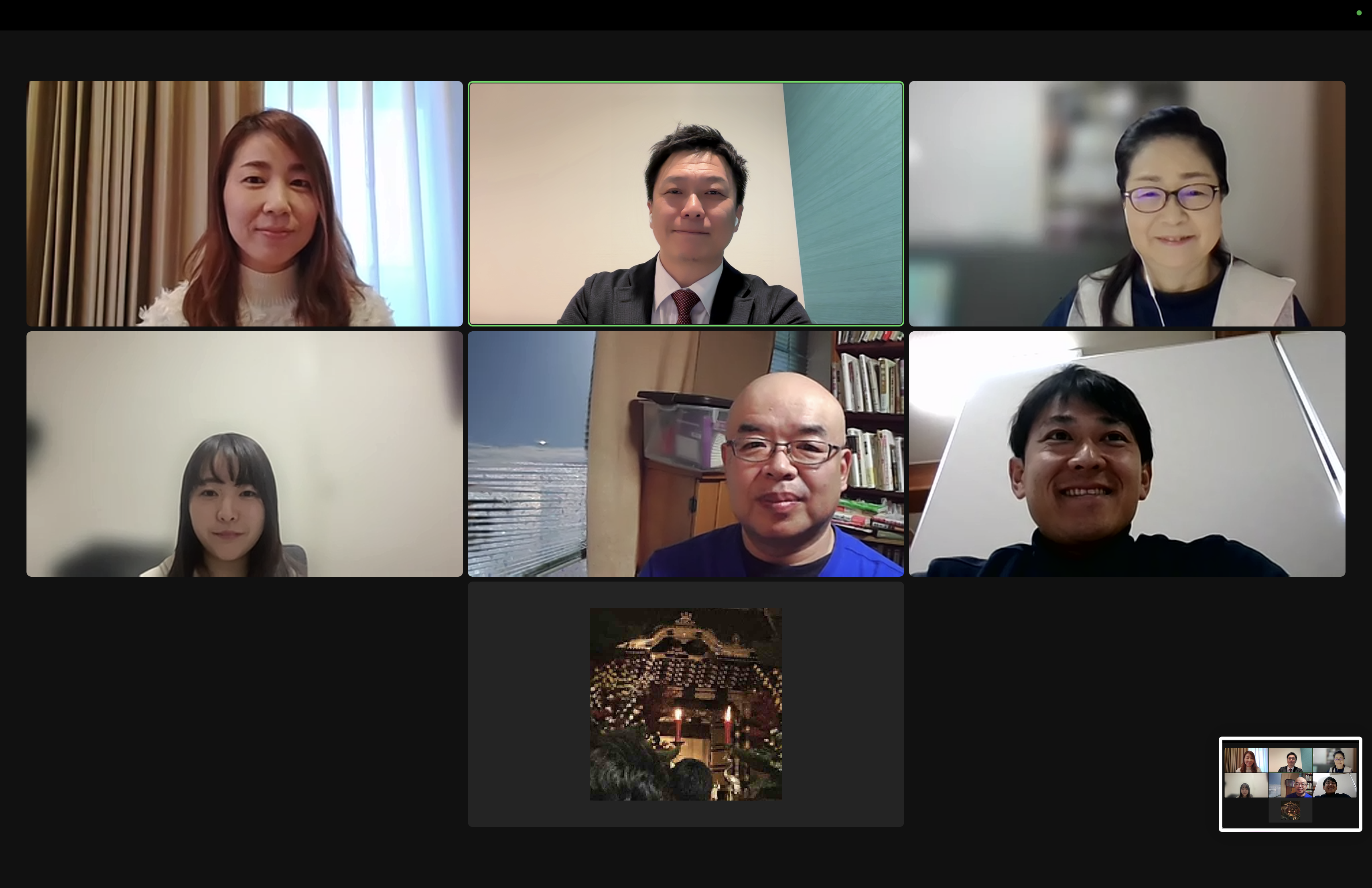不可思議の目覚め
(名畑 直日児 教学研究所研究員)
激動の近代日本を生きた清沢満之(一八六三~一九〇三)は、新しい文明、思想を吸収しながら、特に哲学という学問の方法を取り入れながら、念仏による救いの普遍性を、明らかにしようとつとめた。
満之は、一六歳(数え)の時、東本願寺で得度し仏弟子としての道を歩み始める(法名は「賢了」)。そして二十歳の時(明治十五年)、東京大学に入り宗教哲学を研究した。明治維新を機に、一気に近代化が推し進められ、西洋の哲学が流入する時代にあって、満之は、様々な哲学思想を学び吸収した。
その後、満之は、京都に赴き、教育の現場に身を置いた。その中で『歎異抄』に親しみ、行者の生活を実践する中で、三十歳の時、『宗教哲学骸骨』を出版する。そこで満之は、我々は真実に目覚めることが出来ないという根本的な課題(「無明」、「不得思議」)を抱えており、その課題への目覚めを契機とする救いの論理化を試みている。満之は、西洋の学問の方法を用いながら、その学問の不十分さを指摘しつつ、念仏(「宗教」、「安心」)による救いの論理を明らかにしようとした。
満之は救いの論理化を試みようとするのだが、救いとは我々の思いを超えており、また思いを破って働き出てくるものであるから、そこに矛盾があることはいうまでもなかった。
満之は、その後、肺病による「死」との出会い、そして『阿含経』、『エピクテタスの教訓書』(『歎異抄』を含め、「予の三部経」としている)との出会いを通して、真実への目覚めを成就していくのである。
満之は、『臘扇記』と題する日記の中で、真実への目覚めを表白していく。その中で、特に「不可思議」という言葉を書きつづっていることが注目される。我々は、死んだ後どうなるのか、死後だけではなく、現在ただいまのことでさえ、「不可思議」であるとしている。そして「要するに吾人の不完全は不可思議に乗托せしむる宗教を以て実際上の必須件とするものなり」(『清沢満之全集』第八巻三六六頁)とし、この不可思議の自覚が、救いの「実際」となることを指摘している。
このように見てくると、満之の歩みは、この不可思議(「不得思議」)による、救いの論理化、そしてその不可思議の自覚に注がれていたことがわかる。不可思議とは、単に何も分からないということではない。分からないと思っている「思い」が翻ることを、不可思議の自覚というのである。満之にとって、その自覚を促したのは、『歎異抄』等の教えと、自らの身に迫る「死」が大きな縁となっていたのである。
また不可思議の自覚は、本願の道理への目覚め(「無限の因果」「いわれ」)を意味している。つまり『歎異抄』第一条にある、「弥陀の誓願不思議にたすけられまいらせて」(聖典六二六頁)に続いて、「そのゆえは、罪悪深重煩悩熾盛の衆生をたすけんがための願にてまします」とあることが、リアルな事実として頷かれるということである。つまり、不可思議の目覚めとは、我々の思いを超えた本願の道理への目覚めであり、浄土真実への礼拝帰命の営みである。
(『ともしび』2015年9月号掲載 ※役職等は発行時のまま掲載しています)
「聞」のバックナンバーはこちら
●お問い合わせ先
〒600-8164 京都市下京区諏訪町通六条下る上柳町199
真宗大谷派教学研究所
TEL 075-371-8750 FAX 075-371-8723