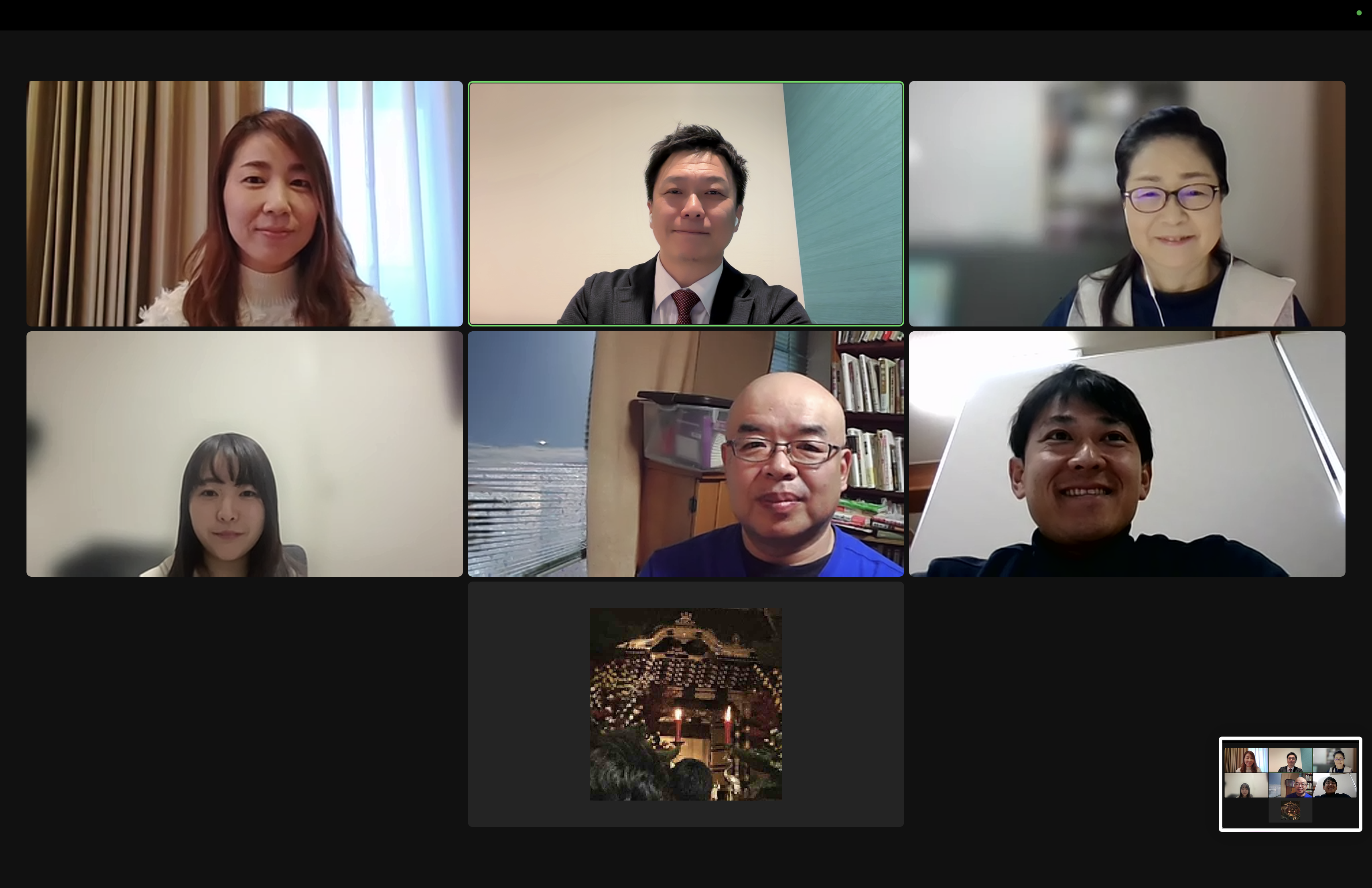南無阿弥陀仏をとなうれば
三世(さんぜ)の重障(じゅうしょう)みなながら
かならず転じて軽微(きょうみ)なり
(「浄土和讃」『真宗聖典』四八七頁)
ここ数年、胸奥に消えない「言葉」として、親鸞聖人のこのご和讃をいただいています。
功徳とは、ひらたく表現すれば「優れた性質(はたらき)をもつもの」と教えられます。現代において、また、私たちの日常感覚としてある代表的な功徳は、お金と健康と知識かと思います。お金があれば欲しいものをいちおう手に入れられます。健康を保っているあいだは自分ばかりでなく周囲も明るくします。高度情報化社会といわれるこんにち、知識の功能については申すまでもないでしょう。
さて、親鸞聖人はここに、「一切の功徳にすぐれたる」と明言されます。そして過去未来現在にわたる重い障りがみな、必ず軽く微(かす)かになる。無くなるのでなく転ぜられる。そのはたらきが「南無阿弥陀仏」である、とおっしゃいます。
これに容易に頷くことができない──その事実が私には確かにあります。ただ同時に、真宗本廟が今に、お寺が今に存在し、『正信偈』が現代に伝わり、南無阿弥陀仏の声がこの私に届いた事実は、この問題を消すことなく、生涯を貫く「問い」として磨いてくださっているようにも思えます。
また、このご和讃は、ある意味で、現代社会における仏教の”信頼度”の問題を投げかけてくださっているように受けとめられます。信頼度というと、なにか対象を向こうに置いた数値評価の印象がぬぐえませんが、言ってみればこれは「はたして私は仏教を本当に信頼しているのか? 何を信じてご門徒との仏事にたずさわっているのか。自分のモノサシや合理的かどうかという条件付きで仏教を捉えようとしてばかりいるのではないか」という問題です。
実際、このご和讃を頂戴するたびに私は、「仏教が自分の人生に役に立つのなら利用しよう」という日ごろの心が問われている気がします。南無阿弥陀仏をとなえたら本当にそうなるのか、この自分の苦悩が、誰にも言えない悩みが軽く微かになるのだろうか、もしそうなるのだったら用いてみてもいい、といった自力の執心を、まざまざと見せつけられます。ご門徒とのかかわりのなか”真宗の教化という問題で、最後のところはやはり一人の人間が自分に縁のある人々に「念仏せよ」と言いきれるか言いきれないか、というところにしか、もう問題はないのではないか”と吐露された先生もありました。真宗にご縁をもつ私たちは、このご和讃から、あらためて「信」の問題を、たいへん厳しいかたちで突き付けられているのだと思います。
信頼──「信」ということの対の語として宗祖は「疑」を示されます。疑惑とは猶予のことですが、「教えにはそう書いてあるけれど、現実はなかなかそういかないから…しかたがない」。これが猶予する心でありましょう。抜きがたい罪と教えられます。さらにこの問題は、そもそも私たちが「「たすかる」ということをどのようなものとしてイメージしているのか」という問いとなって立ち現れてまいります。都合よくいくことがたすかること、という深い闇は、どれだけ自分の胸先をこねても晴れることはないものと、日々あらためて思い知らされています。
安田理深先生のある講話の一節です。「教えは人に現れる」──真宗人である限り、私いちにんが、仏教の信頼を背負っていることになる。この意を、いま、お念仏にふれ得た私たちは、自分自身の毎日のひたすらに恥ずかしい言動を顧みながら、もう一度、ふかく受けとめ直さなければならないのではないでしょうか。
聞法の伝統に、かたじけなくも加えていただいた一人として、『正信偈・和讃』という祖聖渾身の讃歌から、日々またとない、尊いうながしを受けている。そのしあわせを、摂取の心光照護のなか、家族や友人と共に感じていきたいと思っています。
(教学研究所所員・小田朋隆)
[教研だより(122)]『真宗2016年9月号』より
※役職等は発行時のまま掲載しています。