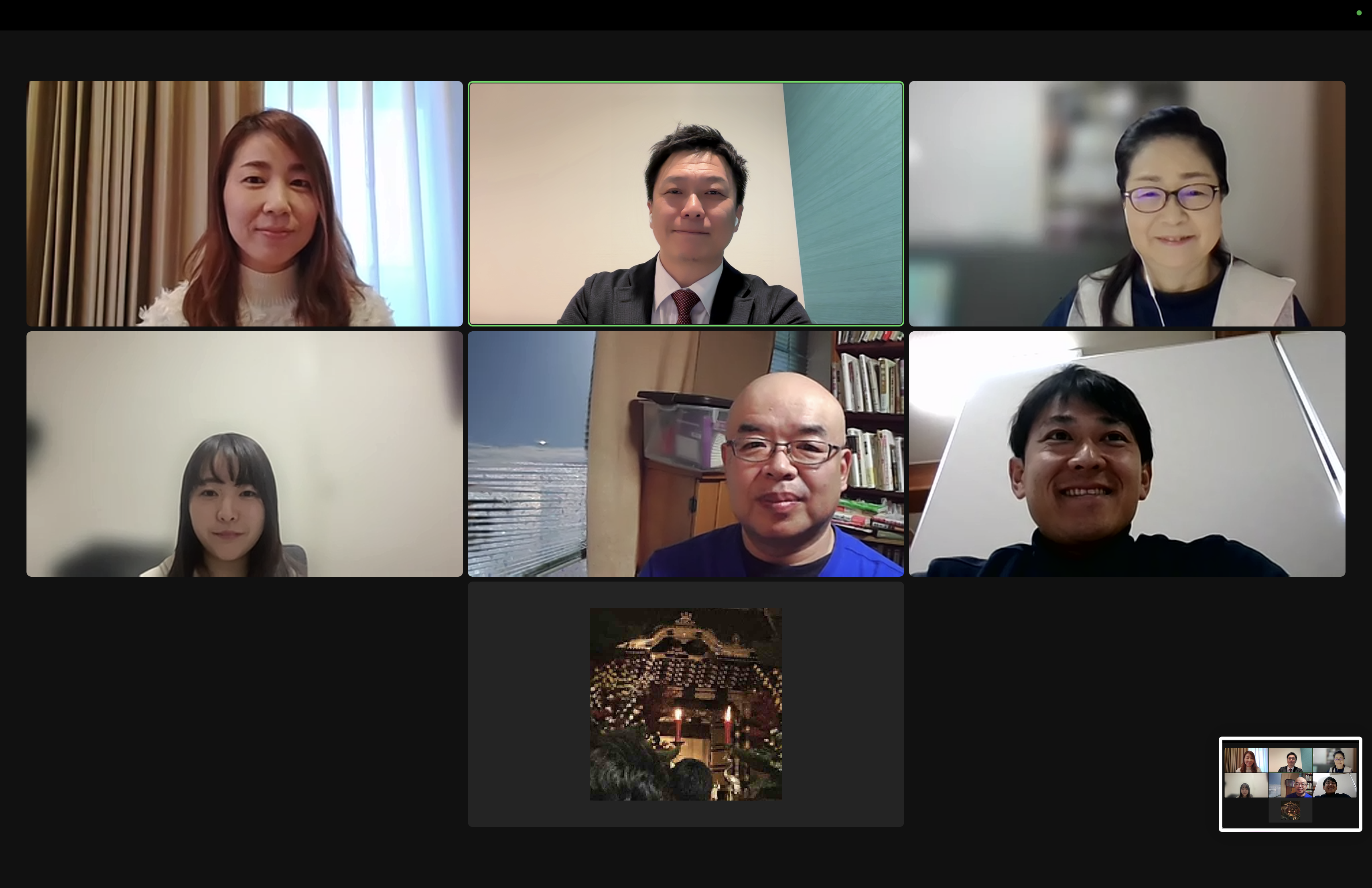「聖典と人権」をめぐる問題を考える
(名和 達宣 教学研究所所員)
宗門は今、聖典中に見られる差別的言辞を仏教徒としていかに受けとめるのか、という課題と対峙している。近年、中心的に議論がなされているのは、二〇一三年に部落解放同盟広島県連合会より改めて問われた、『仏説観無量寿経』中の「是旃陀羅」をめぐる問題である。その問題提起を受け、教学研究所では、現在、特に『観経』「序分」をいかに読み直すのか、という課題に取り組んでいるが、そこにおいて留意しなければならないのは、「聖典と人権」という問題である。
そのような背景より、二〇二二年九月七日、この問題に関して長く重厚な議論の蓄積があるキリスト教の事情を学ぶべく、宗教学者の小原克博氏(同志社大学神学部教授)を招き、研究会をおこなった。以下、講義内容の要約を報告する。
普遍的な課題
キリスト教や仏教をはじめ、長い歴史をもつ宗教は、多くの場合、反差別的な教えとして誕生した。しかし、だんだんと教団が大きくなったり、歴史が長くなったりするうちに、家父長制や身分制など、社会の支配的な規範の影響を受けていき、次第に容認するようにもなった。そのため、聖典中に差別的な言辞が記されている場合も少なくはない。
その意味からすると、今、真宗大谷派が取り組んでいる課題は、一教団(固有性)の中で自己完結させるような問題ではなく、人類史に関わるような普遍的な課題と言える。
正典の成立と聖書テキストの解釈
キリスト教では、三九七年のカルタゴ教会会議において、現在あるようなかたちで旧約聖書(三九巻)・新約聖書(二七巻)が「正典(Canon)」として認定される。これはテキストの固定であるが、同時に何が正統で何が異端かを判別する根拠(基準)ともなった。
十九世紀以降になると、ヨーロッパ社会では聖書学が発展していく。聖書学とは、従来、教会において「神の言葉」とされてきた聖書を、古代の文献として、学問的に扱う文献批評学である。その後、十九世紀末から二十世紀初頭にかけて文献批評学やダーウィンの進化論がアメリカにもたらされると、聖書をあくまで「神の言葉」として信仰の土台に据えるキリスト教原理主義が誕生し、キリスト教社会は二分化した。
聖書の言葉と翻訳
聖書の原語は、旧約はヘブライ語(一部はアラム語)、新約はコイネーギリシャ語である。当初、教会はローマ帝国から迫害・弾圧されていたが、四世紀になると同国の公認宗教となり、やがては国教となった。そのようにして教会が安定すると、東方(中東・ギリシャ・東ヨーロッパ)・西方(ドイツなど西ヨーロッパ)に分かれ、東方はギリシャ語、西方はラテン語の聖書を使うようになった。日常語ではないラテン語で書かれた聖書は、一部の人にしか理解できないものであったが、十六世紀にルターが宗教改革をし、聖書をドイツ語に翻訳した。そしてドイツ語聖書は、活版印刷(グーテンベルクの発明による)という時代の恩恵を受けて本屋に並び、一般の人でも誰でも手にとることができるようになった。
以降、聖書はさまざまな言語に繰り返し翻訳され、次々と新しいバージョンが出されていった。現代の聖書の翻訳では、ほとんどの場合、包括的言語(inclusive language)が意識されている。それは、原語の中に差別的・排他的な表現がある場合、より多くの人を包摂できるような言語へ翻訳するというもの。
ただし、長年聖書は、もっぱら男性中心社会の中で、男性によって解釈されてきた。そのため、多くの場合、女性のことが視野に入っておらず、さらにはそのこと自体が正当化・容認されてきた。キリスト教はもともと社会の周辺に置かれていた。しかし、時を経て支配宗教になると、迫害されていた歴史を忘れてしまい、自分たちの支配的な立場からいろいろなものを切り捨てていったのである。
イエスが語った言葉と、後世のキリスト教教団の歴史とは、やはり大きく乖離していると言わざるをえない。その事実をしっかりと見ていくことが、歴史研究の大事な点である。
性差別に対して
聖書の中には、現代の観点から見ても解放的な文言もあるが、他方で、家父長的・男女差別的、あるいは同性愛者を批判する根拠として扱われるような記述が多数存在する。
そのような記述に対しては、包括的言語をもって可能な限り差別を引き起こさないような解釈を選ぼうという試みが、一九九〇年代から始まり、今に至る。ただし、翻訳には程度の幅があり、翻訳者の主観が入り過ぎると、原文を無視した改ざんとなってしまう。
翻訳(解釈)のレベルでは、そのような試みがなされながらも、現代でも正典(原典)としてのヘブライ語旧約・ギリシャ語新約の聖書は固定されている。そのため、テキスト自体の言葉を削除するとか、「読まない」といった手の入れ方は一切しない。
おわりに――差別を克服するために
差別を克服するためには、自分の宗教の歴史、教義・聖典と批判的に向き合うことが必要である。また、偏見や誤解を克服するための一助として、科学的知見から学ぶことも重要であり、課題を多面的に理解するためには、他の宗教と協力する必要がある。そして、差別の問題とは、宗教だけの問題ではなく、人類普遍の課題である。普遍と固有とを行き来しながら、教団内の議論を開かれたものにしていくことが大事ではないか。
研究会を終えて(担当者所感)
講義を聞き終えて、第一に、キリスト教では聖書の中に差別的な表現があると認めても、テキスト自体の言葉を削除するとか、読まないといった手の入れ方をすることは一切ない、と断言されたことが印象深かった。「同時にそれを超えていけというメッセージを聞き取るから」であり、またそもそも「正典」たる聖典を、時代ごとの価値判断で不要とするような議論自体があってはならないためであるという。そのことを小原氏は、ナチス時代(第二次世界大戦中)にドイツで旧約聖書が排除された例などを挙げつつ、繰り返し指摘された。
なお、そのことに関連して、質疑の際に「もしも聖書のある差別的な文言を読むことで、聞いている人の中に「痛み」を感じる方が出る可能性がある場合、どうするのか」と尋ねた。すると小原氏からは、「その場で読んだ言葉の解釈を牧師が説いて、読みっぱなしにしない」という応答がなされた。また質疑の中で、大谷派宗憲第十一条に定められた「正依の聖教」のことを紹介したところ、「キリスト教で言う正典(Canon)に近いのではないか」との返答をいただいた。
「聖典と人権」の問題を考えるにあたり、まずもって人権の尊重という基本を外してはならない。その上で、原典と解釈の分限を冷静に見定めることの必要性を、改めて強く感じた。講義の最初に述べられた、今、大谷派が取り組んでいる課題は「人類史に関わるような普遍的な課題」という言葉が、胸のうちに重く響いている。
([教研だより(197)]『真宗』2022年12月号より)