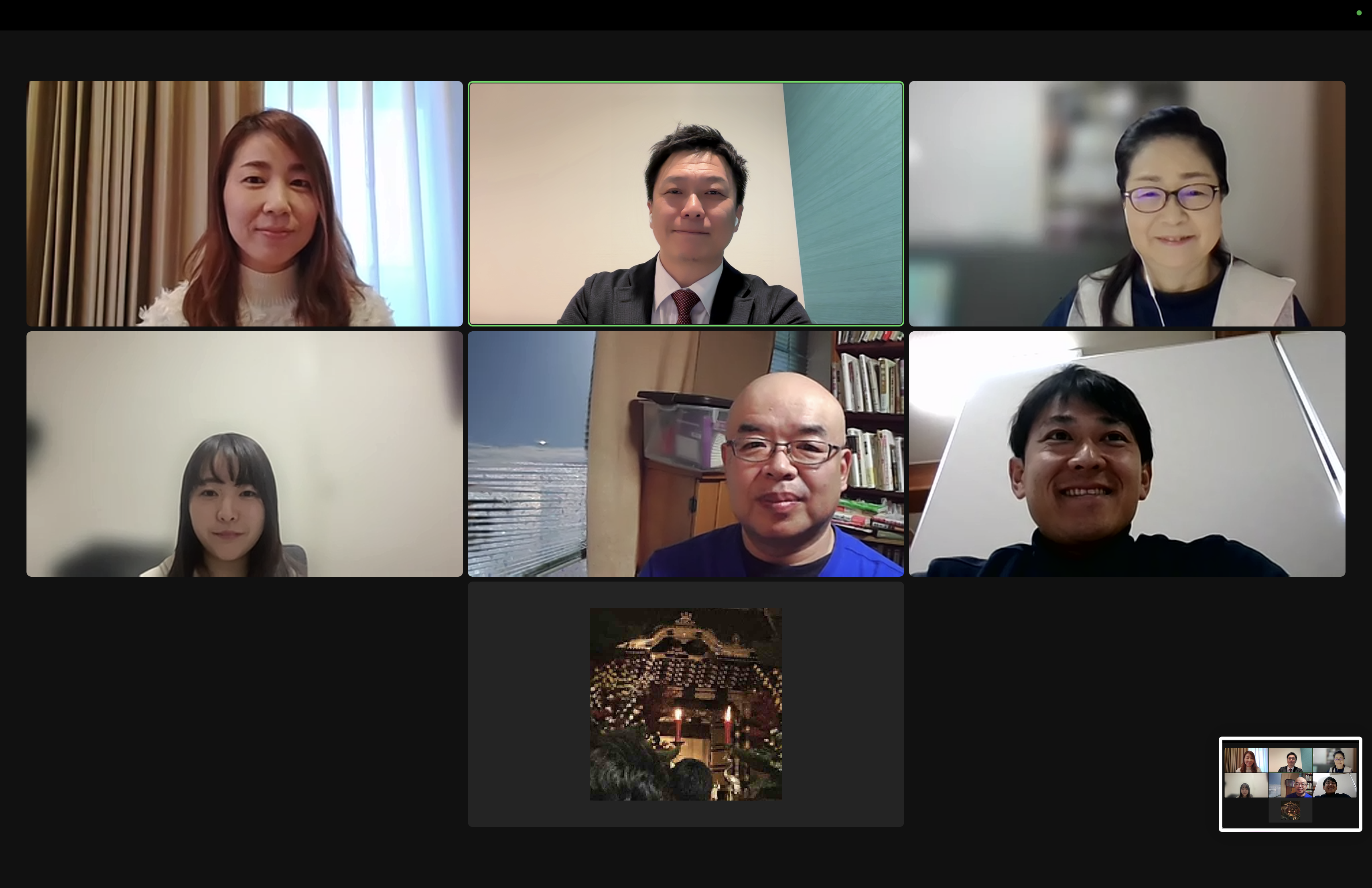いまからちょうど七十年前(一九五二年)、曽我量深先生は、宗祖の七百回御遠忌(一九六一年)を九年の先に迎えるという時、「その第一の仕事は教主釈尊に帰るというのが一番大切なことであろう。小さな宗派根性で仏教を私してはならぬ。(中略)根本の釈尊に帰るのが一番の要でなかろうか。それでなくては、仏教は世界的になることができない」と講話(「往還の対面」一九五二年三月)の最後で語られた。
それから三ヵ月後、「私は清沢先生のたどられた道を思うとき、仏教は釈尊に帰らねばならぬと思う。釈尊を超えねば釈尊に帰られぬ。親鸞の七百回忌の御遠忌(一九六一年)を迎えるにあたって、親鸞のところに立ち止まってはだめである。南無阿弥陀仏の根元に帰って釈尊を超えて釈尊に帰らねばならぬ」と、清沢先生五十回忌記念講演会の講話(「如来について」一九五二年六月)の最後で語っておられる。
私たちは、明二〇二三年春に、宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要を迎える。曽我先生は講話の中でしばしば、御遠忌の法要を十二年後に迎えるとか、九年後に迎えると言って、早くから心待ちにしておられたようである。ではいったい私たちはどんな心で迎えようとするのか。他にはない、私は曽我先生にならおうと思う。「南無阿弥陀仏の根元に帰って釈尊を超えて釈尊に帰ろう」と思う。
では、その道はいかん。先の二つの講話の中で曽我先生は、「釈尊の悟りは南無阿弥陀仏である」と言っておられる。これまでずっと、ややもすれば執拗に、私はこの言葉と向かいあってきた。まだずっと終わらないとも思う。時々においてこの言葉が発せられた脈絡が見えかくれしている。それはつまり、曽我先生の発語における意図の表と、隠されているかも知れない裏と、その全貌が私には見きわめられないからである。
見えるかぎりで言えば、曽我先生には、帰るべき教主釈尊とは誰かということの結着がついていないのではないかと思われる。というのは、この発語の背後にあった問いを曽我先生は問い切っていないからである。「清沢先生のたどられた道を思う」からこそ、「他力救済の教え」と「釈尊の根本仏教、阿含経というようなものといったいどんな関係をもつか」ということが問題になったと講話で語っておられる。
そしてそれを問いたずね、「釈尊の悟りを親鸞はどのように了解していたか」を考え、『大無量寿経』の本願成就文が釈尊の体験、釈尊の悟りをあらわすと親鸞聖人は了解したと受けとめて、「釈尊の悟りは南無阿弥陀仏である」と語られたのである。そして「釈尊の悟りの体が南無阿弥陀仏というのが親鸞の了解の根本の問題であろう。これはいままで言わなかったことである」と言う。なるほど、しかりである。
それでも、私は執拗に、阿含経との関係という最初の問いはどうなったのかと食いさがってみたくなる。
その後の講話をみると(「分水嶺の本願」一九五二年七月、九月)、最初の問いは決して忘れられていたのではなく、逆に阿含経がばっさりと切り捨てられてしまったのである。「なぜあんな経典が伝わったか、あんな散漫な個人的な解説が……」という具合である。こんな乱暴な言葉を浴びせられても、阿含経は減りもせず増えもしない。教えていただけないなら、自分でたずねていかざるを得ない。
したがって曽我先生の「釈尊の悟りは南無阿弥陀仏である」というこの発語は、無量寿経の教主釈尊のことであったということになる。そして実は初めからそうであったのを、私が早合点して阿含経の教主釈尊のことと思い込んだということである。
最近、別の見方があることに気がついた。宗祖聖人は「正信偈」の依釈分の初めに三国の高僧たちが「大聖興世の正意を顕し、如来の本誓、機に応ぜることを明かす」と言われる。七高祖たちがそれぞれ、仏陀釈尊の出世の正意としての如来の本願を受けとめ、解釈されたということである。
『教行信証』「教巻」には、宗祖聖人自身によって『大無量寿経』が出世の大事を説く真実の教であることが述べられ、そして「正信偈」の依経分でも「如来所以興出世」と出世本懐が述べられている。
『まさしく仏陀の出世に出会ったものこそが、その仏陀の出世の本意を明らかにすることができるのだと言わなければならないだろう。したがって、如来は弥陀の本願海を説くために世に出興したと述べておられる宗祖聖人は、その無量寿経の教主釈尊に出会ってそのように語っておられるのである。
そして七高祖がたもまた、大聖興世の正意を顕しているのだから、大聖釈尊に出会って論釈を作っておられるのである。『浄土論』の世親は「世尊我一心」と言い、無量寿経の教主釈尊に向かって「世尊よ」と応答しているように。
そして「釈尊の悟りは南無阿弥陀仏である」という曽我先生の言葉もまた、大聖興世の正意を顕す七高祖や宗祖聖人と並んで、その無量寿経の教主釈尊との出会いを語るものであると言うことができるであろう。
ここまでが見えているかぎりのことである。残った問題は、無量寿経の教主釈尊と阿含経の教主釈尊とがどのように関係するのかということになる。結局、曽我先生が出された最初の問題にもどることになる。これは解けない問題なのか。それでは、釈尊に帰るといっても、どの釈尊に帰ればいいのか、帰れないことになる。
実は、この曽我先生の言葉を、何度も取りあげられた方がいる。児玉暁洋先生である。児玉先生もまた、私が早合点したように、曽我先生の言葉から、阿含経の教主釈尊の悟りが南無阿弥陀仏だと読まれた。だから、どうしてこんなことが言えるのかという驚きをもって取りあげられている。
私たちは、もはや阿含経の教主である釈尊を離れては釈尊を語ることができない時代を生きているのだ、という感覚が児玉先生にもあったのだろうと思う。だからまた、常に阿含経の教説を大事にされていた児玉先生は、宗祖聖人の「正信偈」の源空章のなかに、釈尊の四聖諦の教説との一致を見出されたのである。「還来生死輪転家 決以疑情為所止 速入寂静無為楽 必以信心為能入」が、苦集滅道の四聖諦にぴったりと相応していると言われた(「正信偈響流」『児玉暁洋選集』第八巻、九九~一〇三頁)。
この源空章の言葉は、『選択集』の三心章深心釈によるものであり、それは二種深信を語るものである。初めの二句は機の深信を、後ろの二句は法の深信を語り、また初めは生死の因果を、後ろは涅槃の因果を表わしている。だから、二種深信という構造をもった真実信心が、苦集と滅道との構造をもった縁起の構造と一致するということを意味している。私にとって、このことが何を意味するのかというと、阿含経の教説を新たな観点から解釈しなおす可能性が開かれてくるのではないかということである。
無量寿経の教主釈尊の悟りは南無阿弥陀仏であると、曽我先生が言われた。その曽我先生の了解をさらに推して、その南無阿弥陀仏の一声に、阿含経の教主釈尊の正覚の一念が響き流れているのだと、児玉先生がお説きになっていると、私たちは了解したい。
そして「南無阿弥陀仏の根元に帰って釈尊を超えて釈尊に帰らねばならぬ」と曽我先生は語られた。その「釈尊に帰る」ということが実質的な意味をなすのは、「南無阿弥陀仏の根元に帰って」、すなわち本願の真実に帰って、阿含経の教主釈尊の言葉が、現代を生きる私たちの生活を照らし出すのだと言えるまでに、意味開示の努力をしなければならないのだと思う。
([教研だより(192)]『真宗』2022年7月号より)