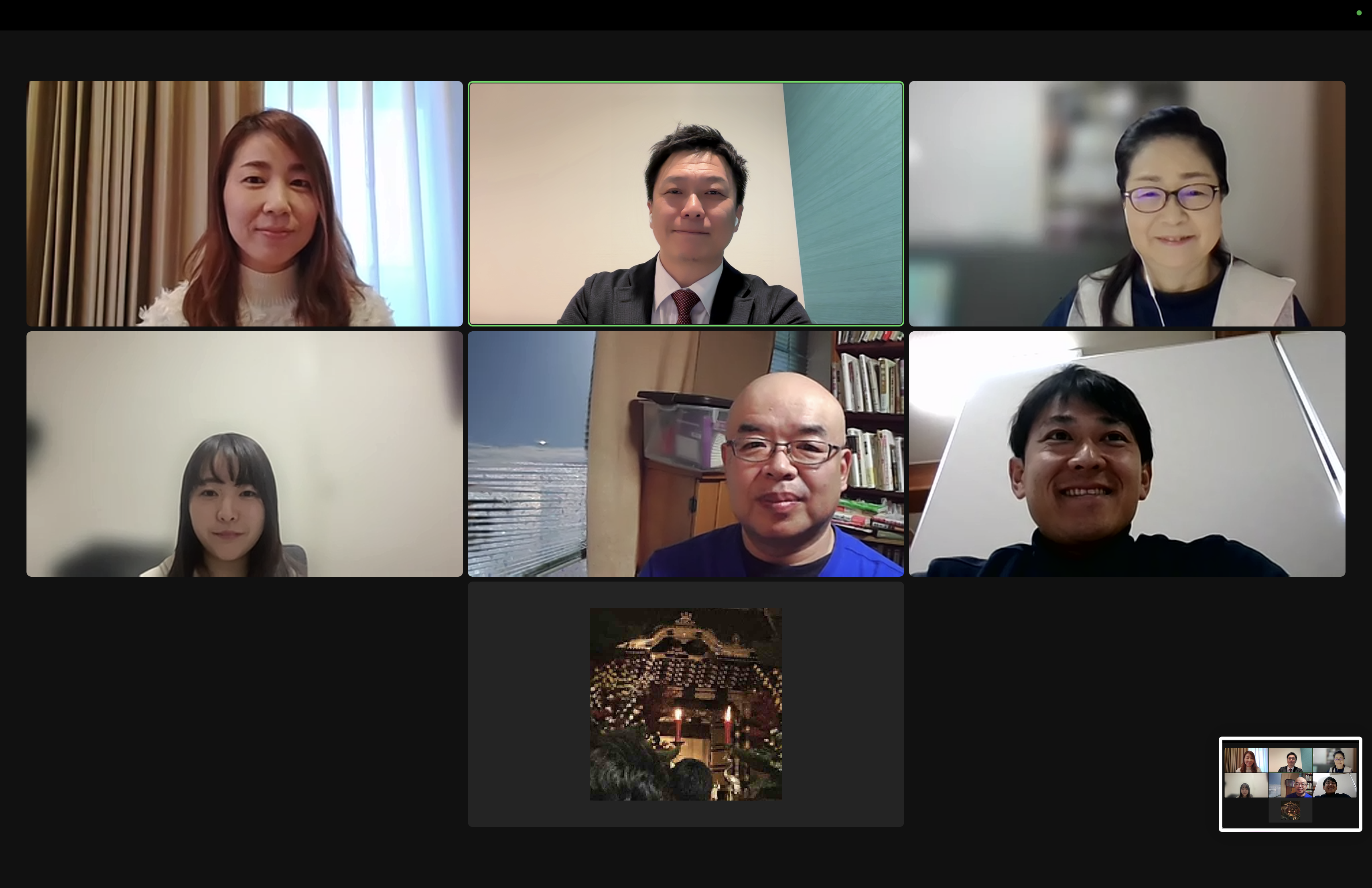正午の鐘
著者:有賀尚子(長浜教区光了寺)
8月15日
私は子どものころ、お盆というのは終戦記念日のことで、戦没者に対してのお参りをする行事だと思っていました。
私の地元では、お盆の期間中、何軒かのご門徒のお宅に盆逮夜としてお参りに伺いますが、お寺で盂蘭盆会を勤め、皆さんがお参りに来られることはありませんでした。
しかし、8月15日の終戦の日だけは、正午に鐘をつき、その後本堂で阿弥陀経・正信偈のお勤めをする習慣があり、その鐘をつくのが私や姉妹の仕事でした。ちょうどお昼ご飯の時間です。ラジオ片手に正午の黙とうの合図とともに鐘を鳴らしました。おなかがすいたなあと思いながら、このお勤めが終わらないとお昼が食べられないと不満にも思ったものです。
その15日のお勤めには、1人2人と、わずかにお参りに来られる方がありました。正午といういわゆる「時分時」に御仏供米を持ってお参りされ、特に言葉を交わすこともなく、お勤めが終わると静かに帰って行かれました。その人たちは、子や兄弟など、身内が戦死している方々だったのです。だから、この日に、お参りに来られるのだということを大人になってから知りました。住職の読経は、アブラゼミの鳴き声が響く中、お線香とツンとした辛めのお焼香の香りと、じっとりとした汗と共に思い出します。報恩講とはまた違う厳粛な雰囲気が漂っていました。
お参りされていた方々が、どなたを亡くされ、どういう思いでお参りに来られていたのか私は知りません。ただ、ご本尊の前に身を置き、手を合わせることでしか表せない思いがあったのだろうということに、今ごろになって気づくのです。
あのころからずいぶん時が経ちました。かつてお参りに来られた方々の姿はありません。戦死した人のことを知っている人たちがいなくなって、もう鐘をつくのもやめようかと思ったりもしました。
そこで思うのです。私たちは、自分の身近な人、顔が分かる人、声が思い出される人、何より自分を慈しんでくれた人のことは折にふれ思い出します。そして、さまざまな思いから手を合わせます。それは、懐かしさであり、恋しさであり、もって行き場のない苛立ちであったりします。
しかし、自分の視野に入らない人のことに気づくことはなかなかありません。普段私は、私の世界だけで、私の力だけで、誰のお世話にもなっていない、と思って生きています。そして、そうあることが一人前の人間であるように思います。自分の知らないものは関係ない、要らない…と。
でも、本当にそうでしょうか。私たちは少しうまく事が進むとすぐに傲慢になります。また、反対に些細なことから自らを卑下します。私って何なのでしょうか。
そんな「私」は、ある日突然この世に出現したわけではありません。どういう縁をいただいて生まれ、生きてきたのか。自分にとって都合の良いことだけが縁ではありません。できたら「消去」したい。人生に「戻る」のボタンはないのかと探しますが、そういう様々な不都合もすべてが縁、自分の出来事です。様々な縁が私を今日生かしているというのが事実なのです。
お盆は、地域によって日はまちまちですが、亡き人をしのび手を合わせる大切な行事です。まずは身近な亡き人をたよりに、その先の多くの人たちとのかかわりの中で私が生かされているという事実に、思いを巡らせてみることが大事ではないでしょうか。
8月15日正午、今年も鐘をつきます。
東本願寺出版発行『お盆』(2020年版)より
『お盆』は親鸞聖人の教えから、私たちにとってお盆をお迎えする意味をあらためて考えていく小冊子です。本文中の役職等は発行時のまま掲載しています。
東本願寺出版の書籍はこちらから
読みま専科TOMOブック