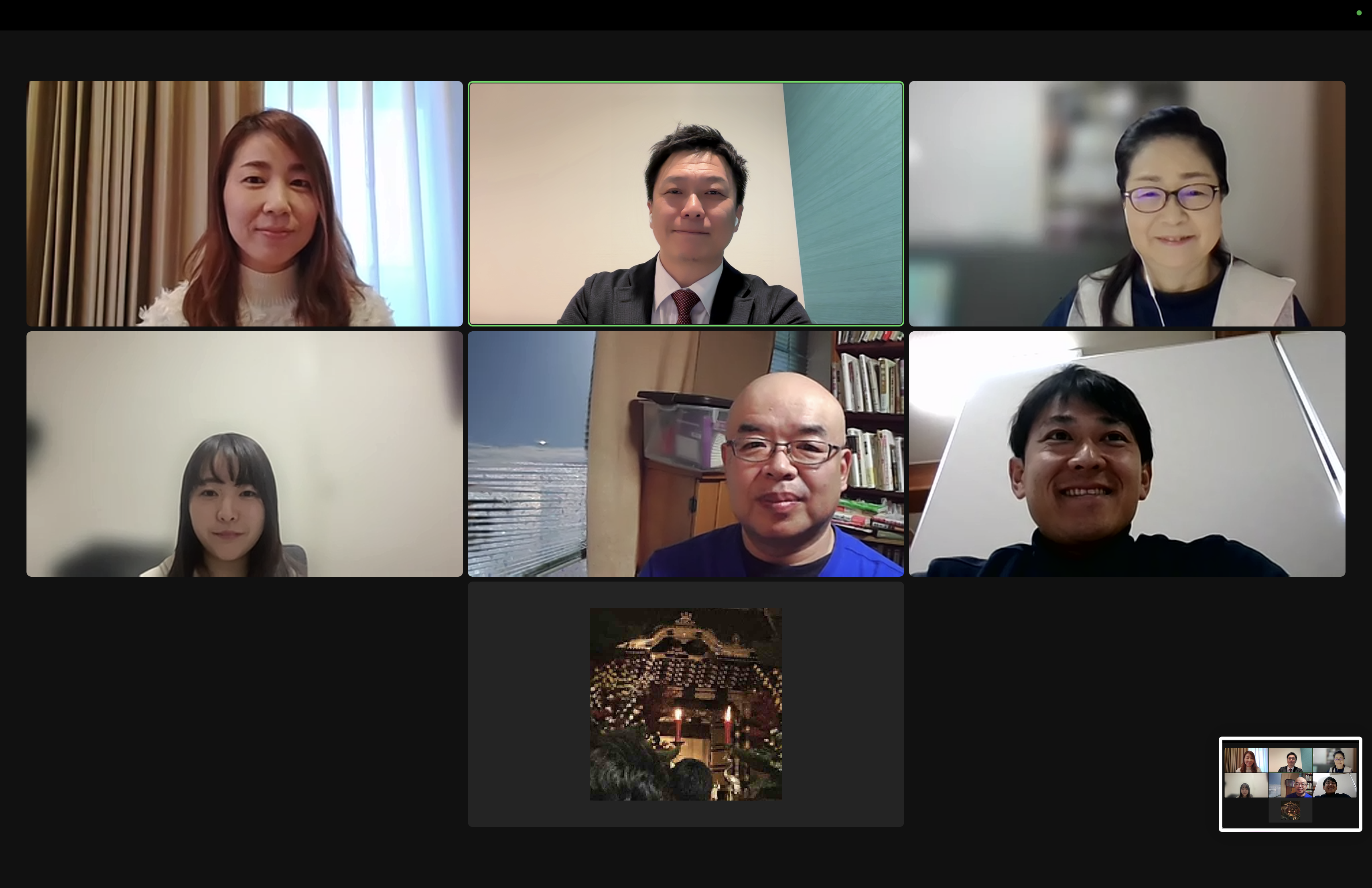(『教行信証』「別序」/『真宗聖典』二一〇頁)
中学二年生の頃、英語の授業中に突然、えもいわれぬ違和感におそわれた。教師が黒板に「答え」を書き、私たちにそのまま写すよう指示した瞬間、全身に強烈な拒否反応が起こったのである。それは第一に「先生が書いたからといって、本当に”答え”なのだろうか」という素朴かつ不遜な問いであったが、加えて、クラス全員で書き写すという行為に対しても、何ほどかの疑問が生じた。
その後、疑問の実態がよくわからないまま思春期を過ごしていったが、やがて高校に進み、ある時期から夢中になって読みふけった寺山修司の作品中に、「きっとそういうことだ」と思えるような、いくつかの言葉を発見した。それらはいずれも「問い」をめぐるもので、「人生はただ一問の質問にすぎぬと書けば二月のかもめ」という歌や、二匹のカメを飼って大きい方を「問い」、小さい方を「答え」と名づけた逸話などであったが、つまるところ「問い」は「答え」よりも大きく、人生を貫くものにちがいないという予感をえた。
このような経験があったためか、成人して初めて『教行信証』を読んだ時、「しばらく疑問を至してついに明証を出だす」という言葉に強く惹きつけられた。これは「行巻」と「信巻」の間に位置する「別序」のなかの一文であるが、古来「疑問を至して」というのは、「信巻」中に展開される「三心一心問答」を指すと了解されてきた。しかし、ここで言われる「疑問」は、それだけの意味にはとどまらないであろう。『教行信証』という書物全体の底を貫くもの、ひいては宗祖の学問の姿勢を象徴するものではないかと受けとめる。
もし『教行信証』が「答え」のみを示す書であるならば、「教巻」「行巻」で十分に尽くされているともいえよう。現に「行巻」では、称名念仏の伝統と利益が確かめられ、巻末の「正信念仏偈」は、「唯可信斯高僧説〔ただこの高僧の説を信ずべし〕」(聖典二〇八頁)という一句で結ばれている。ところが宗祖は、その「答え」に落ち着くことができなかった。むしろ、仰ぐべき「教」「行」が明らかとなった時、同時に自らのうちに、ごまかしのきかない大きな「疑問」を感得した。それは、和讃に「浄土真宗に帰すれども/真実の心はありがたし/虚仮不実のわが身にて/清浄の心もさらになし」(聖典五〇八頁)と詠われるように、帰すべき仏道との値遇によって、初めて問いたずねていくべき課題が見出されたことを意味するであろう。
そこにおいて、自身が衝突した「疑問」と向き合い、その実態を追究しようと展開したのが「信巻」である。その「疑問」とは、「何を信ずべきか」と、教義を対象的に問うような質のものではない。むしろ「信によって問われる」とでも称すべき、立場の根本的転換に根ざした大いなる「問い」であった。
──「問い」は「答え」よりも大きい。
宗祖の言葉に学び、予感は確信に変わった。真宗の救いは、歴史を貫く「問い」との邂逅にかかっている。では「答え」はというと、一人ひとりの身上において明証(あか)していくよりほかにないであろう。
(教学研究所研究員・名和達宣)
[教研だより(135)]『真宗2017年10月号』より
※役職等は発行時のまま掲載しています。