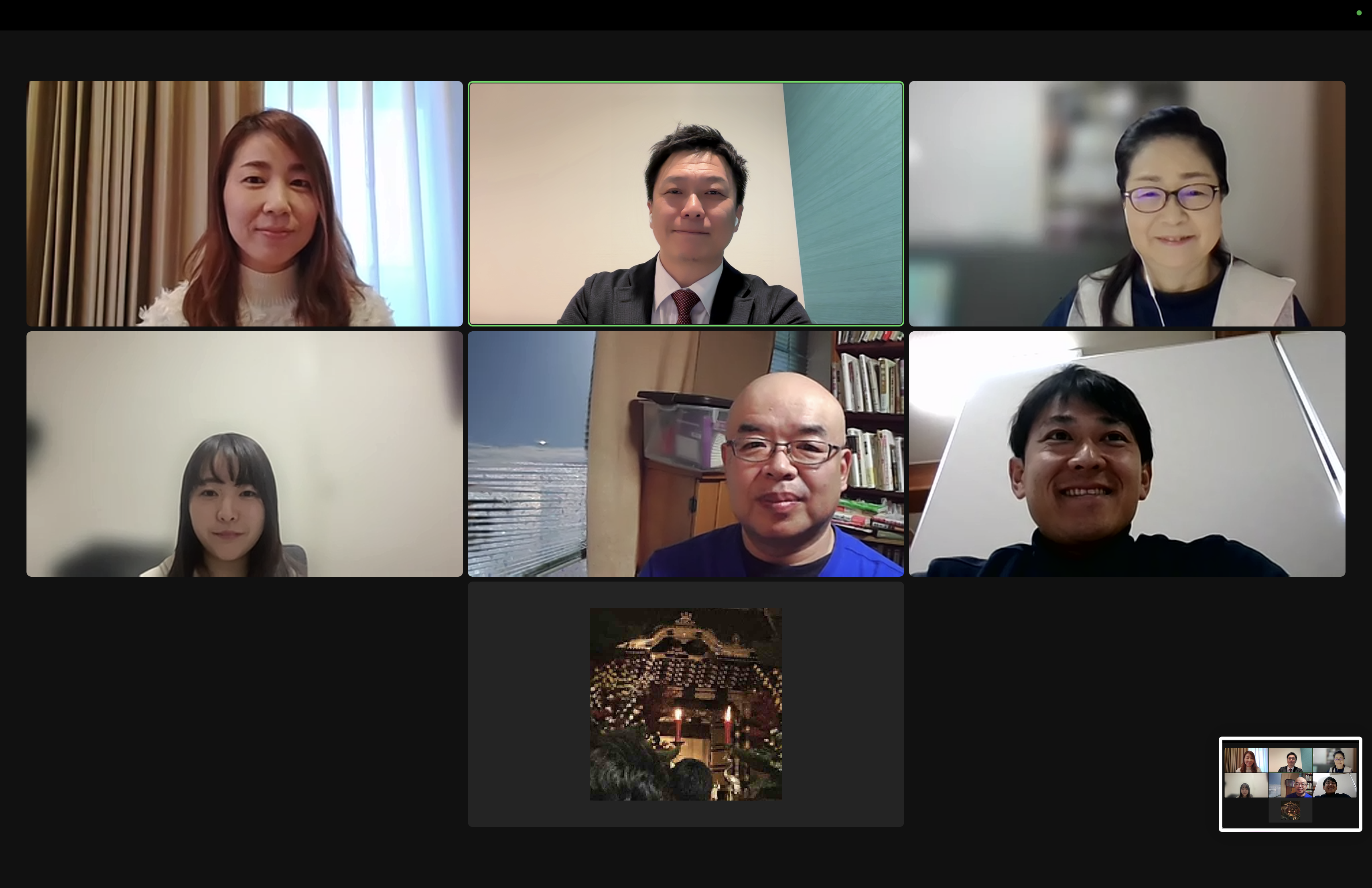(『教行信証』行巻『真宗聖典』一五七頁)
「自分の存在は大海を漂う浮草のようだ」。
物心ついたころから私は、このような感覚に囚われ、虚無的に生きてきました。その私にとって転機となったのは、二十四歳の時に東京の書店で偶然、一冊の本を手に取ったことでした。
そこには、
と記され、また、
と述べられていました。私が自己を探し求めるに先立って、向こうから曠劫以来呼びかけられていたことを教えていただいた言葉です。
その言葉によって、私を悩ませていた虚無感が、実は「如」(真実)からの呼びかけであるという感覚が生まれました。自分を無条件に呼び求める声があり、同時にそれは自分に真実を求めさせる内的促しにまでなって、呼び帰そうとしている。そのことへの驚きが、私に浄土真宗の教えを尋ねさせる要因となりました。
しかし問題はそこからでした。私は、自己の内奥の願いに目覚めた、私の主体はここにあるという思いに囚われていきました。いわば、我が身にかけられた如来の願いを「私の願い」として私有し、自分を固める手段としてしまっていたのです。自我の意志と混同された願い、知識化された教えは自我を肥大させ、私は道を求めるほどに、その「教え」をもって自他を裁く審判者となり孤独化していきました。
そのような流転のなかで入学した大谷専修学院においては、師友との生活を通して、二つのことを教えられました。それは「たすけられなければならない者」「自分を愛する」ということです。自分が如来からたすけられなければならないほど深い罪を抱えている。その罪とは、自分が自分自身を軽蔑しているということでした。
与えられた我が身を無条件に尊重し愛することができない自己嫌悪と、それによる劣等感が、生きる喜びを失わせ虚無を生み出していたのです。そのことを知らず、自分を責め裁くことが誠実さであるとさえ思い込んでいたのでした。
それは同時に、自己嫌悪の思いから、他者はこんな自分を軽蔑しているに違いないと決めつけ、自分から人を遠ざけていた罪でもあります。虚無の大海と思い込んでいたなかには、私を大切にしようとして関わってくれていた人、苦悩しながら現実を担って生きている人々がいるにも拘らず、自分の思いがそれを見えなくさせていたのでした。
その愚かな在り方を悲しみ、たすけんとする心から如来の本願は発されていたのです。同時に、その「大悲の願」は、私の身に如来の悲しみが聞き遂げられることを願い、如来の名号(真実行・大悲の願の現行)、すなわち諸仏の称名にまでなって私に呼びかけていたのでした。それを教えてくださったのが、表題のお言葉です。
真実行が誓われる諸仏称名の願は「諸仏咨嗟の願」とも呼ばれます。『六要鈔』では、この字について、「咨也、嘆也、痛惜也」(『真聖全二』二三一頁)と註記されています。そのように如来(法)から痛まれている身(機)であることを知らず、「私が」と確固たる主体(邪見の我)を立てようとする機法の分限の混乱が私にはありました。
愚かさを悲しまれ、教えられていく凡夫の分限を忘れて、「私が」という自負を固める愚かな自分を、絶えず諸仏の称名に教えられていきたいと思っています。
(教学研究所研究員・中山善雄)
[教研だより(147)]『真宗2018年10月号』より
※役職等は発行時のまま掲載しています。