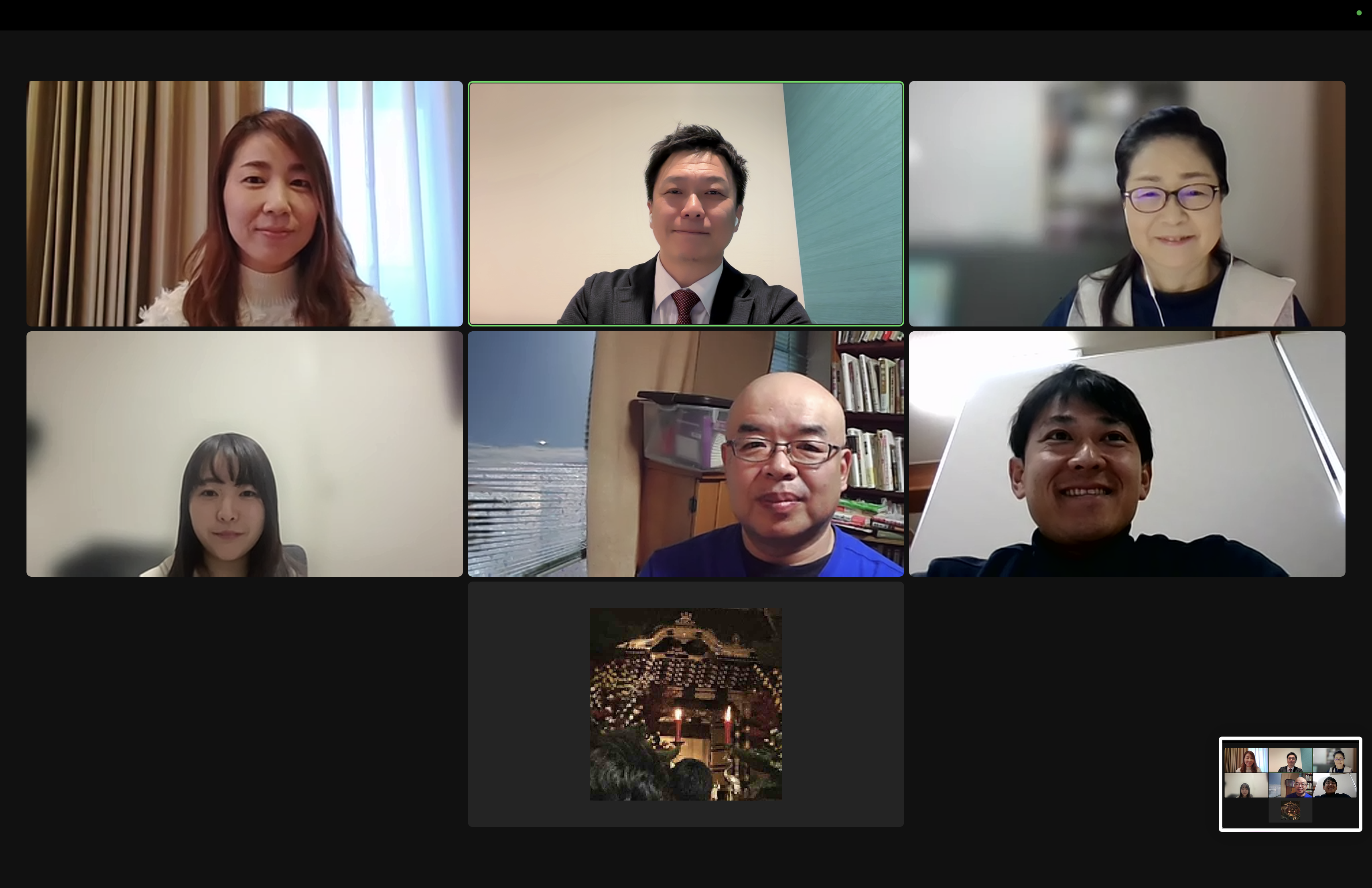<ハンセン病問題に関する懇談会 広報部会チーフ 酒井義一>
ハンセン病療養所・多磨全生園の方々とお付き合いが始まった当初は、つらい過去を思い出させてはいけないという思いから、ハンセン病の話題を避けていました。それがやさしさだと思ってもいました。しかし、それは本当のやさしさなどではありませんでした。
そのことを教えてくれたのは、一九九八年から始まったハンセン病国賠訴訟でした。訴訟をきっかけに、ハンセン病だった多くの方々が、長い沈黙を破り、自らの体験や今の思いを語り始めたのでした。それは単に過去の話なのではなく、そのことによって今なお深い傷を負っているという、今の自分を語る真剣な場面でした。
身のふるえる思いをしながら、私はその話をお聞きしました。自分を語る言葉を持つということの力強さと大切さを、強く感じました。そして同時に、長い間この方々のことを何も知らないままでいた自分を痛感しました。人々の声を隔離してきたのは、国の隔離政策だけではなく、実は私もそのひとりだったのです。
聞くべき声をちゃんと聞いていくこと、自分を語る言葉を持つこと。私もそのような歩みができる人間になりたい、と強く思いました。
あと数十年たつと日本からハンセン病回復者はおられなくなる、と言われています。
しかし、言うまでもないことですが、その時がハンセン病問題の終息なのではありません。ハンセン病問題を人間の課題として学んでいくことには、終わりはないのです。
思いつくまま、考えられる私たちの課題を列挙してみます。
・ハンセン病の歴史を学ぶ。
・その中を生きた人々の歩みや願いを知る。
・大谷派がなぜ過ちを犯したのかを探る。
・ハンセン病問題を通じた交流を図る。
・解決すべき政治的課題は、実践的に動く。
・自らが学んだ課題を言語化し、発信する。
ハンセン病問題からの呼びかけに耳を澄ませ、何が自分に問われているのかをじっくりと考え、自らが学んだ課題を自分の言葉で表現していくこと。
そのような歩みを終わらせないことが、私の課題です。
─ハンセン病問題とグリーフケア
ところでハンセン病問題とは、人間を見失っていくという質を持った問題です。同じような問題は、時代・社会に山積しています。次に、ハンセン病問題からの広がりということを考えてみたいと思います。
二〇〇七年から自坊で始まった「グリーフケアのつどい」という動きは、私にとってハンセン病問題の延長にある動きです。グリーフケアとは、死別などによって悲しみを抱えた人々が、それぞれの体験や今の思いを語り合うつどいのことです。
多くの方々がやって来られます。それは裏を返せば、多くの方々が自らに起こった出来事や今の思いを語る居場所を探し求めているということです。
ある時、事故で夫を失った女性はこう語られました。「みんなあの事故のことを知っているのに、誰もそのことにふれようとしない。何ごともなかったかのように…。それがとても辛い」。
語るべきことが本当はたくさんあるのに、それが語れないという辛さを表現されたのです。ここにも隔離があります。そして同時に、自らを表現できる居場所を懸命に探す人が、そこにおられます。
自分を語る言葉を持つということは、とても大切なことです。悲しみが深い縁となって、人と人とがつながっていくからです。
悲しみをなくすのではなく、悲しみが大きな縁となって、悲しみの意味を訪ねていく歩みが始まっていくことを、人は心の奥底で願い求めているのではないでしょうか。
─ハンセン病問題と東日本大震災
東日本大震災の直後、あるハンセン病回復者はこう語られました。
「ある日突然家を失い、家族を失い、友人を失い、故郷を失う。状況は違うがすべて私が体験したこと。あの人たちの悲しみは私の悲しみだ」。
被災者の悲しみを、我が悲しみとしようとする人がそこにおられます。状況はそれぞれ個別であり、状況を共有することはできません。しかし、悲しみは響きあうものです。そこに共感の世界が広がっていきます。
国の政策として推し進められたハンセン病隔離政策と原子力行政。状況は個別ですが、問題の本質はよく似ています。その底に「人間を見失う」という共通の課題が横たわっているからです。
個別の問題に取り組むことをとおして、普遍的な課題を生きる。そんなしなやかな生き方を獲得していきたいものです。
ハンセン病問題には、ふるさと問題や医療の充実などの個別な問題があります。しかし、その底には普遍的な課題もあります。
ハンセン病問題や東日本大震災やグリーフケアの底に流れる課題とは、人間を見失っていく社会や自己の闇をきちんと見抜いていくということではないでしょうか。
そして、ひとりの人間を、道を求めて歩む同朋として見出していくということだと受けとめています。
それは、人間に与えられた普遍的な課題です。そのような課題をこそ生きる者でありたいと思います。
(二〇一四年八月二十四日記す)

《ことば》
「住み慣れた楽生院は第二の故郷なんだよ。」
日本の統治時代に台湾にもハンセン病療養所楽生院が作られた。
幹線道路に近い斜面に建設され、当時は寂しいところであったが、今では地下鉄の駅ができ、楽生院を取り壊して地下鉄の車庫と整備工場を作ろうと工事が進んでいる。すぐそばまで住宅が迫り、こんもりとした緑の山である楽生院も訪問するたびに取り壊されていっている。
京都での交流集会にも来てくれたさんは、統治時代に「公学校」へ通っていたせいか日本語が堪能だ。私たちが楽生院へ行くと、電動車で坂の多い園内を案内してくれる。統治時代に作られた建物は古く、不便なのにここを桃源郷だという。
「花や野菜を育てたり、マングローブの木の下で歌を歌ったり、仲間とここで死ぬまで暮らしたい。便利かもしれないが、庭もない新病棟のビルに移るのは絶対に嫌だ。それは第二の隔離だ」。
そう言っていたさんは膝から下のない脚が悪化して電動車にも乗れなくなり、五年前に新病棟に移った。
韓国の療養所でも感じたことだが、病院とは名ばかりで十分な治療も受けられず生きるための生活で手足を失った人が本当に多い。
想い出の詰まった我が家で人生の最期を送ることができ、歴史的な負の遺産として楽生院が保存されることを願ってやまない。
(大阪教区・小松裕子)
真宗大谷派宗務所発行『真宗』誌2014年10月号より