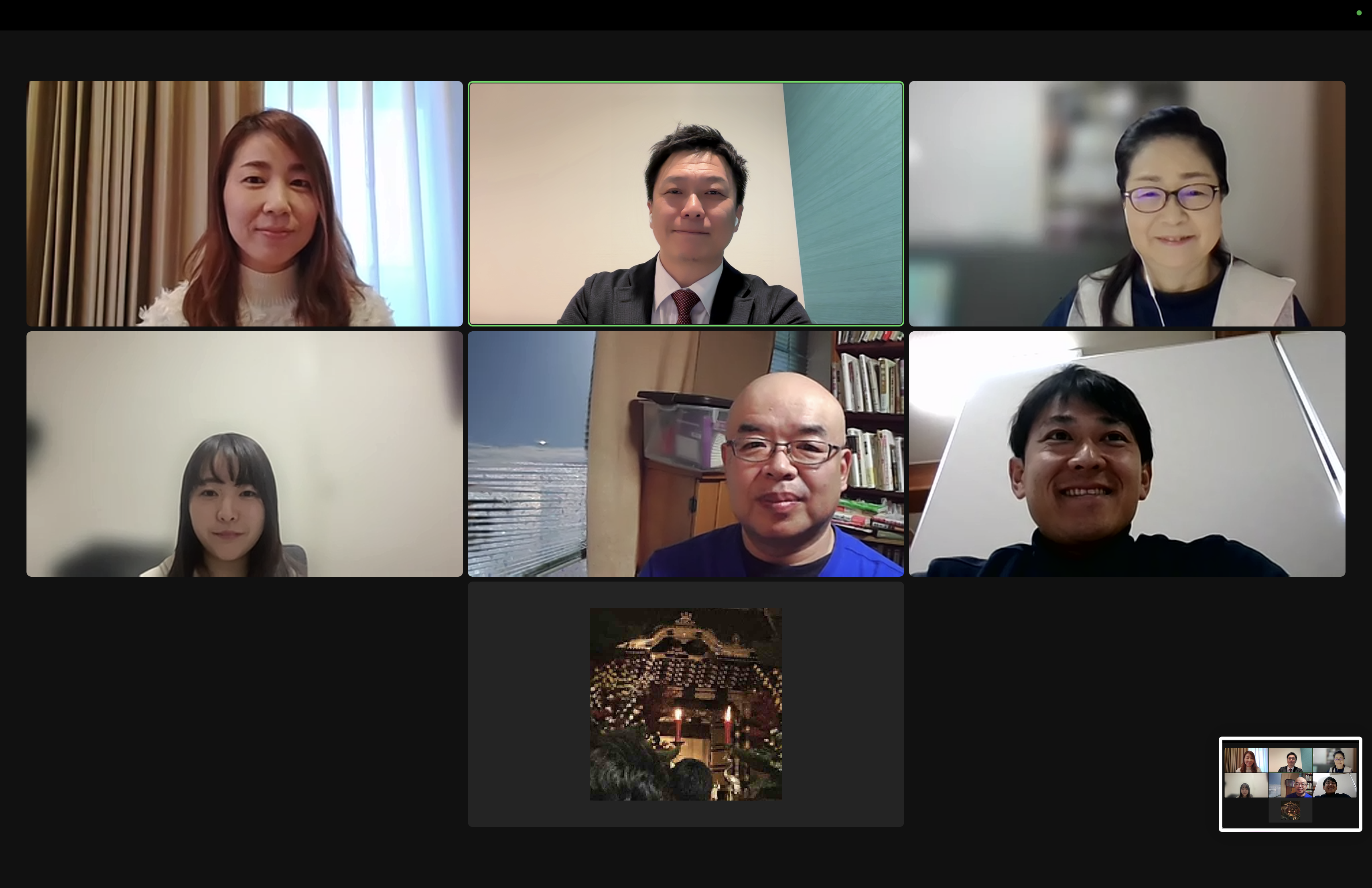立教開宗の願いに帰る
宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要まで、あと一年となりました。宗門は、今から四十九年前の一九七三年、教団問題を抱える中、親鸞聖人御誕生八百年・立教開宗七百五十年慶讃法要を勤めました。
新型コロナウイルス感染症という難問もさることながら、私たちは今、世界的にも国内的にも多くの問題を抱えた中で法要を迎えようとしています。ことに新型コロナウイルス感染症によって人と接することに配慮をせざるを得ない状況は、宗教活動の障害となっています。このような状況の中で想起されるのは、先輩諸氏が教団問題を抱えながら、慶讃法要を勤めるべく意欲されたことです。それというのも、親鸞聖人の立教開宗は、聖道諸宗に対する絶望の中にあって、聖人御自身の本願との出遇いから始まったからなのです。
危機と立教開宗
公益財団法人 全日本仏教会発行の季刊誌『全仏』六五一号(二〇二一年一〇月一日発行)に「お寺の未来~新聞記者の憂い」という特集を組んで赤堀正卓氏(産経新聞社 終活読本ソナエ編集長)が「葬儀から僧侶が消える~取材を通じて懸念する将来像~」という文を書いています。
「葬儀社は十年以上前から社員教育・研修でグリーフケアを徹底して学んできている」という現状の中で、「すでに「寄り添うこと」や「グリーフケア」という分野では、僧侶は葬儀業者にはかなわないのだ。そんなことより、「葬儀における宗教的な意義」とは何なのか。足元を見つめなおしてみる必要はないだろうか。この領域は、宗教者にしかできないのだから」と述べ、「自分の寺が三十年後に、どのような姿になっているのか。消えているのか、存続しているのか。もし存続させるべきと考えるのであれば、そのための僧侶の問題意識、将来ビジョン、やる気をもう一度、再点検する必要があると思っている」と結論づけています。
かつて、「捨てられる前に捨てている」という言葉を聞いたことがあります。この言葉をすべてに当てはめることはできませんが、僧侶と門徒の方々との関係に当てはめてみた場合、厳しい指摘であると思います。自身が民衆であることを忘れた僧侶は、いろいろな思い違いをしてきたのではないでしょうか。親鸞聖人は「他力真実のむねをあかせるもろもろの聖教は、本願を信じ、念仏をもうさば仏になる」(『歎異抄』第十二章)、ただこのことを伝えるためにご苦労されました。このような聖人の教えに学ぶ者に「葬儀の執行者である僧侶」と「執行してもらう民衆」などという関係はあり得ないはずです。僧侶自身が親鸞聖人と同一の信心でありたいという願いを忘れて、民衆を見捨てていたのではないでしょうか。
危機感から危機意識へ
近代の真宗の教化は『歎異抄』を抜きに語ることはできません。『歎異抄』の「前序」には「先師口伝の真信に異なることを歎き、後学相続の疑惑有ることを思うに、幸に有縁の知識に依らずは、争でか易行の一門に入ることを得んや」と説かれています。教えられたことを純粋に受け止めること、そして我流の解釈をして他力の宗旨を誤らぬことが願われています。
人は誰でも、自分の生活を脅かすものに対しては危機感を覚えます。しかし、その危機感の根拠を問うことが大切です。危機感を覚えた自分が教えによって真実に向かって開かれていくところに宗教の役割があり、それによって明確にされた課題をさらに深める力となるものこそ危機意識と言えるのではないでしょうか。危機を怖れるだけではなく、求道につながる危機意識に置換されることが大切です。
教学と教化
一九五八年七月に、それまでの「教化研究所」が「教学研究所」に改称されました。
教えを教えにする為には、私自身が身を以つて受けとることが何よりも大切であり、教えの深さが、わが身の迷いの深さを貫いて頂けて行く。それが学ということであるに違いない。学ぶというと世間一般の常識からは頭で学ぶことに考えられ勝ちであるがそうではない。学ぶは身を以つて学ぶのである。自己の迷いの、苦悩をひつさげて教法に聞くのである。
教化という言葉には、熱心の余りであろうが教えるということが強く意識されて、学ぶという面がどうしても閑却されがちの傾きが、響きがあつた。 …中略…
教えを頂けば頂いた教えが教えの用きとして他に伝わる。それを教化というのであろう。深く教えを頂いたものだけが、深く教法を伝え得る。こういう意味で教化は根本的には教学なのである。
教化研究所が教学研究所と改称されたのは、決して一般大衆に通じない難しいことを研究しようというのではなくて、教化の根本にかえることであり、それによつて従来教化といわれて来たものを生きたもの、本当の教化たらしめるという願いからに他ならぬ。言いかえれば教団全体を如来の教法の用かれる場所にしよう、こういう願いの実現なのである。
(『真宗』一九五八年八月号)
「教化」というと、人間が人間に教えるというイメージがあります。「教学」というと難解な論理と知識が予想されます。しかしそのいずれも、親鸞聖人の立教開宗の願いとするものとは異なるのでしょう。教学は自らが「一人の念仏者」となることに主眼のある求道の学であり、教化は他に「一人の念仏者の誕生」を願う報恩の歩みなのであります。
先に寺院の置かれた厳しい状況、そして危機感ということを申し上げました。このような中、天親菩薩の言葉が私たちに何を願って生きているのかを問うています。
何等の世界にか、仏法功徳の宝ましまさぬ。
我願わくはみな往生して、仏法を示すこと仏のごとくせんと。
(『浄土論』『真宗聖典』一三八頁)
「極楽はたのしむ」ところではないと言いつつ、思い通りにならないと恐れや怯えを感じてしまいます。しかし天親菩薩が教えて下さったのは、念仏こそが功徳大宝海であるということです。だからこそ、仏法功徳の宝ましまさぬ世界に生まれたとしても、念仏者にとっては往生一定なのです。
俳優であった植木等氏の父親、植木徹誠氏は真宗の僧侶であり社会主義者として労働運動、部落解放運動に生きた人です。
おやじは、死人の供養をして、お布施で生活することに満足していなかった。後日、妹真澄の夫、川村善二郎がおやじに「社会運動をやっていた者が宗教界に入ることに矛盾を感じなかったか」とたずねると、おやじは「なあに、社会が変わっても夫婦げんかは無くならないから、坊主のやる仕事はあると思った」といって笑ったそうだ。おやじの関心事は、いつの場合も、夫婦げんかを含めて現実社会の問題を解決することにあったようだ。
(植木等著『夢を食いつづけた男』八七頁、ちくま文庫)
「社会が変わっても、坊主のやる仕事はある」という言葉は心に沁みます。葬儀から僧侶が消えることが僧侶の死ではありません。「我願わくはみな往生して、仏法を示すこと仏のごとくせんと」という願心に教えられ、「共に念仏者となりたい」という生活にこそ僧侶のいのちがあります。そのことを見失う時が、“僧侶の死”なのです。
([教研だより(186)]『真宗』2022年1月号より)